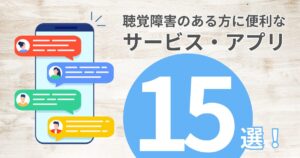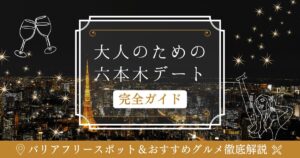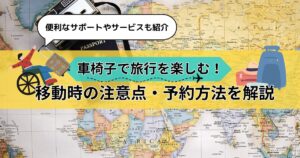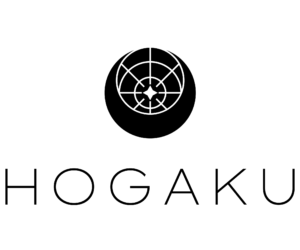皆さんは普段、移動に高速道路を利用しますか?
身体障害者にとって車は、便利で体力的にも負担の少ない移動手段ですよね。
今回は、高速道路をはじめとする有料道路の障害者割引について、利用や申請方法について解説していきましょう。
また、令和5年3月に高速道路における障害者割引制度が見直されたので、どのように変わったのかも解説しています。
通院や旅行などで高速道路を利用する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
1.障害者手帳での高速道路や有料道路の割引制度とは?
そもそも、「高速道路や有料道路が障害者手帳の割引対象になっていることを知らなかった」という方も多いのではないでしょうか?
障害者手帳での高速道路の割引制度とは、障害者の方の自立と社会経済活動支援を目的とした制度です。
通学・通勤・通院などの日常生活での移動の際に、高速道路の料金が割引率50%(10円未満の端数は切り上げ)になります。
有料道路は、主にNEXCO東日本や西日本、中日本など地域ごとに分かれていますが、いずれの地域でも障害者手帳による高速道路割引制度が統一的に実施されています。
高速道路割引制度は、他の利用者から徴収される料金で賄われているため、目的や対象車両については一定の要件が設けられています。
また、割引を受けるためには、ただ単に身体障害者手帳を所持しているだけでなく、事前に車両の登録や書類の申請手続きなどが必要です。
次の項目では、高速道路割引制度の対象となる障害者の範囲や条件についてみていきましょう。
2.障害者割引の対象となる障害者の範囲
2-1.障害者本人が運転する場合
障害者本人が運転する場合は、身体障害者の交付を受けている方が対象です。
障害の等級は関係なく、手帳交付の対象となる1〜6級のうちどの等級であっても割引の対象となります。
そのため、日常的に運転をする多くの身体障害者にとっては、優良な制度だといえるでしょう。
2-2.障害者が同乗し、本人以外の人物が運転する場合
次に、障害者以外の人物が運転し障害者が同乗している場合の対象となるには、身体障害者手帳または療育手帳のうち「重度障害者」に認定されていることが条件です。
たとえば、重度身体障害者とは1級や2級または、3級程度の障害が2つ以上重複している方です。
15歳未満の身体障害者は、保護者に障害者手帳が交付されることになっていますが、障害者本人が同乗していない場合は割引の適用外になるので注意してください。
療育手帳の場合は、A判定を受けている障害者が対象になります。
重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じなので、確認してみましょう。
また、対象となる障害者が重度障害者なのかわからない場合は、お住まいの市町村にある福祉相談窓口に尋ねてみることをおすすめします。障害者手帳の種類や申請方法、取得することでどのようなメリット・デメリットがあるのかなどは以下の記事で徹底解説しているので、是非ご覧ください。
参照:障害者手帳の申請方法や取得するメリット・デメリットを徹底解説!
2-3.精神障害者は障害者割引の対象外
精神障害者は高速道路や有料道路の障害者割引の対象にはなりません。
その主な理由は、障害者割引に対して国からの補助を受けていないためです。
現在の有料道路制度は道路の建設や管理などにかかる費用を借入金でまかなっていて、利用者から徴収している料金収入により借入金を返済していく形で成立しています。国や自治体からの助成はありません。
もし障害者割引を適用する場合、事業者としては障害者割引分の負担額が減収につながるのです。
このように利用者の通行料に支えられている関係上、割引適用の対象となる範囲を絞らざるを得ないため、精神障害者は対象外となっているのです。
参照:なぜ精神障がい者を障害者割引の対象としないのですか。|NEXCO東日本
精神障害者に対してすぐに障害者割引を適用することは現状困難である一方で、 他の有料道路事業者や関係機関と連携して、今後見直す余地はあるとNEXCO東日本は表明しています。
なお、2024年4月にJRグループや東京メトロ、大手私鉄などの鉄道関連事業者は、精神障害者も割引対象になることを明らかにしました。
JRグループでは、2025年4月1日より介護者の方と一緒に利用する場合と精神障害者保健福祉手帳を持つ方1名で利用する場合に、それぞれ5割引きになるサービスの提供を始めます。
このような動きが高速道路や有料道路でも進むことを願います。
3.障害者割引の対象となる自動車の範囲
障害者手帳での高速道路料金制度では、1人1台まで自家用車の事前登録が可能です。
以前は、高速道路における障害者割引制度で対象となる車両は、事前登録を行った自家用車のみでした。
レンタカーや介護タクシーなどは事前登録ができないため、障害者割引の対象外となっていました。
令和5年3月に1人1台要件が緩和されたことで、現在は割引対象となる障害者が運転または同乗している車両かつ一定条件を満たしていれば、事前登録していなくても高速道路料金の割引対象となります。
ただし、事前登録していない車両を利用する場合も、障害者割引の申請は前もって行う必要があるので注意しましょう。また、料金所で身体障害者手帳または療育手帳の提示が求められるので必ず用意しましょう。
割引の対象となる要件や車両の種類については、NEXCO西日本の公式サイト「対象となる自動車の範囲について」の表を参考にしてください。
参照:対象となる自動車の範囲について|有料道路における障がい者割引制度についてのご案内|NEXCO西日本
参照:令和5年3月27日の有料道路における障害者割引制度の見直しによる「1人1台要件の緩和」とは何か教えてください。|NEXCO東日本
4.障害者手帳での高速道路割引の申請方法
4-1.市区町村の福祉担当窓口で申請する場合
市町村の福祉担当窓口での申請は、ETC通行を利用する場合と利用しない場合、両方の割引に対応しています。
ETC通行(ノンストップ走行)を利用しない場合の申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 事前登録を希望する自動車の自動車検査証等(車検証)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合にのみ必要)
- 委任状(本人以外が代理で申請する場合にのみ必要)
- 割賦契約書又はリース契約書(分割購入やリースの車を利用している場合のみ必要)
申請完了後、窓口で割引適用を証明するシールが発行されるので、身体障害者手帳や療育手帳に貼り付ければ完了です。
ETC通行を希望する場合は、上記に加えて以下の書類が必要になります。
- ETCカード
- 自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ証明書・申込書」
ETCカードは、基本的に本人名義のものに限りますが、対象となる障害者が未成年の重度障害者で本人以外が運転しなければならない場合は、特例として親権者や後見人名義のETCカードでも登録可能です。
窓口での申請は、制度に詳しい担当者から説明を受けながら行えるので、わからない事があればすぐに聞けるのがメリットです。
4-2.オンラインで申請する場合
オンラインでの高速道路割引の申請は、ETC限定となります。
以前の高速道路における障害者割引制度では、事前の登録・申請をするために市町村の窓口に直接出向かなければなりませんでした。
しかし、外出が困難な身体障害者や重度障害者の方が外出して申請をするのは体力的にも難しく、親族が代わりに申請するのにも委任状などの手続きがあり、手間がかかってしまいます。
そこで、申請者の負担と申請窓口の事務作業を軽減するために、令和5年3月の見直しにより高速道路会社のサイトフォームからオンライン申請が可能になりました。
オンライン申請での必要書類は、以下の通りです。
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 通知が受け取れるメールアドレス
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合にのみ必要)
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 障害者ご本人名義のETCカード(未成年者かつ本人が運転しない場合は親権者か法定後継人名義)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
- 住民票(本人名義以外の車両・ETCカードを登録される場合)
- リース契約書又は割賦契約書(リースや分割購入の車を利用している場合にのみ必要)
オンライン申請には「マイナポータルへの利用者登録」および「マイナポータルアプリ」が必要になるので、事前にスマートフォンで登録しておくようにしましょう。
登録手順については、以下を参考にしてみてください。
申請受付が完了すると、入力したメールアドレスに申請完了メールが届きます。
その後は申請内容に不備がないか確認し、割引が適応されるかどうかの審査が行われます。
審査結果についても、メールで通知がくるシステムです。
また、登録完了後は郵送にて障害者割引を証明するシールが郵送されるので、自分で身体障害者手帳や療育手帳の所定の位置に貼り付けましょう。
参照:申請のご案内|有料道路における障害者割引制度のオンライン申請
5.高速道路における障害者割引制度の利用方法
5-1.事前に登録されていない車両を利用または現金で支払う場合
知人の車や旅先でのレンタカーなど事前にETC登録をしていない車両で障害者割引制度を利用する場合や、現金を使用する場合は、高速道路の料金所で直接支払いを行います。
降車する高速道路の料金所で身体障害者手帳や療育手帳を提示して、割引に必要な事項が記載されているかどうかを高速道路の係員がチェックします。
タクシーや福祉有償運送車の場合も、手帳の提示を求められるので障害者手帳は常に携帯しておくのがベストです。
また、障害者手帳アプリの「ミライロID」に登録した障害者手帳の提示でも代用可能です。ミライロIDでの高速道路割引の利用方法や登録の詳細については、以下を参考にしてください。
5-2.ETC無線通行(ノンストップ走行)の場合
事前に登録したETCカードを併せて事前登録したETC車載器に挿入して、正常に作動していることを確認した上で、料金所のETCレーンを通過します。
なお、料金所では割引前の利用料金が表示されますが、ETCレーン通過後にデータをシステム上で確認し割引が適応されます。
ETC無線通行の場合は、基本的に障害者手帳の提示は不要ですが、ETCが設置されていない料金所やレーンの点検整備などでETCの料金所が利用できない場合は提示が必要です。
また、事前登録したETCカードと車載器番号が一致しない場合は、割引適用外となるので注意してください。
6.障害者割引に有効期限はある?(ご当地ナンバー変更後も更新が必要)
高速道路や有料道路の障害者割引は、有効期限が設けられている制度なので更新が必要です。
新規申請および変更申請後の有効期限については、申請日からその後の2回目の誕生日までです。
たとえば、申請日が2023年11月で申請者の誕生日が1月である場合、有効期限は2025年の1月まで有効になります。
変更申請が必要なケースは、ETCカード番号や自動車登録番号の変更などがあります。
最近では、ナンバープレートをご当地ナンバーに変更する方も多いですが、そのような場合も変更申請が必要なので注意しましょう。
また、更新申請については有効期限2ヶ月前から前日まで可能で、申請日から3回目の誕生日までが割引有効期間となります。
ただし、申請日から3回目の誕生日までが2年2ヶ月を超える場合は、申請日から2回目の誕生日までが割引有効期間です。
有効期限に関する通知については、ETC申請されている方のみ、有料道路ETC割引登録係より申請時に記入した住所に郵送にて届くようになっています。
市町村の窓口で申請された方については、自治体によって通知方法が異なりますので、申請時に確認しておくことをおすすめします。
7.まとめ
障害者手帳での高速道路や有料道路の料金割引制度、申請方法などについて解説しました。
制度の見直しによってオンライン申請ができるようになったり、1人1台という条件が緩和されたりしたことで、より制度が利用しやすくなりました。
高速道路料金が割引になると、さらに社会活動の幅が広がり、外出をするきっかけにもなるでしょう。
事前申請は複雑で難しい部分もあるので、お住まいの社会福祉担当窓口でアドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。
また、スマートフォンの扱いに慣れている人は、オンライン申請も検討してみてください。
ぜひ、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、高速道路料金の割引制度を申請して活動の場を広げてみてはいかがでしょうか?
Ayumiでは、交通機関の情報と合わせてバリアフリーな旅行や観光地情報を発信しているので、ぜひこちらのカテゴリーもご覧ください。
参照:旅行/観光|Ayumi