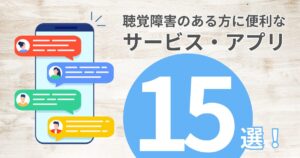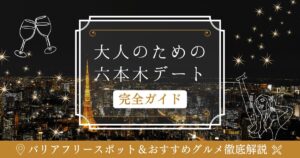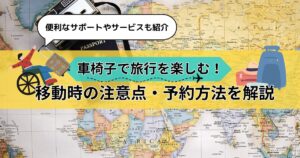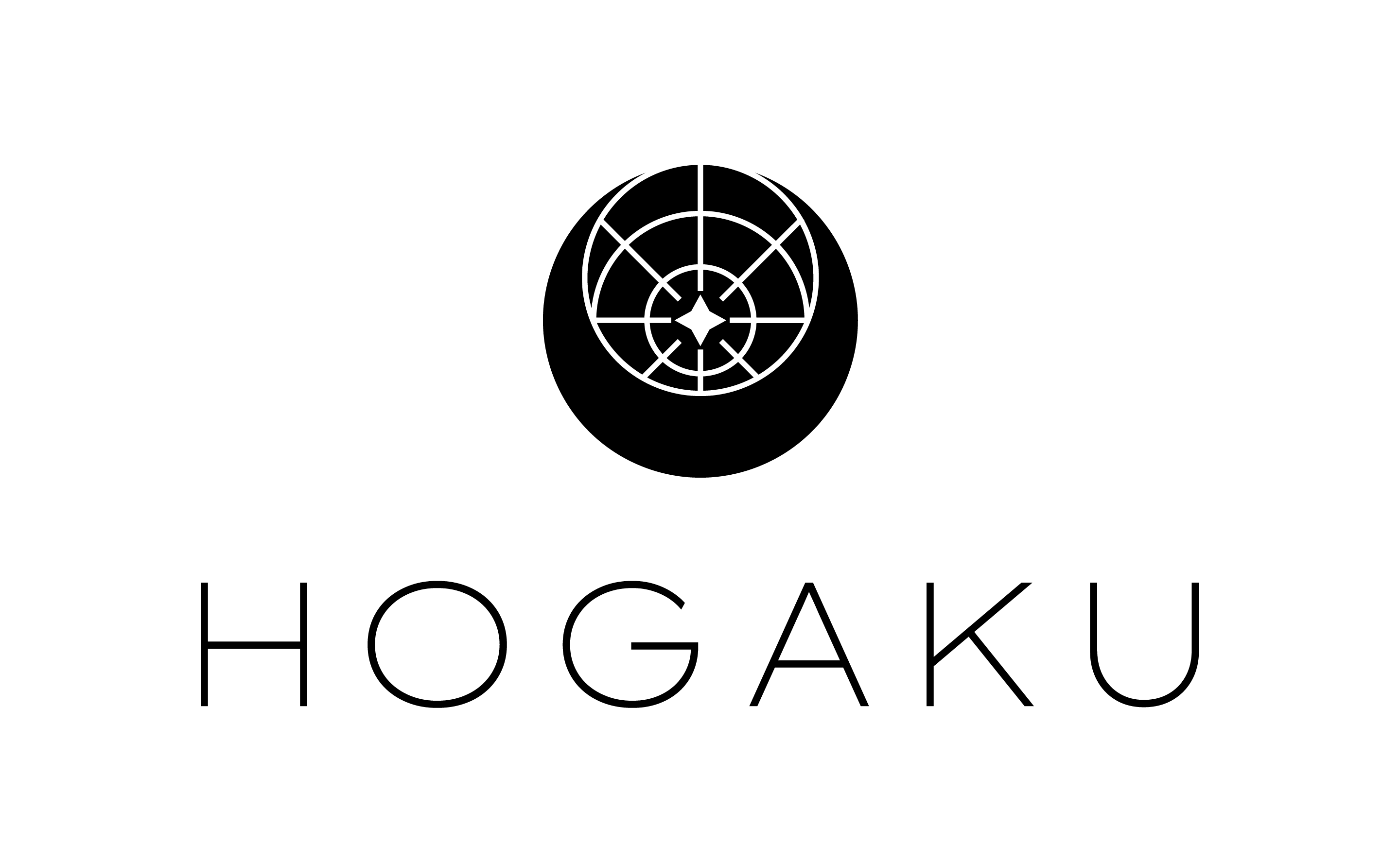34歳で脳出血を発症し、半身麻痺となったいずみともひろさん。現在は復職を果たし、当事者のためのおしゃべり会開催やSNSの発信など、積極的に活動されています。
今回は、病気との向き合い方や社会復帰への道のり、そして今後の展望について伺いました。
目次
1. いずみともひろさんってどんな人?
1-1. 建築への情熱と社会人としてのキャリア
【インタビュアー(ライター):赤石/インタビュイー:いずみともひろさん】
赤石:子供の頃の性格はどんな感じでしたか?
いずみさん:子供の頃はおとなしい性格でした。
中学校までは田舎の学校で過ごしていましたが、高校で名古屋駅近くの高校に進学し、都会的な人たちと出会ったことで、ファッションやスニーカーなどにも興味を持ち始めました。
赤石:当時の夢は何だったのですか?
いずみさん:設計士になりたかったんです。
大学も建築学部に進みましたが、実際に勉強してみると設計は自分に向いていないと感じました。結局は雑誌の真似事みたいなもので、自分だけのものが何もないと思ったんです。
でも建築自体は好きだったので、ゼネコンに就職し、建物を建てる方の仕事を選びました。
意匠建築も手がける会社で、私がよく通っていた大学時代のインテリアショップなどを建てた会社です。建物と関われることに魅力を感じていました。
赤石:社会人としてのキャリアについて教えてください。
いずみさん:現場監督として働き始め、15年間キャリアを積んできました。薬局、ホームセンターなどの建物や事務所ビルの建設を手がけてきました。
1-2.突然の脳出血、2週間の意識不明から目覚めた世界
赤石:いずみさんが脳出血を発症された経緯について教えていただけますか?
いずみさん:実は2回倒れているんです。
1回目は34歳の時、当時の彼女と公園で遊んでいたら突然力が入らなくなり、立てなくなってしまいました。
病院で検査を受けたところ、脳梗塞と「もやもや病」という難病が見つかりました。
もやもや病とは、脳に血流を与えるための血管が閉塞してしまう病気です。血流が回らないと生活できないので、自分自身で毛細血管を作ってしまうのですが、その毛細血管が詰まりやすく破裂しやすいという特徴があります。
1度目の発症では後遺症もありませんでしたが、「もやもや病」が進行していた為、バイパス手術を受けました。手術は成功し、体調も時間とともに回復していきました。
しかし、手術をして3か月後、友人とカラオケに行った後、トイレで突然倒れて2週間意識不明になりました。
これが脳出血でした。
赤石:意識が戻った時のことは覚えていますか?
いずみさん:トイレに行ったことまでは覚えていますが、その後の記憶はあいまいです。
意識が戻った時は手にミトンをつけられ、ベッドに縛り付けられていました。最初は「ここから逃げ出さなければ」と思いましたが、実際には体が全く動かない状態でした。
1-3. 入院生活での葛藤
いずみさん:急性期の入院は本当につらかったです。
おむつ生活で、カテーテルを入れられ、下剤を飲まされて「そのままトイレをしてください」と言われました。34歳でおむつをしたことがなかったので、本当に辛かったですね。
また、何でもできた自分から何もできない自分へと一変してしまいました。
お風呂もストレッチャーで運ばれて体を洗われる状態でした。そういう経験は精神的にもかなり厳しかったです。
赤石:どのくらいの期間入院されていたのですか?
いずみさん:リハビリを含めて合計5ヶ月ほど入院していました。最初の1ヶ月は急性期で過ごし、その後4ヶ月はリハビリに専念しました。
2. 社会復帰への道のり
2-1. 体が動かないという現実との向き合い方
赤石:体が動かないという事実をどう受け止めましたか?
いずみさん:リハビリでは歩く練習をするのですが、指示されても全く体が動かせず、「どうやって歩いていたのだろう」と思いました。
車椅子でも体幹がなく、トイレに行っても左側に倒れてしまうこともあったんです。
ショックではありましたが、現場監督の経験から「できないことがあれば、どうすればうまくいくか考える」を常に考えて生きてきたので、「体が動かないならリハビリを頑張ろう」と前向きに捉えることができました。
右足のアキレス腱を切った過去の経験から、リハビリに取り組めば回復できるという自信もありました。
絶望して泣いたりすることもなく、入院中に病気のことでずっと悩んだという記憶はありません。
2-2. 就労移行支援施設での経験
いずみさん:リハビリ病院退院後は家に引きこもりがちになり、何もすることなく過ごしていました。そんな時、病院に勧められて就労移行支援施設に通い始めました。
そこで強制的に家から出るきっかけが生まれました。また、同じ脳卒中を経験した同年代の人と出会い、お互いの状況を共有できたことが大きな支えになりました。
赤石:就労移行支援施設ではどのようなことをされていましたか?
いずみさん:エクセルでの入力作業や間違い探しなど、社会復帰に向けた基礎的なトレーニングをしていました。最初はできないことが多く自信をなくしましたが、10ヶ月の訓練を経て少しずつ自分を取り戻していきました。
また、就労移行支援施設に通う中で、金曜日には友人と飲みに行くという週末の楽しみもできて、社会とのつながりを感じられるようになりましたね。
3.職場への復帰と新たな挑戦
3-1.「できないこと」を正直に伝える
いずみさん:復職に向けては、まず自分の症状を会社に全部伝えました。
注意障害や見落としが多いこと、マルチタスクができないことなどを伝え、会社から「この業務ならできるのでは」と提案された仕事を訓練しました。
指導員さんと一緒に手順書を作り、実際に会社でその業務ができるか試す機会をもらいました。うまくいったので、1ヶ月間お給料なしで出社する「試し出勤」を経て、正式に復職することができました。
赤石:復職されてみていかがでしたか?
いずみさん:復職後は自分のできる範囲で仕事を続けています。現在は現場監督の仕事はできないので、パソコンを使って書類のチェックや若手の育成などを担当しています。
3-2.全国から仲間が集まる「おしゃべり会」
赤石:SNS発信を始めたきっかけを教えてください。
いずみさん:入院中にスマホで情報を集めていたのですが、エスカレーターの乗り方や入浴方法など、実際の当事者目線での情報がほとんどありませんでした。特に社会復帰の方法や働き方についての情報は皆無だったんです。
無いなら、自分が欲しかった情報を自分で発信しようと思い、自分自身の経験を発信するようになりました。
最初はYoutubeだけをやっていて、あまり多くの人に見られていなかったのですが、ある時マッチングアプリで出会った女性から「あなたは凄い良いこと言ってるんだからもっと多くの人に発信した方がいい」と言われたんです。
「けど、僕は編集出来ないし、何を伝えれば良いか分からない」と答えましたが、「なら私と会話をして、その中から良いと思ったものを原稿にしよう」と提案してくれて、それからショート動画の編集を手伝ってくれるようになり、SNSでの発信が大きく変わりました。
その結果、Instagramのフォロワーは20,000人を超えるまでに成長しました。その人の存在が本当に大きな助けとなっています。
赤石:現在はどのような活動をされているのですか?
いずみさん:本業とは別で喫茶ドリームで週末働きながら、月に1〜2回「おしゃべり会」を開催しています。
SNSを通じて、全国から参加者が来てくれて、東京や岡山、広島などからわざわざ来てくれる方もいます。
このおしゃべり会は、病気や障害を持つ人が家から出るきっかけになればと思って始めました。参加者同士がつながり、コミュニティができることで、社会参加を促進したいと考えています。
4. やりたいことを口に出せば、現実になる
赤石:今後の目標について教えてください。
いずみさん:全国各地でおしゃべり会を開催し、より多くの当事者をつなげていきたいです。
自分が会いに行くことで、参加者同士がつながり、コミュニティが育つきっかけを作りたいと思っています。
今年の5月からは助成金の活用も検討しながら本格的に始動する予定です。
赤石:最後に、一歩を踏み出せない人へのメッセージをお願いします。
いずみさん:まずは「やりたいこと」を口に出してほしいです。
頭の中だけで諦めないでください。無理だと言われるかもしれませんが、やったことがない人や無理だと思い込んでいる人の言葉よりも、自分の思いを大切にしてほしいと思います。
例えば、僕がスニーカーを履きたいと言ったとき、「麻痺が重いから無理」と言われました。でも諦めずにリハビリを続けた結果、今はスニーカーを履けるようになりました。
やりたいことを言葉にして、周りの人に伝えることで、現実に近づいていきます。
中途障害者になったから、僕も過去の自分と比べる時があるんですが、過去と比べても苦しくなるだけです。もし過去と比べるなら、倒れた直後の自分と今の自分を比べてみてください。きっと成長を実感できるはずです。
5.まとめ
いずみさんのインタビューからは、困難に直面してもポジティブに捉え、前に進む強さを感じました。
病気や障害は「定数」であり、変えられないことを嘆くのではなく、「変数」である自分の可能性を最大限に広げていくという考え方は、大きな気づきになるのではないでしょうか。
また、自分の経験を活かして同じ境遇の人々をつなげる活動は、社会全体のバリアフリー意識を高めることにもつながっていきます。
「やりたいことを口に出す」「過去ではなく倒れた直後と比べる」といったいずみさんの言葉は、障害の有無に関わらず、人生の岐路に立つすべての人の背中を押してくれるメッセージです。
Instagram:https://www.instagram.com/zoome1126/?hl=ja
編集者さんのInstagram:https://www.instagram.com/yasuyo_tomita/