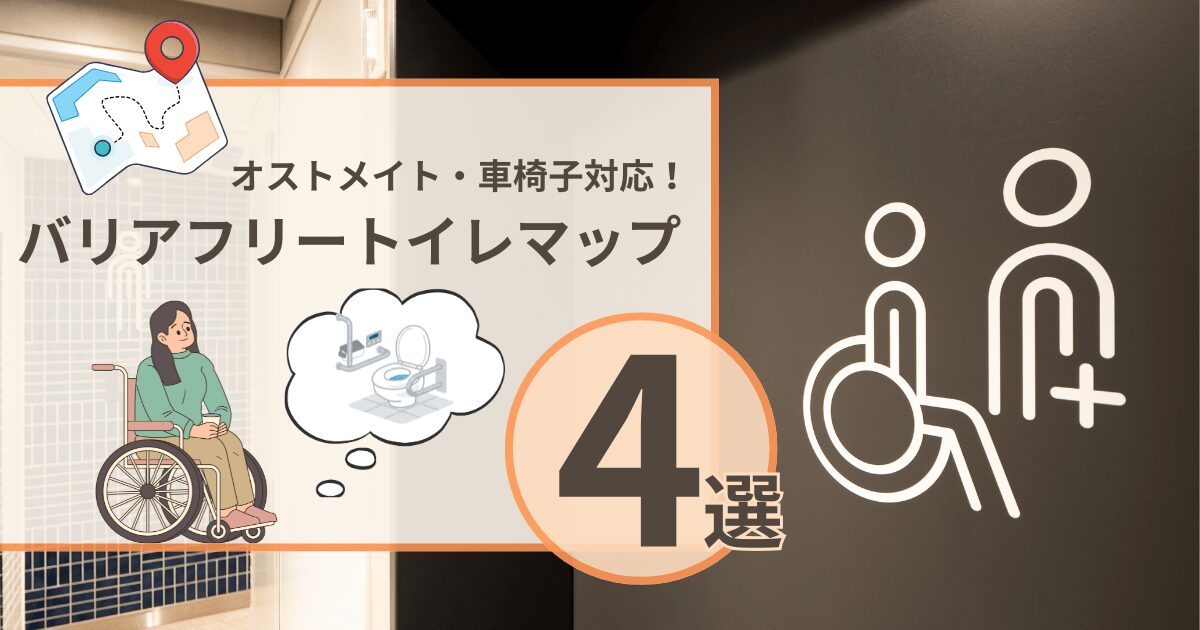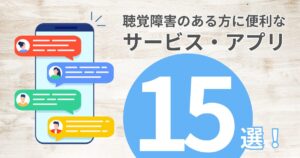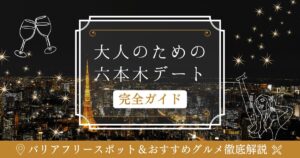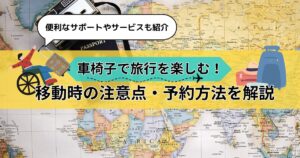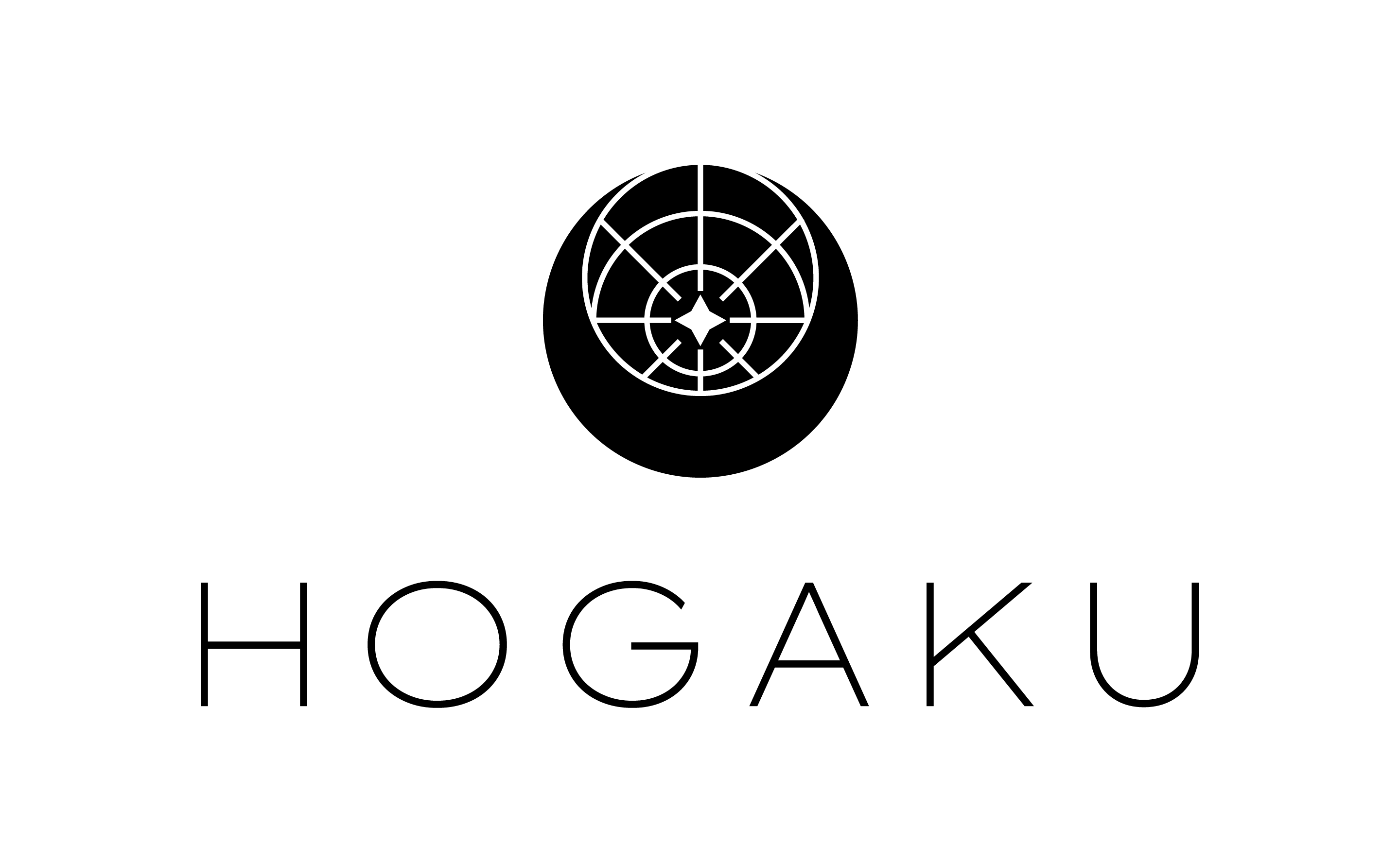外出先で「車椅子で入れるトイレが見つからない」「オストメイト対応のトイレが分からず不安」と感じたことはありませんか。急な便意や長時間の外出時に利用できる場所が分からないのは、大きなストレスになります。
実際、車椅子利用者やオストメイトの方にとって、使えるトイレの有無は外出の自由度を左右する深刻な課題です。バリアフリートイレは整備が進んでいるものの、「どこにあるのか分からない」「混雑していて利用できない」といった声は今も少なくありません。
そこで役立つのが、全国や地域ごとに提供されているバリアフリートイレマップです。車椅子でも利用しやすいトイレや、オストメイト対応のトイレを条件別に検索できるため、外出前や移動中に安心して利用場所をチェックできます。
この記事では、代表的な全国版のマップから大阪・東京・銀座など地域限定の情報源まで徹底解説します。トイレ探しの不安を解消し、外出をもっと快適で自由なものに変えていきましょう。
1.障害者にトイレマップが必要な理由

1-1. バリアフリートイレが「足りない」「わからない」現実
外出時に安心して使えるバリアフリートイレがどこにあるのか……これは、車椅子利用者やオストメイトにとって行動範囲を大きく左右する切実なテーマです。
現状として、バリアフリートイレの数は増えているものの、障害者のニーズに十分に応えられていません。オストメイト対応設備が整った施設でも「場所が分からない」「営業時間外で閉まっていた」というケースが多く報告されています。
そのため、多くの方が出発前にトイレの場所を検索し、利用可能な時間を確認したうえで外出しているのです。
さらに、国土交通省の調査では、車椅子利用者の9割以上が「バリアフリートイレで待たされた経験がある」と回答しました。本来必要としない人も利用することで混雑が発生し、本当に必要とする人が使えない状況が起きています。
バリアフリートイレの使用について、SNSではさまざまな事例が浮き彫りになっています。
スーパーで身障のトイレを使おうとたら
— 妹尾 将充 (@seno121210) June 16, 2025
閉まってて、中から電話の声もするし
15分くらい経ってやっと出てきて
「ここじゃなくてもできますよね?」って注意したら、「どうぞ使ってください」って言われて、ここじゃなくてもできますよね?
と言っても、「どなたでもお使いください」…
バリアフリートイレは、"誰でも使える"ものだと思いますか?
— いくこ|レーサー復活までの道のり (@IkukoE195) August 30, 2025
「だれでもトイレ」と書かれていることも多いこの場所。
混雑時に使ったことがある方もいるかもしれません。
私が車椅子を使っていたときのこと。
5分以上待っても物音ひとつせず、困り果ててノックしたら、⤵︎
こうした課題を受け、国は2021年に「多目的トイレ」の呼称を使わない方向性を固め、「バリアフリートイレ」へ呼び方統一しました。利用対象を明確にすることで混雑を抑え、誰もが必要なときに設備を使える環境整備を進めているのです。
1-2.車椅子利用者・オストメイトユーザーが抱えるトイレの不安
バリアフリートイレの有無は、車椅子利用者やオストメイトユーザーにとって生活の自由度と安心感を決める要因といえます。
人工肛門や人工膀胱を持つオストメイトユーザーは、ストーマ装具にたまった排泄物を1日に7〜8回処理しなければなりません。
しかし外見から障害が分かりにくいため、長時間バリアフリートイレを利用すると「健康そうなのになぜ?」という視線を浴び、不安やストレスにもつながります。外出時のトイレ問題が壁となり、出かけることを諦める人も少なくありませんでした。
尿意や便意を我慢できない障害を持つ方や、狭い個室で不安を感じやすい発達障害のこどもなど、バリアフリートイレを必要とする背景は多岐にわたります。こうした不安が社会参加を阻む現実として、今も続いています。
1-3.トイレマップで得られる安心感とメリット
そこでトイレマップを活用すれば、車椅子利用者やオストメイトユーザーが外出する際の不安を大幅に軽減できます。
最大のメリットは、出発前に目的地周辺のバリアフリートイレを把握できる点です。事前にバリアフリートイレの場所を知っていれば、安心して外出の計画を立てられ、万が一のトラブル時にも落ち着いて対処できます。
後ほど詳しく紹介しますが、「だれでも東京」のようなサイトでは、一人ひとりの特性に合った条件でトイレを検索できます。また、スマートフォン用のアプリであれば、現在地からもっとも近いトイレを手軽に探せるため、緊急時にも心強い存在です。
マップには温水の有無や商業施設の何階にあるかといった詳細情報も掲載されており、迷うことなく目的地に辿り着けます。さらに、ユーザー登録を通じて自身が見つけたトイレ情報を投稿し、全国の仲間と情報を共有する仕組みも整っています。
バリアフリートイレマップがあれば、車椅子利用者やオストメイトユーザーが外出の不安を軽減し、社会参加を広げるきっかけになるのではないでしょうか。
また、2025年バリアフリーに関する法律が一部改正されました。トイレに関連する項目も該当しています。ぜひ下記の記事も参考にしてください。
参照:バリアフリー新法とは?2025年の改正内容もわかりやすく解説!
2.おすすめのバリアフリートイレマップ4選

全国で利用できる代表的なトイレマップは複数ありますが、それぞれ特徴や強みが異なります。目的や状況に応じて使い分けることで、外出時の安心度を高められるでしょう。ここでは4つの主要サイトを紹介します。車椅子利用者やオストメイトユーザーにとって必須の情報源です。
2-1.みんなで作ろう多目的トイレマップ
「みんなで作ろう多目的トイレマップ」は、圧倒的な掲載件数と簡単な検索方法が魅力です。
2025年9月1日時点で68,719件の情報が集まっており、全国を広くカバーしています。GPS検索に加え、都道府県・施設名・郵便番号など多彩な条件で探せるのも特徴です。
各トイレ情報には、写真、広さ、ドアの形状、手すりの有無、オストメイト設備の有無などが記載されています。さらに、5段階の星評価によって利用者の体験が反映されているため、実際の使いやすさを事前に把握可能です。
会員登録すれば情報投稿に参加でき、誰でもサービスの充実に貢献できる点も評価されています。
コメント欄は下記のようになっています。
参照:利用者の皆さんからのコメント|みんなで作ろう!多目的トイレマップ
参照:みんなで作ろう!多目的トイレマップ
2-2.オストメイトJP
「オストメイトJP」は、オストメイト対応トイレに特化した全国規模の情報サイトです。
最大の特徴は、設備情報の細かさにあります。検索は都道府県や駅名、施設名から可能で、温水機能の有無や「汚物流しシャワー型」「パウチしびん洗浄水栓型」といった仕様の違いまでチェックできます。利用者にとって切実な条件を事前に把握できるのは大きな安心材料です。
2007年の開設以来、ユーザー投稿により情報が積み上げられてきました。現在では、iPhone・iPad対応アプリやLINE検索にも対応しており、外出中でも近くのオストメイト対応トイレをすぐに探せます。長年支持されている理由は、利便性と情報の信頼性にあるのです。
参照:オストメイトJP
2-3.YORISOU
「YORISOU」は、車椅子利用者や子育て世帯の声を反映して開発されたトイレマップです。実際の利用者の視点で設計されているため、使いやすさが際立ちます。
検索は目的地や駅名、現在地から可能です。さらに、駅からの所要時間やトイレの寸法といった移動に直結する情報まで掲載されており、バリアフリー経路を重視する人に適しています。
チェック項目は多岐にわたり、オストメイト設備、大型ベッド、ベビーチェア、車椅子の回転可否、手すりの種類などを確認可能です。会員登録すれば、一度検索したトイレ情報を保存できるため、日常的に同じ場所を利用する人には便利な機能といえるでしょう。
参照:車イス・ベビーカーで行けるトイレ情報サイト YORISOU
2-4.Check a Toilet(チェックアトイレ)
「Check a Toilet」は、NPO法人Checkが運営するユニバーサルデザイン対応のトイレマップです。登録件数は72,804件と国内最大級の規模を誇ります。
大きな特徴は、自治体や事業者だけでなく、個人やNPOからの口コミ情報も集約されている点です。Googleマップで「バリアフリートイレ」が検索できるのも、この団体が情報提供した成果です。
検索条件は車椅子対応、ベビーシート、駐車施設の有無、授乳室の有無などさまざまで、利用シーンに合わせて絞り込みができます。スマートフォンアプリは2024年に終了しましたが、現在はパソコン・スマホ向けサイトに統合されており、従来のアカウントでそのまま利用可能です。
口コミをベースにしたリアルな情報は、外出時の判断材料として役立ちます。
3.自治体や地域限定のトイレマップも紹介

3-1.大阪府バリアフリートイレマップ
全国版のマップに加え、自治体や地域が運営する公式サイトも外出時の強い味方です。自治体提供の情報は正確性が高く、設備の細部までチェックできるため、事前準備に役立ちます。
大阪府が公式に提供している「大阪バリアフリートイレマップ」は、外出時に頼れる情報源です。高齢者や障害者、子育て世帯など、幅広い人が安心して使えるよう設計されています。
大阪バリアフリートイレマップは、パソコンやスマートフォンからアクセスでき、位置情報をオンにすれば現在地周辺のトイレをすぐに表示してくれます。外出先で急に探す必要がある場面でも役立つでしょう。
アイコン表示によって、車椅子対応、オストメイト設備、介助ベッド、ベビーチェアなどの有無を直感的に把握できるのも便利です。さらに、府内の公共施設だけでなく、主要な商業施設やコンビニ、Osaka Metroの駅情報まで網羅しています。
ただし、改修工事や営業時間変更で最新の状況と異なる可能性もあります。利用前には公式サイトで再確認しておくと安心です。また、駅構内のトイレは入場券が必要になるケースがある点も注意しておきましょう。
3-2.大阪メトロ
大阪市内で地下鉄を利用するなら、Osaka Metroの公式ページが役立ちます。全駅にバリアフリートイレが設置されており、車椅子利用者やオストメイトの方でも安心です。
サイト上では、各駅の設備仕様を一覧でチェック可能です。
例えば、オストメイト対応トイレが「汚物流し一体型」なのか「パウチ・しびん洗浄水栓型」なのか、駅ごとに違いが明記されています。介助用ベッドやオムツ交換台についても同様に詳細が記載されているため、必要な条件を事前にチェックして移動計画を立てられるでしょう。
参照:多機能トイレ(バリアフリートイレ)設置状況の詳細|大阪メトロ
3-3.だれでも東京
東京都が運営する「だれでも東京」は、バリアフリー施設情報を集約した公式サイトです。
検索機能では「車椅子使用者対応トイレ」を条件に絞り、設備内容を詳しくチェックできます。
加えて、外出時の注意点や介助の方法を解説する特集記事もあり、初めて外出する方や家族にとって実用的に使えます。
日本語以外に英語・中国語・韓国語に対応しているのもうれしいサービスです。文字サイズや背景色の調整機能も備わっており、アクセシビリティを重視した設計になっています。
3-4.銀座公式バリアフリートイレマップ
「GINZA OFFICIAL」が提供するマップは、銀座エリア限定の便利な情報源です。観光やショッピングの際に安心して過ごせるよう、具体的な施設情報が整理されています。
特徴的なのは、トイレの見取り図や内部の様子を動画で確認できる点です。初めて訪れる施設でも設備の状況を把握しやすくなります。
松屋銀座、GINZA SIX、ユニクロギンザなど主要商業施設のトイレがリスト化されており、買い物や観光の計画に組み込みやすいのも利点です。
4.もしトイレが見つからない・使えない時の代替策

マップで念入りに調べて到着したにもかかわらず、「清掃中」「故障」「長時間利用されている」などの理由で、目的のトイレが使えない事態がおこりかねません。パニックにならず冷静に対応するため、具体的な代替策を知っておきましょう。外出時の安心につながります。
目的のトイレが使えなかった場合、バリアフリートイレが設置されやすい場所を順番に行ってみましょう。
- 公共施設(役所、図書館、公民館など)
開館時間内であれば設置率が高く、設備も比較的整っています。 - 大規模な商業施設(デパート、ショッピングモール)
複数のフロアにトイレがあるため、1か所が使えなくても別の階で探せます。まずはインフォメーションカウンターで確認すると効率的です。 - 主要な駅(ターミナル駅)
改札の内外にバリアフリートイレがあり、駅員に聞けば案内してもらえるでしょう。 - 比較的新しいコンビニエンスストア
車椅子対応トイレを併設する店舗が増えています。地図アプリで「コンビニ 車椅子 トイレ」と検索し、候補を絞るのも有効です。
自力で探すのが難しい状況では、人に助けを求めるのも有効な手段です。
- 施設のスタッフに尋ねる
商業施設ではインフォメーションや警備員、駅では駅員に「バリアフリートイレが使えず困っています」と具体的に伝えましょう。従業員用の設備を案内してもらえる場合もあります。 - ヘルプマークやヘルプカードを提示する
外見から分かりにくい障害の場合や口頭で説明しづらい場面では、ヘルプマークやヘルプカードを提示することで状況を理解してもらいやすくなります。
複数の選択肢を持ち、事前に備えておけば、突然のトラブルに直面しても落ち着いて対処できるでしょう。
5.まとめ
外出時に安心して行動できるかどうかは、バリアフリートイレの有無や情報量に大きく左右されます。特に車椅子利用者やオストメイトユーザーにとって、トイレ問題は生活の自由度を決める要素といえるでしょう。
全国規模で使える代表的なトイレマップとしては「みんなで作ろう多目的トイレマップ」「オストメイトJP」「YORISOU」「Check a Toilet」があり、それぞれ検索軸や設備情報の詳細さに特徴があります。さらに、大阪府や東京都の公式サイト、銀座エリア限定のマップといった地域特化型の情報源を活用すれば、現地で迷うリスクを減らせます。
また、万一トイレが見つからない・使えない場合でも、公共施設や商業施設、駅、コンビニといった代替候補をあらかじめ把握しておけば安心です。ヘルプマークの活用や緊急用グッズの準備も不測の事態を乗り越える助けになります。
バリアフリートイレマップや代替策を日常的に取り入れることで、障害のある方やご家族が外出時の不安を減らし、より快適に社会生活を送れるようになります。外出前の準備を習慣にして、安心して行動範囲を広げていきましょう。