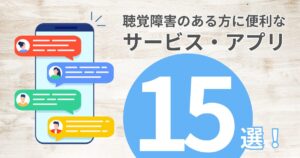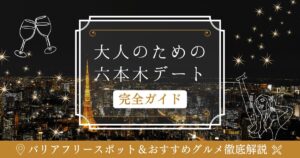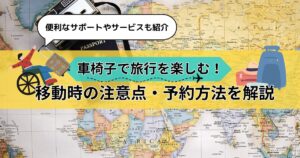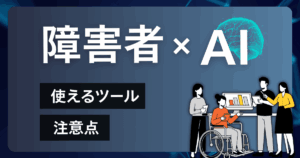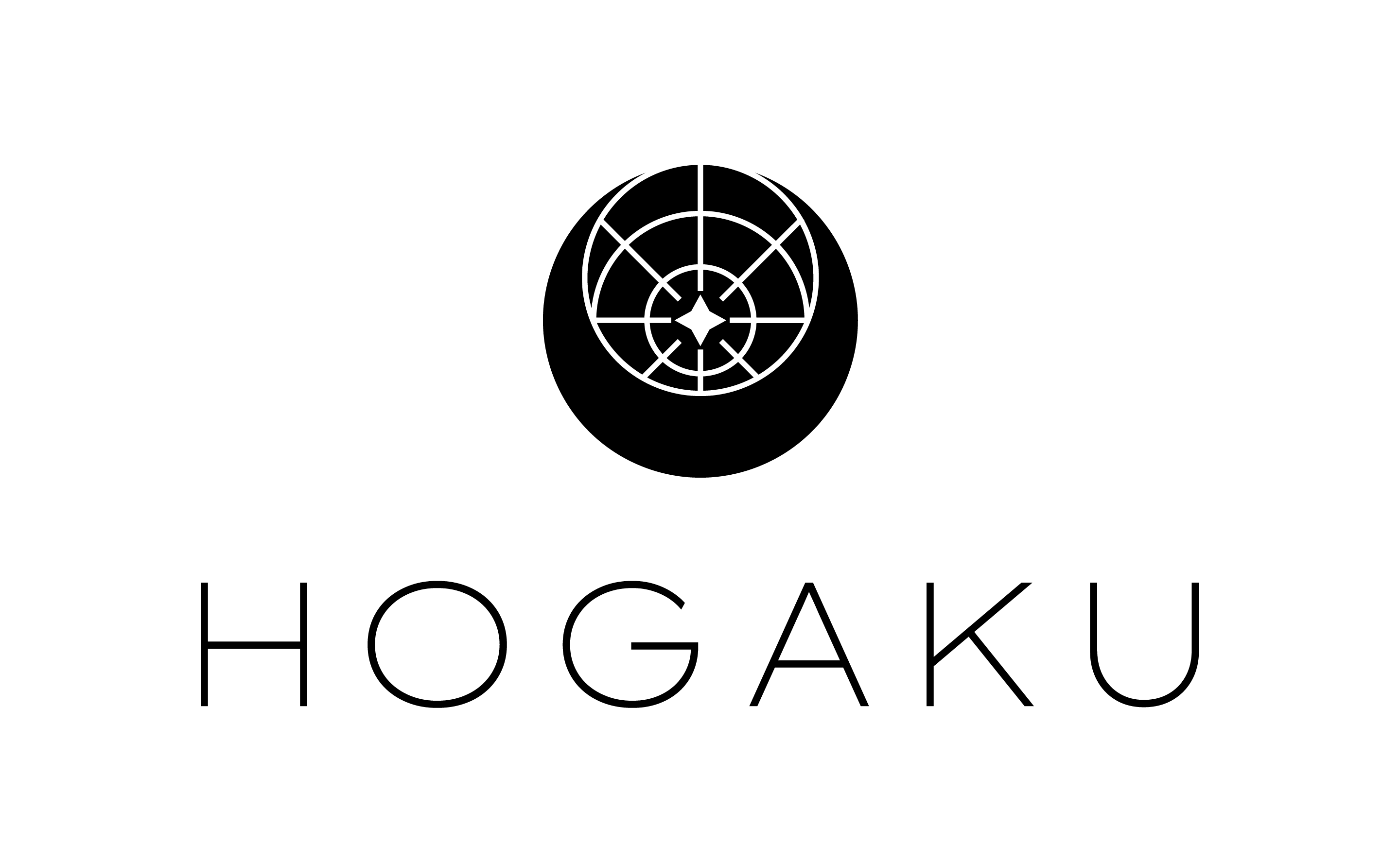在宅でさえ体調面で気を使うことの多い医療的ケア児。そんなこどもを連れての外出となると、身構えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
筆者にも医療的ケア児のこどもがいるのですが、小さい頃は特に、外出には本当に苦労しました。
でも、通院などで出かけなければいけない時もありますし、「こどももずっと家にいると退屈かな」という心配もあり、なんとか気持ちを奮い立たせて外出しておりました。
そんな思いで外出しているのは、私だけではないようです。厚生労働省の調査では「医療的ケア児との外出が困難を極める」という質問に対し、「当てはまる」と答えた割合は65.3%にも上ります。
参照:『医療的ケア児者とその家族の生活実態調査 報告書』P54|厚生労働省
それもそのはず、お子様の医療的ケアや障害の種類によっては、たくさんの機器を積んで外出しなくてはならず、一つひとつが数キロあるため荷物の総量は十キロを超えることも珍しくありません。バギーに積み込むのも一仕事です。
加えて、こどもの状態を見ながら必要に応じて吸引などの処置を行うことも考えると、でかけることが億劫になってしまうこともありますよね。
さらには、時間的制約があり外出時間が限られる場合もあります。
たとえば、常に酸素投与が必要な子の場合、酸素ボンベを持って外出しますが、そのボンベはかなりの重量。持っていける数には限りがあるため、酸素の容量がなくなる前に帰宅するようなスケジュールを組まなければいけません。
このように、大変なことが多い医療的ケア児とのおでかけ。
そこで今回は、医療的ケア児とのおでかけが少しでも楽になるような準備や、サポートサービスなどをご紹介したいと思います。
「おでかけしたい!でもあれこれ考えると億劫になってしまう…」という方の参考になれば嬉しいです。
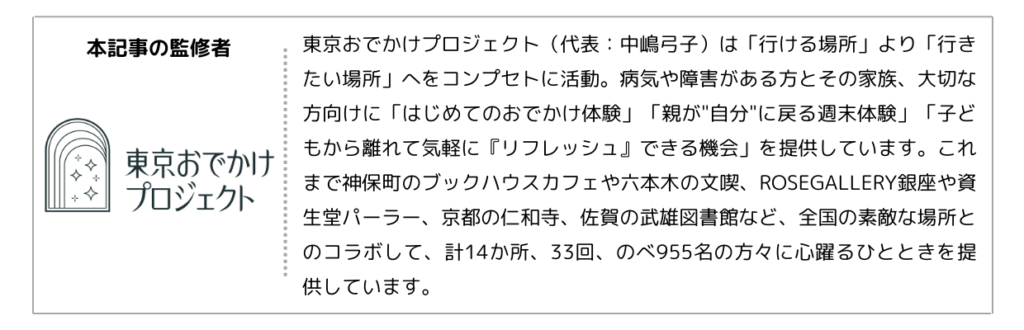
参照:東京おでかけプロジェクト
目次
1.医療的ケア児・障害児のおでかけには、こんな困りごとがある!

姫路大学が行った保護者へのアンケート調査の結果、重症心身障害児・者の外出に困難を覚える理由として、主に「道路や通路の問題」「駐車場の問題」「トイレの問題」が挙げられたそうです。
参照:重症心身障害児・者の外出行動の特徴と外出を困難にする要因についての検討|姫路大学大学院看護学研究科論究(2018年)
道路や通路については、段差があることや、道路が整備されておらずバギーでガタガタしてしまう、通路が狭くバギーで通るのが困難という現状があるようです。
駐車場については、車椅子用駐車場の数が足りない、屋根がなく車椅子やバギーに移乗している間に濡れてしまうなど設備上の問題のほか、一般の人や老齢の方が停めてしまっていて使えないなどモラルの問題もみられました。
トイレについては、行きたい場所に多目的トイレがない、また乳児用のおむつ替えスペースはあっても、それ以上の年齢のこどものおむつ替えスペースがないという声が多く、多目的トイレとおむつ替え用ベッドの設置が希望されていました。
なお、後に紹介する「東京おでかけプロジェクト」では、多目的トイレがない場合、事前に多目的室として使える部屋やソファーがないか施設側に確認したり、目隠しが足りない時は仕切りボードなどを手配して備えたりしています。
このように、自分たちではどうにもならない問題も多いなか、医療的ケア児・障害児のいる家族たちはどんな工夫をして外出しているのでしょうか。
2.医療的ケア児・障害児のいる家族が付き添い一人でおでかけする場合の工夫
2-1.医療的ケア児・障害児のいる家族はどんなことに気をつけているのか?

外出に慣れた先輩たちは、おでかけ先で遭遇するバリアについてもよく知っています。その対策も含めた準備についても、事前に知っておくことができると安心できますよね。
現代では、YouTubeやSNSなどで「医療的ケア児のおでかけ」について発信している企業や個人の方が多くいますので、それを見てシミュレーションをしてみるのも一つの手です。
たとえば、特定非営利活動法人アンリーシュのYouTubeでは、人工呼吸器、吸引吸入など、複数の医療的ケアが必要なお子さんの外出準備の動画を配信しています。
他にも、胃ろうの子が外出する時の準備物や、医療的ケアがある子が旅行をする時の準備についてなど、特定非営利活動法人アンリーシュのYouTubeチャンネルには、様々なおでかけについての動画があります。
準備物や準備のコツなど、先輩たちの知見を得られるのはとても心強いですね。
特定非営利活動法人アンリーシュについて、もっと詳しく知りたい方は下記からどうぞ。
参照:障害児を育てる時に抱える課題の解決に取り組む、特定非営利活動法人アンリーシュとは?
2-2.どんな設備がある場所だと安心できるのか?
外出に必要な準備がある程度分かったら、今度はでかける場所をどこにするのかを考えるのも大切なポイントです。
最低限必要な設備が整っている場所かどうかを前もって確認しておくと、安心しておでかけができそうですね。
では、どんな設備があれば安心なのでしょうか。
先に紹介したアンケートにもあったように、多目的トイレの有無は外出先を選定するにあたって非常に大切な要素です。
多目的トイレは、こどものおむつ替え時はもちろん、親がトイレに行きたくなった時にも使用します。
こどもをバギーに乗せて移動する都合上、普通のトイレではとても狭くて連れて入ることができません。かといって、バギーごと外でこどもを待機させておくわけにもいきません。
そういう意味でも、こどものバギーと一緒に入れる広さの多目的トイレがあることは、外出先を考える際の必須要素といえるでしょう。
外出先を決める時には、多目的トイレの有無、中にこどものおむつ替えができるサイズのベッドがあるかの両方を確認しておくと安心です。
3.おでかけの時に使える医療的ケア児・障害児のいる家族へのサポートサービス

このように、しっかり事前準備をすることで、医療的ケア児・障害児のいる家族が一人でこどもを連れておでかけをするということを日常的に行えている家庭も多くあります。
では、どうしても家族だけでのおでかけが難しい場合、サポートしてもらえるサービスはあるのでしょうか。
まずは、公的福祉サービスとして、ヘルパーさんによる「移動支援」というものがあります。自治体に申請して許可が出れば、移動時にお手伝いをしてもらえます。
ただし、誰でも受けられる支援ではなく「未就学児は障害の有無にかかわらず親が監護するもの」という考え方で移動支援の対象外とする自治体もあり、地域差があるようです。また、外出目的によっては使えないこともあり注意が必要です。
つづいて、こちらも地域が限定されますが、民間で提供している有料の移動支援サービスもあります。
たとえば、ケアプロ株式会社が東京都を中心にサービスを提供している「ドコケア」。“病や障害があっても安心して外出できる世の中を”をモットーに、公的支援制度ではまかなえないような外出支援のニーズに応えています。
看護師同行で医療的ケア児とのおでかけをした動画もありましたので、利用を検討する際の参考になりそうです。
また、特定非営利活動法人あえりあでは、札幌市内で「さぽんて」というサービスを展開しています。
障害児者やその家族からの要望に、医療福祉の有資格者が有償ボランティアとして応えてくれるマッチングサービスです。その一環として外出支援も行っているようです。
一人ではなかなか外出が難しいという方は、こういった民間のサービスを検討してもいいかもしれませんね。
4.病気や障害、医療的ケア児ご家族のおでかけを応援!東京おでかけプロジェクトとは?

病気や障害、医療的ケア児ご家族のおでかけを応援している組織として、「東京おでかけプロジェクト」があります。
東京おでかけプロジェクトは、病気や障害、医療的ケアがあるこどもとそのご家族が、「行ける場所ではなく行きたい場所へ」行ける社会の実現を目指して、全国の心躍る場所でおでかけイベントを開催しています。
家族向けには家族の「はじめて」のおでかけを応援しようと神保町にあるこどもの本専門店ブックハウスカフェを貸し切り、プロの声優を呼んでの絵本のおはなし会やカレーパン付き交流会を開催。
母親向けには「〇〇ちゃんママやお母さんではない”わたし”に戻る時間を楽しんでもらいたい」という想いから、ROSEGALLERY銀座と資生堂パーラーを貸し切り、プロによるヘアメイクやアフタヌーンティーを楽しむイベントを行ったり、表参道にあるMiMCとニールズヤードの協力を得てメイクレッスンを開催。
父親向けには六本木にある有料の書店の「文喫」を舞台に、本や言葉を通じて自分と向き合う時間を提供されました。
ほかにも、京都にある世界遺産の仁和寺や佐賀の武雄図書館で著名なアーティストを招いてのインクルーシブイベントなども開催されています。
月1回以上のペースでイベントが開催されており、バリエーションが豊富です。
これまで参加した家族はのべ900人以上、ファンクラブやSNSのフォロワー数は1,500人を超えていて、多くの方に賛同されているプロジェクトとなっており、今後も魅力的なイベントを開催してくれることでしょう。
参照:東京おでかけプロジェクト
東京おでかけプロジェクトの活動は、ホームページをはじめInstagramやYouTubeからご覧いただけます。
参照:東京おでかけプロジェクト | 活動レポート
参照:東京おでかけプロジェクト | Instagram
参照:東京おでかけプロジェクト | YouTube
5.まとめ
ここまで、医療的ケア児とのおでかけのハードルが少しでも下がるよう、準備やサービスの紹介をしてきました。
あとは、おでかけの回数を重ねていけば、でかけることそのものには慣れていくでしょう。
しかし、超えなくてはいけないのは、そういった物理的なハードルだけではありません。なかには、精神的なハードルを感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
医療的ケア児は、見た目にも特徴があります。管をたくさんつけていたり、大きな医療機器を積んでいたりするので、「周りの目が気になる」という声は、SNSでも多く見かけます。
特に小さな子は、素直がゆえに、驚きや好奇の視線を遠慮なく向けてくることや、ひやかすような言葉をかけてくることもあります。それを家族が「見ちゃいけない」というような言動で制することだってあります。
これは今すぐどうにかなるものではありませんが、医療的ケアや障害があり、重症心身障害のあるこどもも世の中に普通に存在するということは、たくさんの人に知ってもらいたいですね。
「存在が当たり前」「困っていたら自然に手を差し伸べる」という社会になって、障害があってももっとおでかけしたいという気持ちになる人が増えることを願っています。