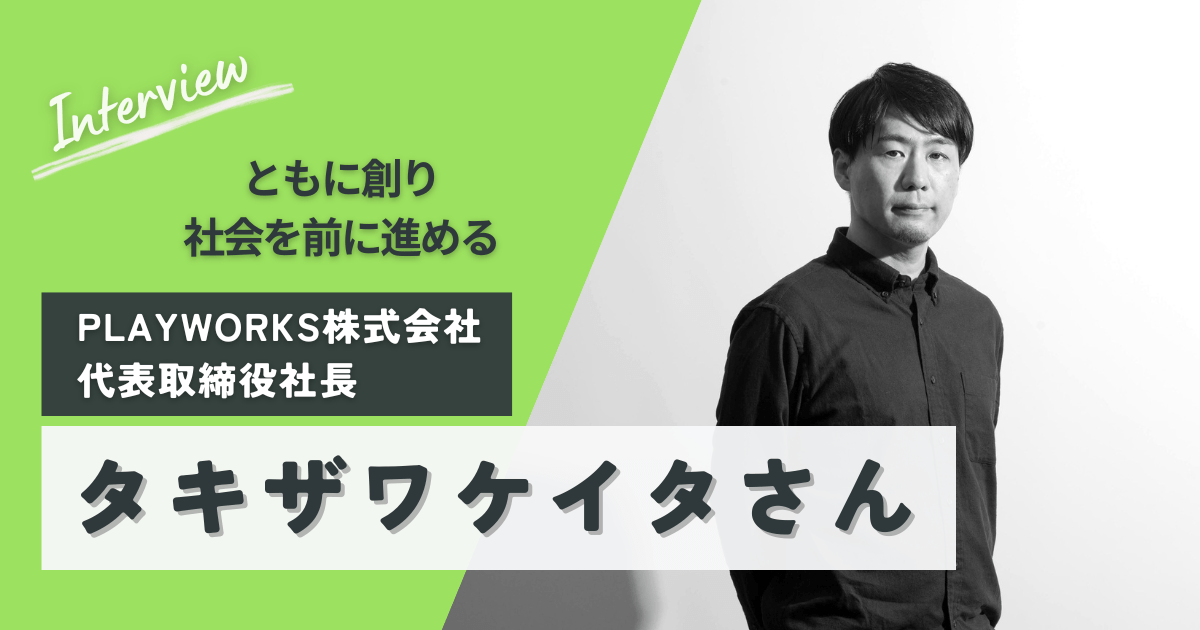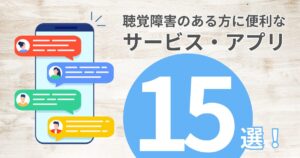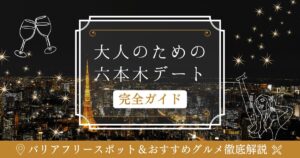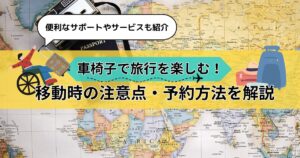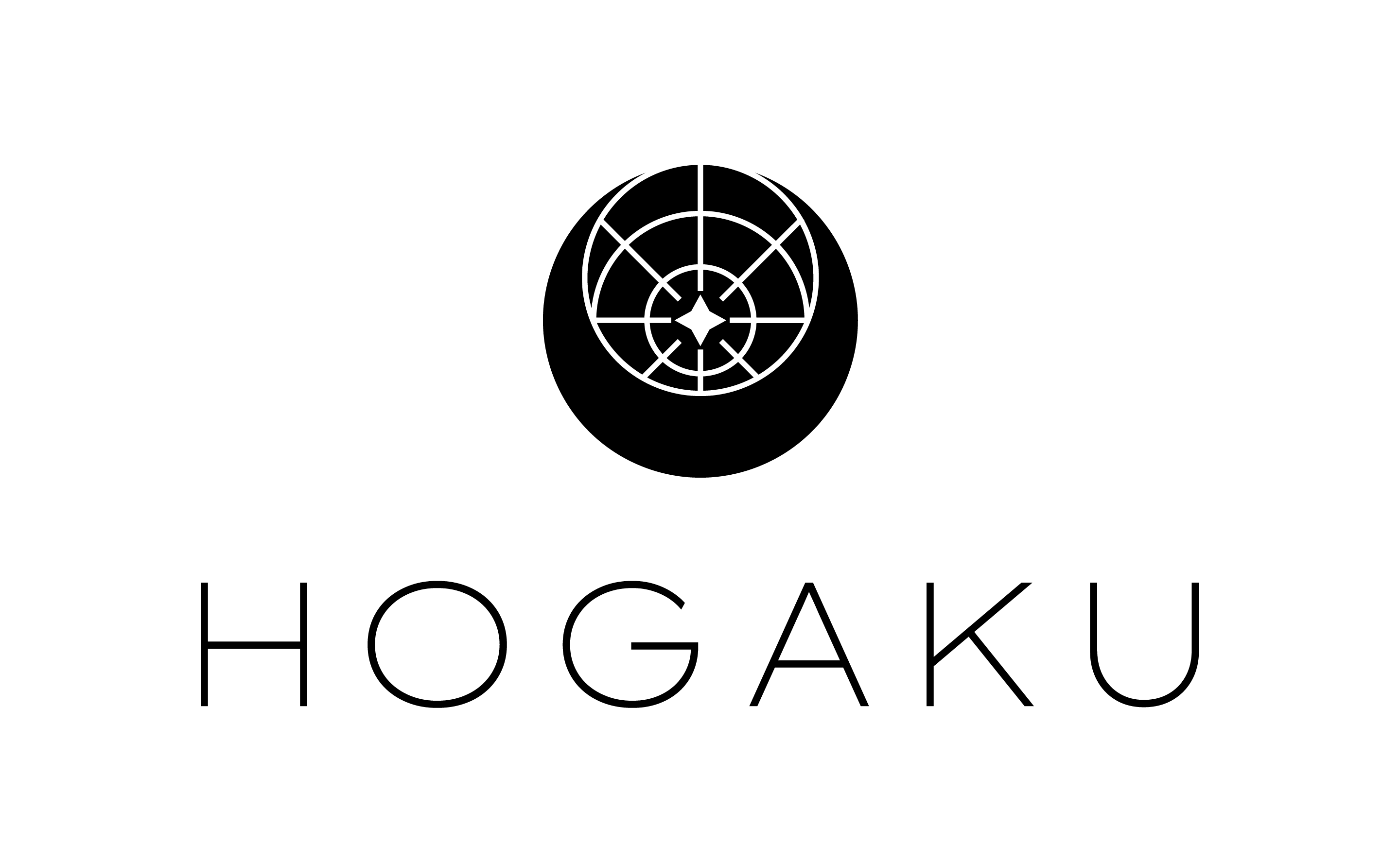インクルーシブデザインとは、障害者など多様なリードユーザーと共創するデザイン手法です。
インクルーシブデザインについては下記の記事をご覧ください。
参照:インクルーシブデザインとは?ユニバーサルデザインとの違いを6つの事例を用いて解説!
インクルーシブデザインを専門に活動するPLAYWORKS株式会社代表取締役のタキザワケイタさんに挑戦の軌跡を伺いました。
目次
1. タキザワケイタさんってどんな人?

【インタビュアー(ライター):赤石/インタビュイー:タキザワケイタさん】
赤石: タキザワさんはどのような経歴をお持ちなのでしょうか?
タキザワさん: 建築・空間デザインの勉強から始まり、設計事務所や企画会社、広告代理店など様々な分野でデザインに携わってきました。
今はPLAYWORKSの代表として、インクルーシブデザインのコンサルティングを行っています。
ただ、子供の頃は目が悪くて手術したり眼科に通院もしていたので、特別な夢があったわけではないんです。
赤石: なぜデザインを学ぼうと思われたのですか?
タキザワさん: 高校生の時に進路を考えるタイミングで、単純にデザインがかっこよさそう、楽しそうだと思ったんです。
大学では建築系の空間デザイン専攻に進みました。建築だけではなく、幅広くデザイン全般を学ぶ環境でした。
大学3年生の時に、非常勤講師をしていた先生の設計事務所でバイトを始めて、そのまま卒業後も就職しました。
その後、企画会社や広告代理店に移りましたが、一貫して「新しいものを考えたり形にしたりする」ことが好きなんです。特に建築は規模が大きく、人への影響も大きいので最初に引かれました。
2. インクルーシブデザインへの道
2-1. インクルーシブデザインとの出会い
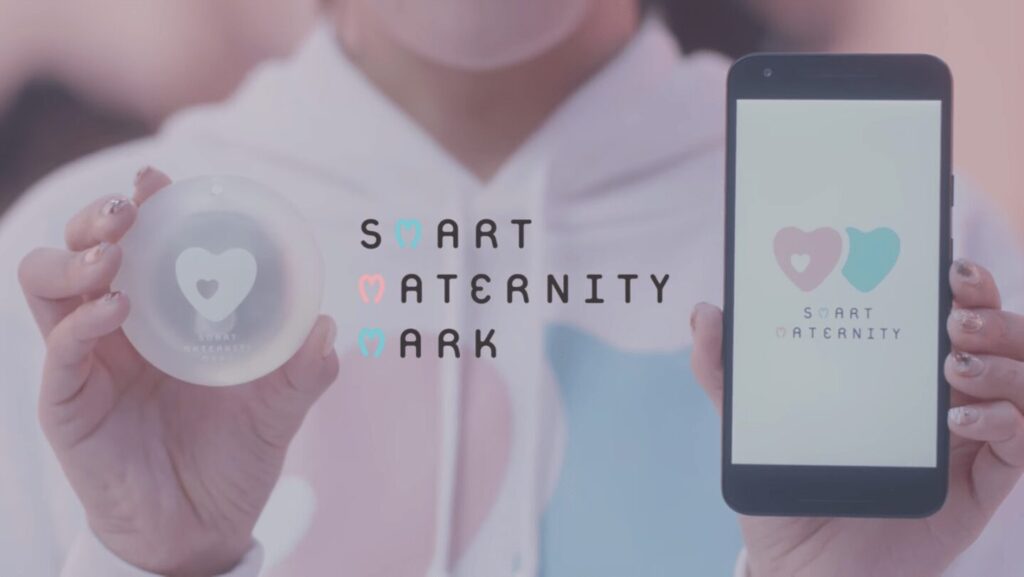
赤石: インクルーシブデザインに注目されたきっかけは?
タキザワさん: 広告代理店に8年ほど勤めていて、辞める2年前くらいに仲間と任意団体を作り、デザインコンペに出したんです。
会社とは関係なく、知り合い同士でデザインのアイデアを考えるコンペティションでした。
そこで生まれたのが「スマートマタニティマーク」です。
これは妊婦さんが電車で座りたい時に押すと近くにいるサポーターのスマホに通知が飛び、席譲りをマッチングするデバイスとアプリのアイデアでした。
発表したところ、「妊婦さんだけでなく障害のある方にも使いたい」という声をいただいたんです。
そこから様々な障害のある方にインタビューをして実証実験を行い、「アンドハンド」というサービスに発展させました。
いま思えば、この時すでにインクルーシブデザインを実践していたんです。
特に意識していたわけではなく、やっていたことがインクルーシブデザイン的なアプローチだったと気づいて、それがきっかけで会社を作りました。
2-2. 当事者と共に創る

赤石: 当事者を巻き込んでいくのは大変だったのでは?
タキザワさん: 最初はネットワークも少なかったですが、徐々に協力してくれる方が増えていきました。
今では定量調査のウェブアンケートを実施する際も、障害の種類に関わらず100人以上の方に協力していただけるようになりました。
大切にしているのは、プロセスを積極的に公開することです。
調査結果やワークショップの様子をすぐにホームページで公開したり映像にして共有したりすることで、応援してくれる当事者の方が参加を実感できるようにしています。
3. インクルーシブデザインの実践と挑戦
3-1. 印象的なプロジェクト「XRキャッチボール」
赤石: 特に印象的だったプロジェクトを教えてください。
タキザワさん: ソニーとの「XRキャッチボール」です。
これは会社設立から2年目の2021年に、視覚障害のあるリードユーザーとのワークショップから生まれました。
通常のワークショップでは「困りごと」を聞くことが多いのですが、このときは「いつか人生でチャレンジしてみたいこと」をテーマにしました。
そこで出会ったのが、視覚障害のある方の「息子と野球がしたい」という願いでした。
息子さんが野球好きで「お父さん、キャッチボールして」と言うけれど、視覚に障害があるためにできないという状況だったんです。
そこで開発したのが、スマホ型のグローブを振りかぶると音が移動するデバイスです。スマホの動きに合わせて音がピッピッピッと移動するので、目に見えなくてもキャッチボールの体験ができます。
タイミングよくグローブを握ることでキャッチができる仕組みですね。
このプロジェクトは銀座のソニーパークやソニーストア、CEATECなどのイベントで体験展示を行ってきました。
将来的には「魔球」も投げられるようになるかもしれませんね。
障害の有無に関わらず、キャッチボールがより楽しくなる可能性を感じています。
3-2. 社会実装への挑戦
赤石: 起業してみて気づいたことはありますか?
タキザワさん: 社会実装の難しさです。
社会課題や障害をテーマにすると、アイデア創出やプロトタイピング、実証実験までは比較的容易ですが、実際に事業化するとなると急にハードルが高いんです。
例えば「スマートマタニティマーク」は様々な実証実験で成果を出しましたが、企業が自社サービスとして採用するには至りませんでした。
そこで見つけたアプローチは、大手企業のDEIやCSR、SDGsの活動に関するコンサルティングという形でインクルーシブデザインを導入していくことです。
企業と共創することで社会実装し、PLAYWORKSのビジョンも実現できる仕組みを目指しています。
3-3. 社会を前に進めるデザイン
赤石: タキザワさんのビジョンや大切にしている考え方は?
タキザワさん: PLAYWORKSのスローガンは「ともに創り、社会を前に進めよう」です。
マイナスをゼロに「改善」するだけでなく、マイナスからプラスの価値を生み出す「イノベーション創出」にチャレンジしています。
その一つが、視覚障害者のための仮設の点字ブロック「ココテープ」です。
幅48ミリの黄色い塩化ビニールのテープで、両サイドが山型に6mm立ち上がっており、足や白杖で感じ取れる製品で、イベント会場やホテルの客室など一時的に必要な場所に貼って、後で剥がして再利用できます。

100年後も持続的に使われ続けている、社会インフラとして生活に馴染んでいる製品を作りたいと考えています。
プロダクトやサービスを通じて、社会を少しでも前に進めていきたいですね。
4. 挑戦に躊躇している人へのメッセージ
赤石:新しい挑戦に躊躇している方へのメッセージをお願いします。
タキザワさん: まずは「やってみたい」という気持ちを大切にしてほしいと思います。
私自身も最初は確かな道筋が見えていたわけではありませんでした。でも、当事者の方々と対話し、一緒に考えていく中で、新しい可能性が見えてきたんです。
大切なのは、一人で抱え込まないこと。様々な視点を持った人たちと協力することで、思いもよらないアイデアや解決策が生まれるはずです。
インクルーシブデザインの本質は、多様な人々が共に創ることです。
すべてのプロジェクトが成功するわけではありませんが、その経験が次の挑戦につながります。私たちも試行錯誤の連続ですが、一つひとつの経験が積み重なって、今のPLAYWORKSがあります。
「社会をよくしたい」「誰かの役に立ちたい」という思いがあれば、小さな一歩から始めてみてください。きっとその先には、想像以上の可能性が広がっているはずです。
5.まとめ
取材を通じて印象的だったのは、タキザワさんの「当たり前を少し変えることで生まれる可能性」への強い信念です。
障害や制約を単なる「問題」として捉えるのではなく、新たな価値を創造するきっかけとして活かす姿勢には、デザインの本質的な力を感じました。
インクルーシブデザインとは、ただバリアを取り除くことではなく、多様な人々と共に考え、すべての人にとって新しい価値を生み出すプロセスなのだと理解できました。
タキザワさんとPLAYWORKSの挑戦は、私たちの「当たり前」を見つめ直すきっかけを与えてくれています。
「ともに創り、社会を前に進める」—このシンプルなスローガンには、より豊かで包括的な未来へのビジョンが込められているのではないでしょうか。
公式HP:PLAYWORKS