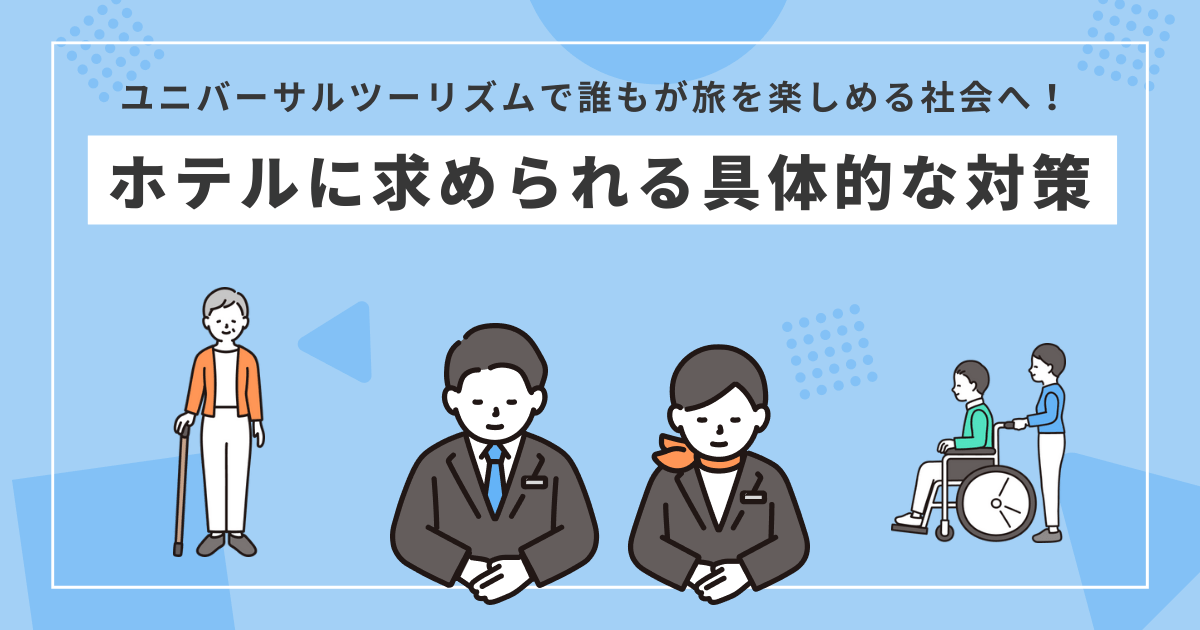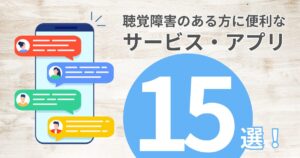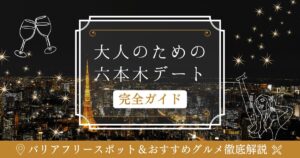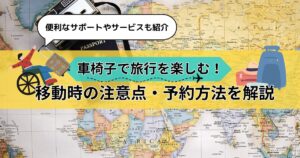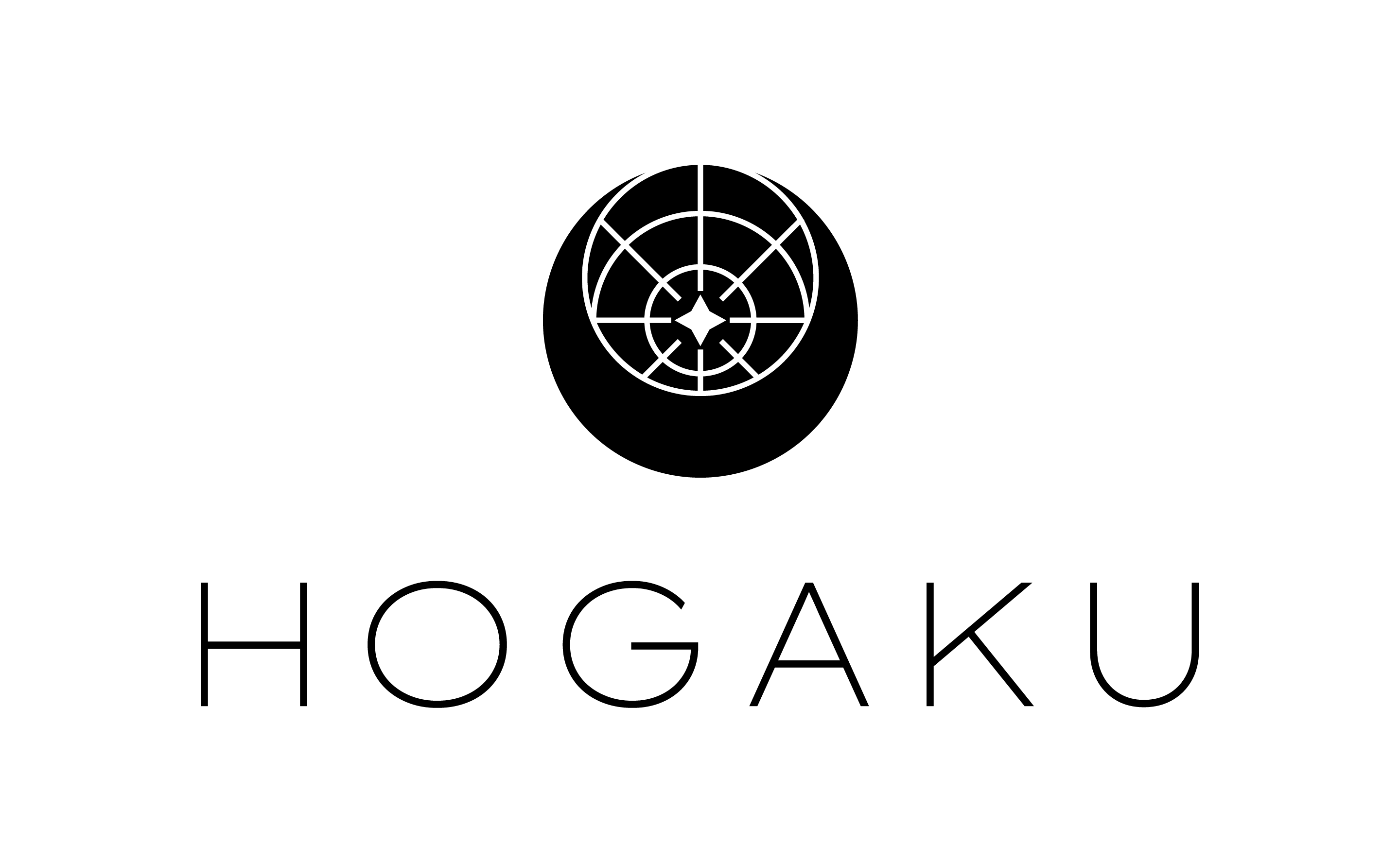旅行は多くの人にとってかけがえのない体験ですが、身体に障害のある方や高齢者の方々にとっては、バリアフリー対応が不十分な場所が多く、旅行を諦めざるを得ない現状があります。
しかし、ユニバーサルツーリズムを推進することで、誰もが気兼ねなく旅行を楽しめる社会の実現が可能です。本記事では、ユニバーサルツーリズムの重要性と、ホテル事業者が取り組むべき具体的な対策について詳しく解説します。
目次
1.ユニバーサルツーリズムの重要性が増す理由とは?

日本において、インバウンドの影響も含め、ユニバーサルツーリズムの推進は重要性を増しており、喫緊の課題となっています。さらにユニバーサルツーリズムへの取り組みが他社との差別化・お客様満足度向上にも繋がっていきます。
1-1.身体障害者人口の増加
身体障害者の数は増加傾向にあり、バリアフリーの需要は年々高まっています 。1970年には約140万人だった身体障害者の人数は、2016年には約428万人となっています 。このデータからも、バリアフリーの需要が高まっていることがわかります 。
参照:内閣府 障害者の状況
1-2.大きな市場規模
身体障害者が来店する際、9割のケースで1名以上の同行者がいるため、障害者1名の集客で2名の来店に繋がり、872万人へのアプローチが可能になります 。さらに、身体障害者のリピート率は健常者に比べ2.8倍と高く 、1人の身体障害者を集客することで、健常者に比べて約6倍の新規集客が見込めます。
また、身体障害もあるシニア層の市場は有望で、高齢者全体の市場規模は約1兆7,800億円に上り 、その市場効果は約5,200億円と試算されています 。
1-3.高まるユニバーサルツーリズム・バリアフリーへの関心
「バリアフリー」の検索回数が飛躍的に上昇しており、5年前には100位以下だったものが、現在では30位~40位に位置しています 。バリアフリー改修を行った施設では、1年後には集客・売上ともに以前の10倍に発展した事例もあります 。
1-4.海外からの評価と課題
海外在住の障害者の約7割が日本の歴史的建造物へのアクセスに不安を抱いており、日本のバリアフリーは進んでいないという印象を持っています 。一方で、訪日経験者からはトイレの清潔さや日本人の親切さへのポジティブなフィードバックもありますが、宿泊施設のアクセシブルルームの不足や観光地の足場の悪さといった具体的な改善点も指摘されています。
アメリカをはじめ、他国でアクセシブルツーリズムが進んでいる理由として、法律の整備を挙げる意見が多数あり、日本における法規制の遅れや不十分さが課題となっています 。
参照:「海外在住障害者の日本アクセシブル・ツーリズム認識調査」~日本のバリアフリー観光、期待と現実のギャップ。35カ国221名の海外在住障害者の声から見えてきた課題 | 株式会社JTB総合研究所
1-5.障害者が感じる情報格差とWEBアクセシビリティ普及の課題
障害のある人やその家族の約2人に1人が、求めている情報を見つけられていない現状があります 。Googleの検索サジェストでも「障害者 情報」といったキーワードが出てくるほど、情報アクセシビリティの課題が顕在化しています 。必要な情報が見つからないために、外出ややりたいことを諦めてしまうケースも少なくありません 。
参照:「情報格差」に関するインターネット調査 | 一般社団法人Ayumi
2.2024年4月1日より障害者への「合理的配慮の義務化」

2024年4月1日より、障害者差別解消法が改正され、事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました 。これは、コンプライアンスの時代において、企業や店舗・施設が組織全体で障害者対応・バリアフリー対策に取り組む必要があることを意味します 。
バリアフリー未対応によるリスクとして、訴訟・提訴、炎上、風評被害、人材流出などが挙げられます 。実際に、精神障害を理由に入店を拒否したインターネットカフェに賠償命令が出た事例 や、車椅子利用者の入店拒否でスポーツジム会社に支払い命令が出た事例 もあります。これらの事例は、メディアで拡散され、悪いクチコミが広がり、経済的・社会的に大きなダメージを負う可能性があることを示しています 。
詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
参照:合理的配慮の提供で生産性向上とリスク回避へ〜現場理解にも繋がる対策とは?〜
3.ユニバーサルツーリズムがもたらす好影響

バリアフリー対策は、単なる義務ではなく、企業にとって大きなメリットをもたらします。
3-1.顧客層の拡大とリピート率向上
バリアフリー対策をしている店舗は、そうでない店舗との差別化になります 。実際、バリアフリー対策がされている店舗と事前に分かれば、90.2%の人が来店したいと回答しており 、利用した店舗に再度行きたいと回答した人は95.7%に上ります 。
参照:「身体障害者の店舗利用に関するアンケート」に関するインターネット調査 | 一般社団法人Ayumi
3-2.ポジティブなクチコミの拡散
バリアフリー対策や親切な接客は、来店者によってSNSなどで積極的に拡散されます 。消費者の来店判断基準は変化しており、約8割の人が評判・クチコミ・他者推薦を参考にしています 。これにより、新たな顧客層の獲得や企業イメージの向上に繋がります 。
3-3.エシカル消費の増加
近年、社会課題解決を考慮した消費活動(エシカル消費)が拡大傾向にあります 。福祉面も意識した消費が増加すると予想されており 、特にZ世代は社会貢献意欲が高く、サステナブルやSDGsに貢献する商品やお店を選ぶ傾向があります 。ユニバーサルツーリズムへの取り組みは、企業のブランディングや差別化に繋がり、こうした層からの支持を得やすくなります 。
4.「心のバリアフリー認定制度」の概要とメリット

国土交通省観光庁は、高齢者や障害のある方がより安全で快適に旅行できる環境整備を推進するため、「心のバリアフリー認定制度」を設けています 。この制度は、観光施設がバリアフリー対応とその情報発信を支援することを目的としており、認定された施設には認定マークが交付されます 。
心のバリアフリー認定制度の対象は、宿泊施設、飲食店、観光案内所、博物館です。
認定を受けるためには、以下の3つの基準をすべて満たす必要があります 。
- バリアフリー性能を補完するための措置
車椅子や杖の貸し出し 、車椅子用可動式スロープの用意 、車椅子利用者が使いやすい席の確保 、スタッフによる車椅子の段差サポート 、筆談・手話によるコミュニケーション 、点字案内物の用意 、補助犬ユーザー用のマットやボウルの貸し出し 、多目的トイレの案内 などが含まれます。飲食店では、メニューの読み上げ や配膳時の「クロックポジション」の使用 、刻み食・とろみ食 、アレルギー対応 などが挙げられます 。 - バリアフリーに関する年1回以上の教育訓練
全社員または現場に関わる人が年1回、外部のプロによる研修を受けることや 、社内で研修を行えるメンバーを配置し、毎年社内研修を実施することが推奨されています 。 - 自社サイト以外の他社サイトによる情報発信
ふらっと。やIKKEL(イッケル)のようなバリアフリー情報を発信するサイトへの掲載が必要です 。SNSでの情報発信は対象外となります 。

5.ホテル事業者が講じるべき具体的な対策

ユニバーサルツーリズムを推進し、顧客体験を向上させるためには、心のバリアフリーを意識した具体的な対策が重要です 。
5-1. バリアフリー性能を補完するための措置
ホテルにおけるバリアフリー性能を補完するための措置は多岐にわたります 。
- 移動に関する配慮:車椅子や杖の貸し出し 、車椅子用可動式スロープの用意 、車椅子利用者が通行しやすいようベッドや椅子の配置移動 、スタッフによる車椅子の段差サポート 、身体の負担を考慮した玄関近くの駐車場の確保 などが挙げられます。
- コミュニケーションの配慮:筆談や手話によるコミュニケーション 、聴覚障害のある方向けの振動や光で情報を伝える装置の設置 、視覚障害のある方向けの点字案内物の用意 、スタッフ同行による備品の説明 、テレビの字幕表示が可能なリモコンの貸し出し 、音声式デジタル時計 などが考えられます。
- 食事に関する配慮:視覚障害のある方へのメニューの読み上げ 、配膳時の「クロックポジション」の使用 、刻み食やとろみ食などの調理アレンジ対応 、食事のアレルギー対応や表記 も重要です。
- 客室・浴室に関する配慮:浴室用シャワーチェアや手すりなどの貸し出し 、シャワーチェアー 、シャワーキャリー 、滑り止めマット 、入浴用スポンジマット 、簡易設置式手すり 、延長コード 、点字表記での「ホテルご利用案内」 、筆談ボード/コミュニケーションボード/電子パッド(500円程度) などが挙げられます。
また、クローゼットの開閉や洋服掛けの位置・高さ、リモコンや内線電話の位置、室温の調整方法、シャワーの位置・高さ、洗面台の高さ、タオルを置く位置、トイレへのアクセスなど、利用者確認が必要な備品・設備の例も多くあります 。
5-2. バリアフリーに関する教育訓練
心のバリアフリー認定制度の目的は、認定を取得すること自体ではなく、毎年の研修・教育訓練を通じて心のバリアフリー対応を進め、差別化を図っていくことです 。認定制度のページに記載されている動画を見るだけでは実態と乖離することが多いため未推奨とされており 、外部のプロによる研修や 、社内で研修を行える人材の育成が推奨されます 。
5-3. 「心のバリアフリー」の重要ポイントと接客の好事例
バリアフリーな接客を心がける上で最も大切なのは、「無理をしないこと」です 。
その上で、感情と事実を切り分け、「建設的対話」を重ねることが重要です 。
5-3-1.接客のポイント
- お客様へのヒアリング:車椅子の利用有無に関わらずお客様の困っていることをヒアリングしましょう 。仕草や表情を見て、何かアプローチした方がいいか分かるようになります 。ただし、大丈夫だと思ったときは、無理に声をかけずに見守ることも必要です 。
- 直接尋ねる勇気:分からないことがあれば直接当事者へ聞いてみましょう 。健常者が障害者の立場をイメージしても分からないことが多いからです 。
- 感謝の気持ちを伝える:車椅子でも来店できるお店が少ない現状があるため、お越しいただいた感謝の気持ちを伝えることが大切です 。これによってコミュニケーションが生まれ、リピーターに繋がります 。
- 提案と実践:お客様に対してアイデアがあれば、こちらからも提案していきましょう 。どうしたら喜ばれるのかを考え、実践し、喜ばれることでリピーターに繋がります 。
- 断られても気にしない:サポートしようとして断られてもあまり気にしないようにしましょう 。不機嫌な人もいるのは一般の人と同じです。断られたらすぐに忘れるくらいの気持ちでいましょう 。
- 丁寧な応対:付き添いの人がいてもサポートが必要な方へ丁寧な応対をしましょう 。付き添いの人がいる・いないで対応が変わることが多いので気をつけましょう 。
- 魔法の言葉:初めて接客する時や困った時には、「何かお手伝いできることはありますか?」 「普段はどのようにされていますか?」 と正面から声をかけ、具体的にどのような支援が必要か、どのようなコミュニケーション方法が望ましいかを確認しながら対応することが大切です 。
5-3-2.ホテルにおける接客の好事例
- 車椅子に掛かりきらなくなった際、他の物も合わせて1つの袋にまとめてくれた 。
- 場所を探している時に、「ご案内します」と先に歩きながらも、一度振り返って「慌てなくて良いですよ、急がなくていいですよ」と声をかけてくれたことに感動した 。
- サポート後に「他に何か要望はありますか?」と最後に聞いてくれた 。
- 「荷物をお部屋まで一緒に運びましょうか?」と声をかけてくれた時、移動の苦労を理解してくれていると感じ、そのホテルのファンになった 。
- 女性スタッフが車椅子利用の子供に対して屈んで声をかけてくれたことで、いつも警戒心を持つ子供も落ち着いてランチを楽しむことができた 。
- 「足元が冷えるようでしたら、膝掛けのご用意もありますのでおっしゃってくださいね」と足元への配慮もしてくれた 。
- 「心地よく利用してもらうために教えて欲しいんですが、どのようなサポートをしたらいいですか?」と声をかけてくれたこと 。「何ができますか?」などの無鉄砲な質問が他のホテルでは多かったので、嬉しかった 。
- トイレに防犯ブザーが設置されていなくても、ポータブルのSOS発信機器を使いトラブルを未然に防いでいる 。
6.合理的配慮の対象範囲と宿泊拒否できないケース・できるケース
合理的配慮は、事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つの条件を満たす範囲に限られます 。また、提供に伴う負担が過重ではないことも要件となっています 。
- 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
- 障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること
- 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと
6-1.宿泊を拒否できないケース
- 車椅子で部屋に入れるよう、ベッドやテーブルの位置の移動を求めること 。
- 発達障害のある人が待合スペースを含む空調や音響などの設定の変更を求めること 。
- 医療的な介助が必要な障害者や重度の障害者、車椅子利用者などが宿泊を求めること 。
- 補助犬の同伴を求めること 。
- 障害を理由とした不当な差別的扱いを受け、謝罪を求めることなどによって宿泊を拒否すること 。
6-2.宿泊を拒否できるケース
- 宿泊料の割引、慰謝料、部屋のアップグレード、レイトチェックアウト、契約にない送迎などの不当な要求 。
- 特定のスタッフのみに自身を対応させること、又は特定のスタッフを出勤させないよう繰り返し要求する 。
- 土下座などの社会的相当性を欠く方法で謝罪を求める 。
- 泥酔しスタッフに対し、長時間にわたる介抱を求める 。
- 対面や電話、メールなどで長時間にわたり不当な要求をしたり、叱責しながら不当な要求を繰り返す 。
宿泊約款にルールを追記し、不当な要求への対策を検討することがおすすめです 。
合理的配慮に関する理解を資料を元に深めたい方はこちらをクリック。
7. Ayumiが提供する合理的配慮の実施への対策・バリアフリー化の伴走支援
Ayumiは、現場での課題と経営全体の戦略を両面からサポートするバリアフリー化・ユニバーサルデザインのセカンドオピニオンとして伴走支援サービスを展開しています。
具体的には、直接施設で訪問し、バリアフリー調査による現状の分析から改善策の提案、接客力向上・受け入れ体制強化に向けたワークショップを実施。
その後の定期的なフォローアップや月次レポートの共有による知識のアップデート支援まで、一貫したサポート体制で企業の合理的配慮やバリアフリー対策の実施を推進します。


8.まとめ|ユニバーサルツーリズムへの対策は経済的・社会的価値の両立を可能にします
ユニバーサルツーリズムの推進は、身体障害者人口の増加や合理的配慮の義務化といった社会の変化への対応だけではありません。新たな顧客層の開拓、リピート率の向上、ポジティブなクチコミによる集客力の強化、そしてエシカル消費を意識する層へのアピールといった、ホテル事業者・宿泊施設にとって多くのメリットをもたらします。
「心のバリアフリー認定制度」の活用はもちろんのこと、車椅子や杖の貸し出し、多目的トイレの案内などのハード面の整備、お客様への丁寧なヒアリング、建設的な話し合いといったソフト面の充実が不可欠です。
障害を理由に旅行を諦める人がいなくなるよう、誰もが旅を楽しめる社会を目指し、ホテル事業者や宿泊施設がユニバーサルツーリズムへの取り組みを一層強化していくことを期待します。また、合理的配慮は、単なる法令遵守や障害者向けの支援策に留まらず、企業の生産性向上、リスク回避、そして市場での競争力強化に直結する戦略的な投資です。小さな改善を積み重ね、現場の声を反映した取り組みを進めることで、企業は持続可能な成長を実現できます。
Ayumiは、そんな企業の伴走パートナーとして、合理的配慮の効果的な実施をサポートし、社会全体の変革に貢献することを目指しています。「まずは気軽に相談したい!」「自分たちがやっている施策について聞いて欲しい、アドバイスが欲しい」という方向けに45分の無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。