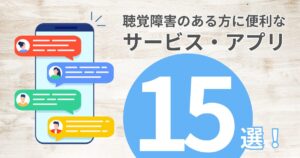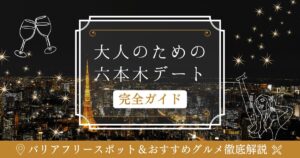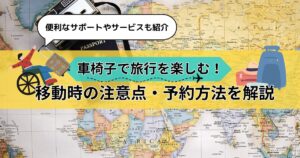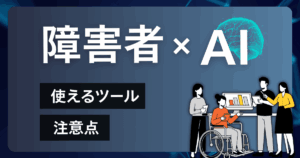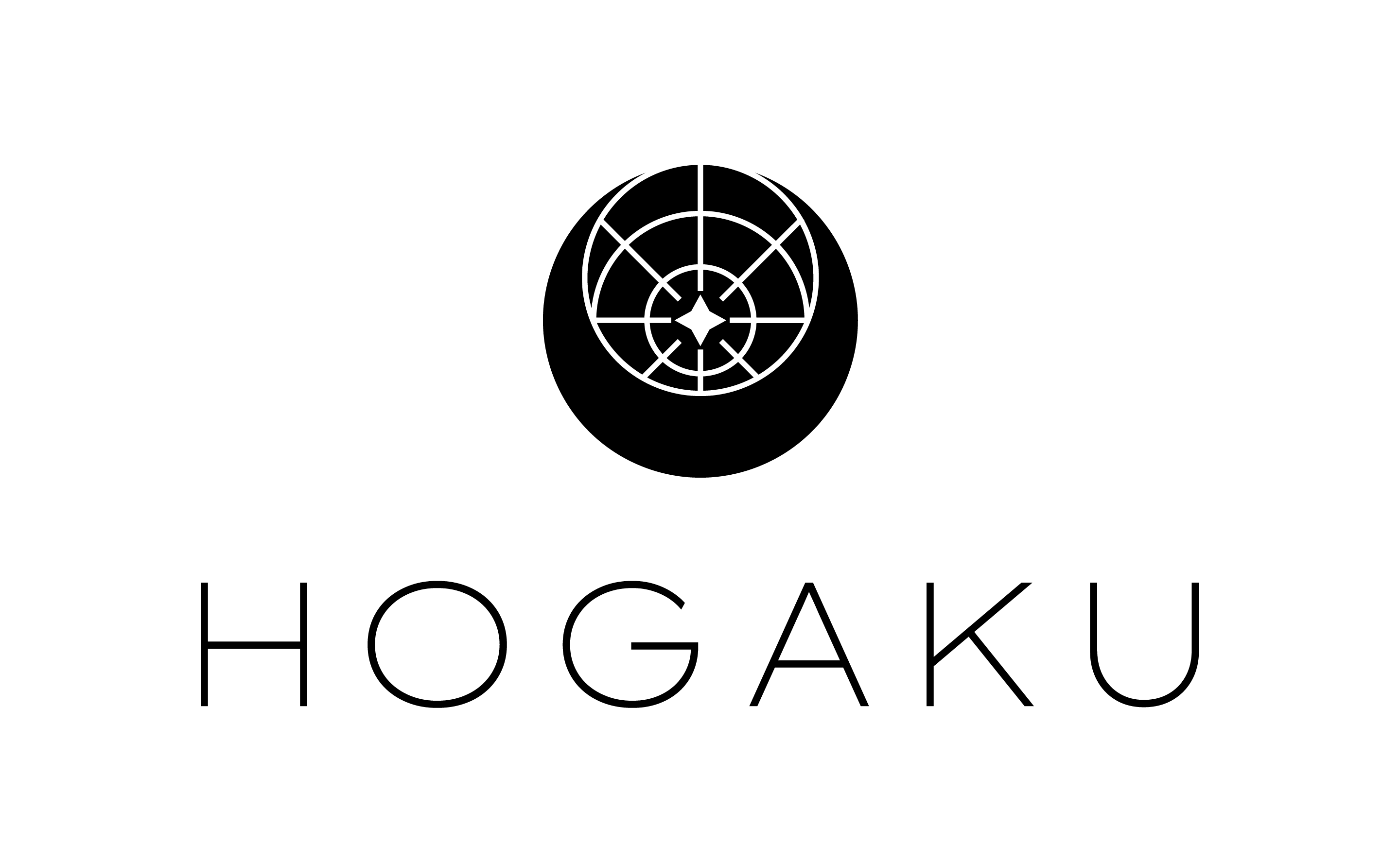「障害者を採用しても、なかなか定着しない」
「現場の理解が足りず、負担が増えている」
「法令は遵守したいが、実践するのは難しい」
障害者雇用について、多くの経営者・人事担当者が同じ悩みを抱えているのではないでしょうか。
とはいえ、障害者雇用は「企業にとっての負担」ではありません。多彩な人材が働くインクルーシブな環境は、新たな発想とイノベーションを生み出し、企業全体の成長エンジンとなる可能性があるのです。
そこで今回は、企業が直面しがちな障害者雇用に関する課題と具体的な解決策を、最新の事例や実体験も交えながらご紹介します。
障害者雇用を「未来への投資」に変え、企業の競争力を高める次の一手をお探しの方は、ぜひご覧ください。
1.障害者雇用の現状

まず、障害者雇用を取り巻く現在の状況を、制度、実績、リスクの3つの側面から見ていきましょう。
1つ目は制度についてです。障害者雇用促進法に基づき、企業は従業員数に応じて一定割合以上の障害者を雇用する義務を負っています。この制度が『障害者雇用法定雇用率』です。
- 対象企業と法定雇用率
2024年4月から、民間企業に課せられている障害者雇用法定雇用率は2.5%と定められており、常用労働者が40人以上在籍する企業は、従業員のうち少なくとも1人以上の障害者を雇用しなければならない義務があります。 - 今後予定されている法定雇用率の引き上げ
障害者雇用法定雇用率は固定ではなく、社会状況の変化や障害者の就業実態を踏まえ、定期的に見直されます。すでに2026年7月からは2.7%へ引き上げが決定しており、企業には早めの準備が求められています。 - 雇用率の算定方法
雇用率を計算する際、障害の程度や労働時間によってカウント方法が異なります。
週20時間以上30時間未満勤務の短時間労働者は0.5人としてカウントされ、重度の身体障害者や知的障害者を雇用する場合は、1人を2人分と計算する制度(ダブルカウント)も導入されています。雇用率の算定方法により、企業の負担を一定程度軽減する仕組みが整備されているのです。
2つ目は実績についてです。2024年時点での障害者雇用達成率と未達成企業の割合を見てみましょう。
厚生労働省の公表によると、障害者雇用の実績は年々改善傾向です。特に精神障害者の雇用は対前年比15.7%増と大きく伸び、さまざまな障害を持つ人々が職場で活躍しています。
ですが、現実には課題も残されています。2023年のデータでは、従業員40〜100人規模の企業で法定雇用率を満たしているのは半数以下にとどまっています。企業が障害者雇用の必要性を理解していても、実際の採用や定着に苦労していると言えるでしょう。
さらに深刻なのが職場定着率の問題です。精神障害者の1年後の定着率は49.3%と半数を下回る水準にとどまっています。
採用後のフォローや職場環境にミスマッチが生じているケースも多く、企業が「雇用はしたものの、定着しない」という壁に直面している実態が浮き彫りになっています。
3つ目は未達成企業が直面する行政指導や納付金のリスクについてです。
法定雇用率を達成できない企業には、ハローワークから行政指導が行われます。状況が改善しない場合は特別指導に進み、最終的には企業名の公表措置が取られる場合もあります。企業名が公表されれば社会的信用の低下や企業イメージの悪化は避けられないでしょう。
また、常用労働者が100人を超える企業が法定雇用率未達成の場合、不足人数1人あたり月額50,000円の納付金が発生します。納付金は調整金や助成金の原資として活用される仕組みですが、企業にとっては経済的な負担要因となるでしょう。
納付金制度は今後、従業員100人以下の企業にも拡大する方向で検討されています。将来的にはより多くの企業が対象となる可能性が高まっており、制度の動向に注意が必要です。金銭面以外にも風評被害や人材の流出など、経営リスクも無視できません。
障害者雇用法定雇用率は、企業にとって法令順守だけでなく、採用・定着・支援体制の整備を求める重要な制度です。今後の雇用率引き上げや制度改正を見据え、早期の準備と組織全体での取り組みが求められています。
参照:行政指導|厚生労働省
2.障害者雇用に企業が今取り組むべき理由

法的な義務やリスク回避という側面だけでなく、企業が積極的に障害者雇用を推進すべき理由はさまざまです。3つの観点から障害者雇用の意義を解説します。
1つ目は、2027年に向けた関連法改正と今後の動きについてです。
前述の通り、法定雇用率は段階的に引き上げられ、2026年7月には2.7%となる見込みです。約37人の従業員がいれば1人の障害者を雇用する必要がある計算になります。
さらに、納付金制度の対象拡大に向けた議論も進んでいます。2027年以降を見据え、小規模な企業にも社会的責任を果たすよう求める流れは加速するでしょう。
こうした法改正の動きは、障害者雇用が多い一部の大企業だけではなく、すべての企業に関わる可能性があるのです。変化の先を読み準備を進めることが、将来の安定経営につながります。
2つ目は企業の社会的責任とブランディングへの影響についてです。
現代の企業経営において、CSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)投資は不可欠です。障害者雇用への積極的な取り組みは、企業価値を大きく向上させるでしょう。
例えば、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を推進し、さまざまな人材が活躍できる場を提供している企業は、顧客、投資家、取引先といったステークホルダーから高く評価されます。この取り組みは、企業のサステナビリティ(持続可能性)を示すメッセージとなるのです。
また、Z世代と呼ばれる若い世代は、企業の社会貢献意識を就職先選びの基準のひとつとしています。ある調査では、就職活動する学生の約7割が社会貢献につながるビジネスに関わりたいと回答しました。倫理的な経営姿勢を打ち出すことは、意欲の高い優秀な人材を惹きつける要因となるでしょう。
最後3つ目は、インクルーシブな職場づくりが企業にもたらすメリットについてです。
障害のある人を受け入れるための環境整備は、結果としてすべての従業員にとって働きやすい職場環境を生み出し、企業全体にプラスの効果をもたらします。
さまざまな角度の視点や価値観が組織に加わることで、固定観念にとらわれない新しい発想が生まれやすくなるでしょう。業務プロセスの見直しやコミュニケーションの活性化が促され、組織全体の生産性や創造性の向上が期待できます。
障害のある従業員が能力を発揮できる職場は、従業員エンゲージメント向上に期待できる環境です。
さらに、障害者雇用に取り組む職場では「コミュニケーションが向上した」「業務が整理・改善された」といった効果が報告されています。互いを尊重し、支え合う文化は、従業員の定着率を高め、組織の一体感を高めます。
障害者雇用は、単なる「数合わせ」ではありません。さまざまな視点の人材が「共に働き」「共に成長」するインクルーシブな環境を築くことで、企業の持続的な成長を実現可能にしてくれるのです。
3.企業が抱える障害者雇用の課題

多くの企業が障害者雇用の意義を理解しつつも、実践の段階でさまざまな壁にぶつかります。ここでは、企業が直面しがちな3つの課題と背景について解説します。
1つ目の課題は障害者への理解不足です。
障害者雇用における深刻な問題のひとつは、企業と障害のある従業員の間に生じる相互理解の不足です。お互いの理解不足は、さまざまなミスマッチを生み出しています。
- 能力と業務内容のミスマッチ
本人のスキルや適性を正確に把握しないまま、過度に簡単な業務しか与えない、あるいは逆に過大な業務を課してしまうケースがあります。これにより、意欲の低下や業務遂行の困難が生じる場合があります。 - 障害特性と職場環境のミスマッチ
例えば、「聴覚障害のある従業員に口頭だけで指示を出す」や「精神障害のある従業員に疲労を無視した長時間会議を設定する」といった配慮不足が見られます。物理的な設備だけでなく、業務の進め方やコミュニケーション方法の工夫は欠かせません。 - 入社前のイメージと実際の業務のミスマッチ
面接時の説明と実際の仕事内容が異なることで、期待と現実にギャップが生じる場合もあります。企業側の期待と本人の想定がずれることで早期離職につながりやすくなります。
相互理解のミスマッチは、障害者という一括りで判断せず、一人ひとりの特性や背景に合わせた柔軟な対応が必要となるでしょう。
2つ目は合理的配慮の範囲設定の難しさです。
障害者雇用促進法では、企業に対して「合理的配慮」の提供が義務付けられています。合理的配慮とは、本人からの申し出に基づき、企業が経営上の大きな負担にならない範囲で、一人ひとりにサポートや環境整備をすることです。
具体的には、PCの音声読み上げソフト導入といった設備面の対応から、マニュアルの図解化や本人の特性に合わせた業務割り当て、時差出勤や通院への柔軟な対応、分かりやすい指示伝達や定期的な面談といった、業務の進め方やコミュニケーション上の工夫まで多岐にわたります。
合理的配慮は企業が一方的に決めるものではなく、本人との丁寧な対話を通じて、どのような支援が実用的か検討する姿勢が重要です。
合理的配慮についてもっと詳しくしりたい方は、下記の記事もご覧ください。
参照:合理的配慮の提供で生産性向上とリスク回避へ〜現場理解にも繋がる対策とは?〜
参照:雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務|厚生労働省
3つ目はコストや人的リソースへの負担です。
障害者雇用の推進には現実的な負担も伴います。おもな負担は以下の3つです。
- 経済的負担
バリアフリー化や支援ツール導入には費用がかかります。ただし、国はこれらの費用を軽減する助成金制度を用意しています。 - 人的リソースの負担
合理的配慮の実施や日常のサポートには、周囲の従業員の協力が欠かせません。特定の担当者に負担が偏らないよう、組織全体で支え合う体制が必要です。 - マネジメント負担
障害者の特性に配慮した適切なマネジメントをするには、管理職にも専門知識やスキルが求められます。現場任せにせず、人事部門が主導して研修や支援体制の整備が有効です。
障害者雇用の負担を、単なるコストと考えてはいけません。全従業員が働きやすい環境を作るための「未来への投資」です。発想を転換させることが、障害者雇用の課題解決につながるでしょう。
4.障害者雇用で働く障害者の実体験を紹介

ここまでは、制度や企業の視点から障害者雇用の現状と課題を解説してきました。では、実際に障害者雇用枠で働く当事者は、日々の業務で何を感じ、どのような壁に直面しているのでしょうか。実体験を紹介します。
この方は、支援機関のサポートを経て約5年前に保険会社へ入社し、現在は契約社員として活躍しています。着実にキャリアを積み重ねていますが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。
入社してまず直面したのは、現場の管理職における障害理解の不足です。障害者雇用の制度自体は社内に整備されていても、直属の上司が障害特性を正しく理解しているとは限りません。
特に、定期的な異動で上司が変わるたびに、自ら障害の特性を一から説明し直し、人間関係を築き直す必要がありました。これは、精神障害を持っている人にとって大きな精神的負担です。
さらに深刻だったのは、業務内容のミスマッチでした。当初配属された部署で、精神障害を抱える本人が、複数の知的障害のある同僚の業務を取りまとめる役割を任されたのです。異なる障害特性を一括りに考えていた、典型的な配置ミスと言えます。
職場環境が合わず心身に不調をきたす障害者も少なくありません。この方の周囲でも、離職には至らずとも、同じ職場で何度も休職を繰り返す同僚がいたといいます。
この方は、勇気を出して上司に部署異動を申し出たことで状況が改善しました。しかし、誰もがそのように声を上げられるわけではありません。
必要な配慮を訴えられず、心身の負担を抱えながら働き続けたり、最終的に離職に至ったりするケースも残念ながら存在します。
実体験を聞いてわかったことは、企業側が障害のある従業員一人ひとりの特性と向き合い、継続的にコミュニケーションをとりながら、適切な業務と環境を提供する仕組みを整える必要性があるということです。
5.障害者雇用を支援している会社の利用も検討する

障害者雇用の推進において、多くの企業が直面するミスマッチや定着の課題。これらを自社のリソースだけで解決するには限界があるかもしれません。専門的な知見を持つ外部の支援サービスを活用することは、障害者雇用を成功に導く有効な手段です。
ポイントは以下の5つ。
- 外部支援がもたらす解決策
障害者雇用支援サービスは、企業と障害のある方の間に立ち、双方にとって良好なマッチングと安定した雇用継続を実現する多角的なサポートを提供します。 - 専門性に基づくミスマッチの解消
支援機関は、障害の特性、法制度、助成金制度、コミュニケーション方法などに精通しています。企業の求める人物像と障害者のスキルや希望を総合的に評価し、採用時のミスマッチを未然に防ぎます。 - 採用から定着までの一貫支援
人材紹介にとどまらず、採用後も定着を支援します。例えば、職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣し、業務の指導や社内コミュニケーションの円滑化をサポートします。定期的な面談により悩みを早期に把握し、離職リスクの軽減にもつなげます。 - 多様な働き方の提案
近年では、企業の状況や障害特性に応じた柔軟な働き方の提案も広がっています。専門スタッフの支援を受けながら働ける農園型、通勤負担が軽減されるサテライトオフィス型など、選択肢が多様化しています。 - 社内理解の促進
障害者雇用の課題として、既存従業員の理解不足が挙げられます。支援サービスは、障害理解に関する社内研修を企画・実施し、職場全体のインクルーシブな文化を作ることを後押しします。
障害のある従業員が能力を発揮するためにはスクールも有効です。下記の記事も参考にしてください。
参照:コミュニティ機能もある障がい者のためのビジネススクール「D-Biz College」
参照:平均年収60万円UP?障害者に特化したオンラインスクールを提供する株式会社RESTAを紹介!
障害者雇用に積極的な企業姿勢を社会に発信できなければ、優秀な障害者人材との出会いの機会が限定されてしまうでしょう。こうした課題に対し、私たち一般社団法人Ayumiでは、広告を活用した新たな支援策を展開しています。
具体的には、駅のエスカレーター等に掲示する「UD(ユニバーサルデザイン)エスカレーターベルト装飾」を通じて、企業のダイバーシティ経営や社会貢献姿勢を広くアピールします。公共の場で企業の取り組みを視覚的に伝えることで、ブランドイメージの向上と共感する人材を惹きつけるのです。
採用や定着の課題解決と並行して、自社の魅力を積極的に発信し採用の間口を広げる「採用ブランディング」も障害者雇用を安定させる有効な施策のひとつと言えるでしょう。
「まず話を聞いてみたい」「施策の方向性を相談したい」という方は、無料相談も実施中です。下記のURLよりお申し込みください。
6.まとめ
障害者雇用は、法的義務として取り組むべき課題であると同時に、経営戦略の一環でもあります。法定雇用率の引き上げや納付金制度の拡大といった制度変更が進む中、企業は早期に準備を進め、安定した雇用体制を整える必要があるでしょう。
障害者一人ひとりの状況、性格を正しく理解し、業務内容や職場環境、コミュニケーション体制を整備することが不可欠です。多彩な人材が能力を最大限に発揮できるインクルーシブな環境は、組織に新しい視点をもたらし、イノベーションを引き起こす可能性を秘めています。
障害者雇用を企業ブランドの強化や人材獲得戦略に活用する新たなアプローチも注目されています。外部支援サービスの活用により、採用から定着までを一貫してサポートしてもらうとともに、積極的な広報活動によって企業のブランディングを社会に発信する取り組みも有効です。
障害者雇用を、単なる「義務やコスト」として捉えるのではなく、企業の未来を豊かにする「投資」として、ぜひ前向きな一歩を踏み出してください。持続的な成長を目指す企業にとって、今こそ主体的に障害者雇用に向き合う姿勢が求められています。