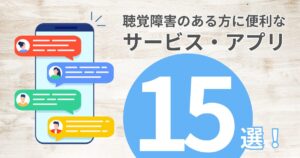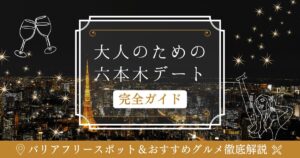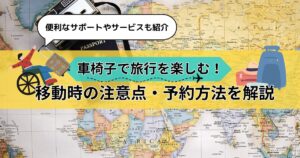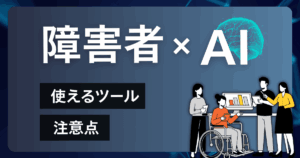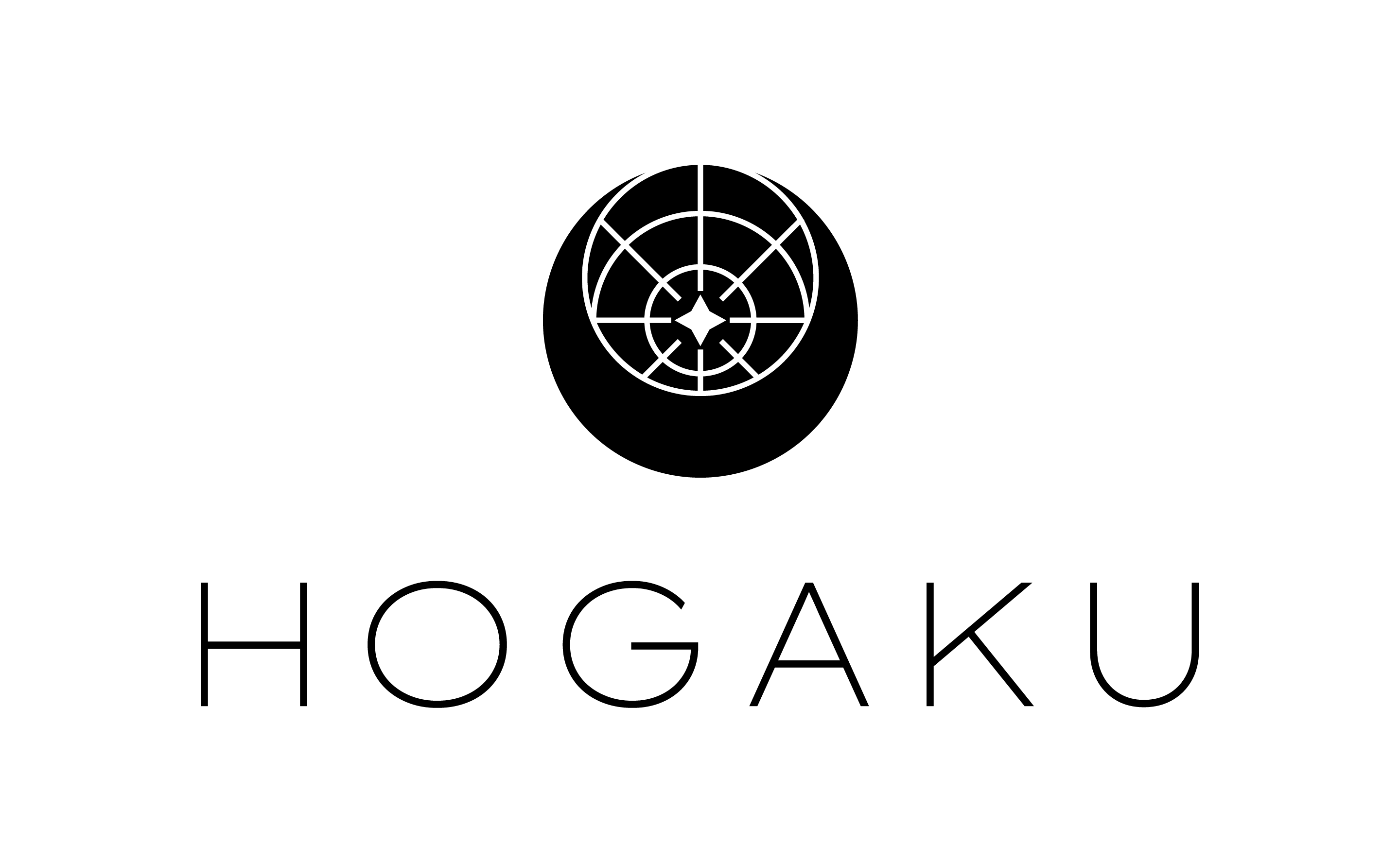みなさんは、「バリアフリー新法」という法律をご存知でしょうか?
2020年に続き2025年6月にも、一部改正されました。ニュースなどでもよく取り上げられていたため、名前は聞いたことがある、なんとなく知っているという方も多いのではないでしょうか。
今回は、なかなか法律としてきちんと知る機会の少ないバリアフリー新法について解説していきます
そもそもバリアフリーとはなにか、詳しく知りたい方はこちらをお読みください。
参照:バリアフリーとは?言葉の意味や身近な実例をふまえてどこよりもわかりやすく説明!
目次
1.バリアフリー法とバリアフリー新法との違い
「バリアフリー法」と「バリアフリー新法」は、呼び方こそ少し違いますが、実質的には同じ法律を指しています。
一般に「バリアフリー新法」とは、2006年に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)を指す名称です。この新法は、従来の複数の関連法を統合・強化して制定されたもので、バリアフリー施策の中核を担う重要な法律です。
2.2025年6月バリアフリー法改正の内容とは?
2025年6月1日より、「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が改正され、日常生活で多くの人が利用する設備に関する基準が強化されました。特に「トイレ」「駐車場」「劇場等の客席」に関して、より実用的な基準が新たに導入されています。
今回の改正の目的は、車椅子使用者を含む誰もが安全・快適に施設を利用できるようにすることです。単なる設置義務の強化ではなく、現場の実態に合った「真のユニバーサルデザイン」への転換が求められています。
バリアフリー法の改正ポイントをわかりやすく表にしました。
| 対象項目 | 改正前の基準 ~2025年5月 | 改正後の基準 2025年6月~ | 備考 |
| トイレ | 車椅子使用者用便房を1つ以上設置 | 原則、各階に1つ以上の設置を義務化 | 床面積が1,000㎡未満の階や、10,000㎡超の階などには例外規定あり |
| 駐車場 | 専用駐車スペースを1つ以上設置 | 台数に応じた割合で義務化例:200台以下→2%以上、200台超→1%+2台以上 | 法人施設なども対象 |
| 劇場等の客席 | 特段の規定なし(設置推奨) | 車椅子使用者用スペースの設置が義務化例:400席以下→2スペース以上、400席超→0.5%以上 | 新設・大規模改修時に適用 |
今回の法改正は、単に設備を増やすだけではありません。すべての人が自分らしく生活できる空間の実現を目指しています。
- 車椅子で移動しても階ごとにトイレがある
- 駐車時に近くに優先スペースが確保されている
- 劇場で家族と同じ空間で観覧できる
こうした「当たり前」が整備されることで、バリアフリー社会の実現が可能となるのです。
3.バリアフリー新法とは?

3-1.法律の目的
バリアフリー新法の法律文面では、「高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と記載があります。
つまり、交通機関や建物などのバリアフリー化を進めることで、身体的・精神的な利便性・安全性を高めることが目的です。
もともとバリアフリー新法は、平成18年(2006年)に「ハートビル法」(病院やデパートなど不特定かつ多数の人が利用する建物にバリアフリー化を義務付ける法律)と「交通バリアフリー法」(鉄道やバスなどの公共交通機関にバリアフリー化を義務付ける法律)を統合する形で施行されました。
3-2.基本方針
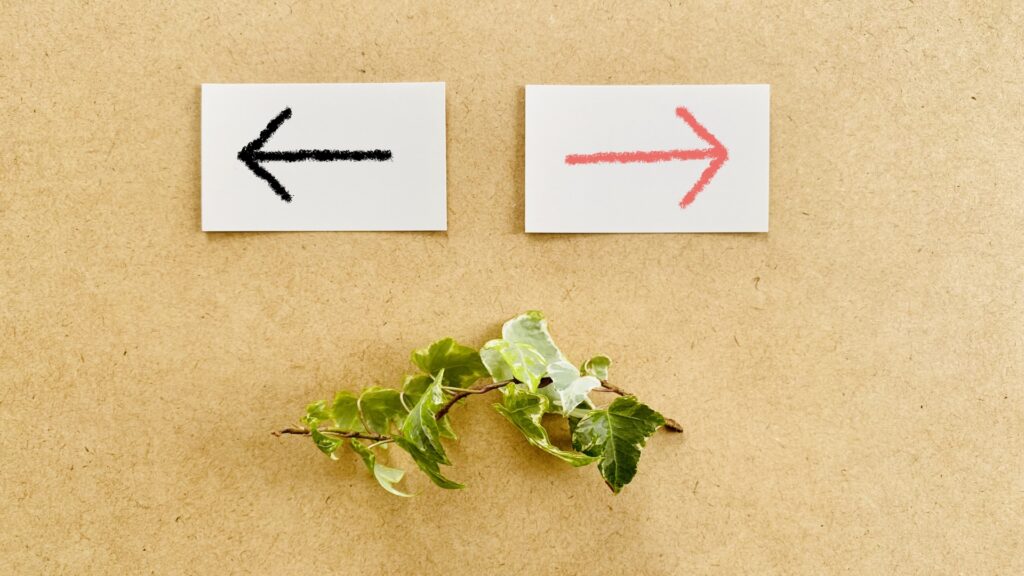
①バリアフリー化の意義・目標
バリアフリー化の意義として、下記3つを提唱しています。
- 「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づいた整備の実現
- 身体障害者のみならず、知的障害者・精神障害者・発達障害者を含むすべての障害者が対象
- 高齢者・障害者の意見の反映
また、ノンステップバスを全体の30%にすること、福祉タクシーを約18,000台にすることなどの数値 目標を掲げています。
②施設設置管理者が行うべき措置
計画的な研修・マニュアル整備などによる職員への教育などを適切に行うことを、交通機関や建物などの所有者がすべき措置として定めています。
③市町村の基本構想の策定
市町村に対し、施策を推し進めるため、特に力を入れる地域の特定や、いつ施策を行うかなどの基本構 想を定めるよう要求しています。
④その他
国民は、バリアフリー化促進に対し理解・協力をするよう定められています。
国は、これらの基本方針をもとに、次章で紹介する義務付けられた基準を定めました。
4.バリアフリー新法によって義務付けられた基準

下記の施設を新たに作る場合は、それぞれの基準への適合が義務付けられています。また、既存の施設においては、努力義務が課せられています。
4-1.公共交通機関
駅(電車、バス、船、飛行機)
・駅の出入口からプラットホームへの経路には、原則エレベーターまたはスロープにより高低差をなくす。
・車椅子が通るための通路幅を確保する。
・プラットホームと車両との隙間はできるかぎり小さくする。隙間や段差が大きい場合は車椅子使用者の乗降をスムーズに行える設備を1つ以上備える。
・プラットホームにはホームドア、可動式ホーム柵、点状ブロックその他視覚障害者の転落を防止する設備を設ける。
・通路、プラットホームなど照明設備を設ける。
・エレベーター、エスカレーター、トイレ、券売機などは高齢者・障害者等が使いやすい構造とする。
・視覚障害者誘導用ブロック、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を設ける。
・エレベーター、トイレなど主要な設備の付近には、JIS規格に適合する標識を設置する。
・乗車券などの販売所、案内所に筆談用具を設け、筆談用具があることを表示する。
車両(電車、バス、船、飛行機)
・電車、バス、船、飛行機には、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を設ける。
・電車、バス、船には、車椅子スペースを設置する。
・電車・船内のトイレは高齢者・障害者等が使いやすい構造とする。
鉄道車両
・列車の連結部にはプラットホーム上の乗客の転落を防止するための措置を講じる。
・車両番号などを文字および点字で表記する。
バス
・低床バス(ノンステップ、ワンステップレベル)とする。
・筆談用具を設け、筆談用具があることを表示する。

福祉タクシー
①車椅子等対応車
・車椅子などの使用者の乗降をスムーズに行える設備を備える。
・車椅子などの用具を備えておくスペースを1以上設ける。
・筆談用具を設ける。
②回転シート車
・助手席または後部座席を回転させるための設備を設ける。
・折りたたんだ車椅子を備えておくスペースを1以上設ける。
・筆談用具を設ける。
船
・バリアフリー化された客席を設置する。
・客席からトイレ、食堂などに通じる1以上の経路にエレベーターなどの設置をし
高齢者、障害者等が単独で移動できる構造とする。
・食堂、売店には筆談用具を設け、筆談用具があることを表示する。
飛行機
・通路側座席の半数以上に可動式ひじ掛けを設置する。(客席数が30以上の場合)
・トイレは、車椅子利用者が使いやすい構造とする。(通路が2つ以上ある場合)
・飛行機内で使用できる車椅子を備える。(客席数が60以上の場合)
4-2.道路

実は、道路にもバリアフリー化の義務があります。
国土交通大臣が指定した「特定道路」は、高齢者や障害のある方が利用することを想定した道路です。
特定道路は、バリアフリー化が努力義務ではなく、法的に義務付けられています。
- 管理者は、道路に関するバリアフリー化基準(道路移動等円滑化基準※)に適合するよう努める。※道路移動等円滑化基準
- 幅の広い歩道の設置
- 歩道の段差解消・勾配改善
- 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- 案内標識の設置
- エレベーターの設置
- バスに乗りやすい歩道の高さの確保
- ベンチなどの休憩施設の設置
4-3.信号機等

当たり前にある信号機や道路標識の機能も、実はバリアフリー化として義務付けられています。
・信号機
音響機能・歩行者用青時間延長機能または経過時間表示機能を付加したもの、あるいは歩車分離方式のものとする。
・道路標識・道路標示
反射材などを利用して見やすくわかりやすいものとする。また、横断歩道には必要に応じて視覚障害者誘導ブロックを設ける。
4-4.路外駐車場

特定路外駐車場※を設置する際は下記を守らなければいけません。
・出入口にできるだけ近い位置に車椅子使用者用の駐車スペースを1つ以上確保する。
・車椅子使用者用の駐車スペースには看板・路面表示などで表示する。
※1 特定路外駐車場:駐車の用に供する部分が500m2以上、かつその利用に対して料金を徴収している路外駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場。
引用元:路外駐車場のバリアフリー化について|国土交通省
4-5.都市公園

私たちが普段何気なく行っている公園にも、バリアフリー新法は適用されています。
特定公園施設※を新設・増設・改築を行う場合は、下記都市公園に関するバリアフリー化基準(都市公園移動等円滑化基準)を守らなくてはいけません。
- トイレ・管理事務所・水飲場は車椅子使用者が使いやすい構造とする。
- 野外劇場・野外音楽堂には車椅子使用者が観覧できるスペースを確保する。
- 車椅子使用者が駐車できる駐車スペースを確保する。 など
※特定公園施設・・・園路、広場、屋根付広場、休憩所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲場、手洗場、管理事務所、掲示板、標識
引用元:都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン|国土交通省
4-6.建築物

不特定かつ多数の人が利用する百貨店や劇場、ホテル、高齢者や障害者が利用する老人ホームなどの施設などでも、一定規模以上の新築等※を行う場合は、バリアフリー化が義務付けられています。
※一定規模以上の新築等・・・建築工事をする床面積の合計が2,000㎡(公衆便所については50㎡)以上となる新築、増改築や用途変更
引用元:バリアフリー新法の解説|国土交通省
5.バリアフリー新法による主な支援策

5-1.補助
国土交通省では、バリアフリー新法でさまざまな補助を行っています。
例えば、ノンステップバスの購入資金を補助する「公共交通移動円滑化設備整備費補助(バリフリ補助)」などがあります。
5-2.政策融資
また、低金利で融資を行う支援策も行っています。
「人にやさしい建築物整備事業」では、認定建築物の廊下、階段、エレベーターなどの特定施設の新設にあたって、無利子貸付制度があります。
参照:人にやさしい建築物(ハートフルビルディング)整備事業|国土交通省
5-3.税制
特定の建物のオーナーだけでなく、個人でも、税制特例措置を受けられます。
「住宅のバリアフリー改修促進税制」では、自宅の一定のバリアフリー改修工事を行った場合、所得税額が一定額控除されます。
このように、国が補助、政策融資、税制を策定することで、バリアフリー化を推進しています。
ほかにもさまざまな補助などがあるので、ご興味がある場合はぜひご自身で調べてみてくださいね。
バリアフリーな家づくりについて、詳しく知りたい方はこちらのAyumiの記事をご覧ください。
参照:障害のあるこどもとバリアフリー住宅に住む上で大事なこととは?
6.2020年に改正されたバリアフリー新法について
6-1.改正の背景とこれまでの課題

2020年にバリアフリー新法が改正されました。2006年の施行から14年が経ち、さまざまな課題が見えてきたためです。
①ハード・ソフト両面のバリアフリー化対応ができていない。
施設のバリアフリー整備といったハード面に加え、駅員に対する高齢者や障害者への適切な接し方の教育や、支援対応に関するソフト面のバリアフリー化も十分に進んでいません。
②バリアフリー化の推進の地域格差が大きい。
基本方針である市町村の基本構想の策定がそもそも進んでいないのが現状です。
2016年の調査によると、1,735市町村のうち、基本構想を策定していたのはわずか288(16.6%)にとどまっていました。さらに、そのほとんど(288中275)は、1日あたり3,000人以上の旅客施設を有する市町村であり、それ未満の地域ではほとんど策定が進んでいない現状が明らかになっています。
参照:基本構想作成予定等調査(調査結果の概要 :平成28年3月末時点現在(平成29年2月1日公表))|国土交通省
③利用のしやすさに問題がある。
バリアフリー新法の一番重要な部分は利用のしやすさです。
約20年間施行され、下記のような利用しやすさの問題が出てきました。
- 観光立国を目指しているにもかかわらず、貸切バスや遊覧船などのバリアフリー化がなされていない。
- バリアフリー化の積極的な情報提供が少ない。
- バリアフリー化への障害者当事者の評価や参画が足りていない。
6-2.基本理念の規定
通常、法律には基本理念はあまり設けられません。しかし、今回の改正では、「共生社会の実現」や「社会的障壁の除去」といった基本理念を新しく掲げています。
6-3.公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進
施設のバリアフリー化などのハード施策に加え、事業者側の接遇や研修のあり方を含むソフト対策のメニューを国土交通省が新たに作成することとなりました。事業者側も、ハード・ソフト共に計画を作成し、定期的な取り組み内容の公表と報告を行わなければいけません。
6-4.バリアフリーの街づくりに向けた地域における取組強化
市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度(基本構想の前段階に当たるもの)が創設されました。
協議会における調整や都道府県によるサポート、制度作成経費の支援などを行うものです。
6-5.さらなる利用のしやすさに向けた様々な施策の充実
バリアフリー化された施設を増やすことと、情報提供、評価を行うことでさらなる利用のしやすさを目指し、下記施策が追加されました。
- 貸切バスや遊覧船等の導入時におけるバリアフリー適合基準を義務化
- 建築物等のバリアフリー情報の提供を新たに努力義務化
- 国が主導して障害者などが参画する施行内容の評価等を行う会議を開催
7.バリアフリー法に基づく2025年末までの目標について

改正に伴い、国土交通省は2025年末までの目標を定めました。
それぞれ要約して解説していきます。
・旅客施設(鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港)
文字や音声による運行情報、案内図記号などによる標識などの設置。
・鉄軌道駅、バスターミナル
平均利用者数が3,000人/日以上の施設、2,000人以上3,000人未満/日で、基本構想の生活関連施設※に位置づけられた施設を原則すべてバリアフリー化。
※基本構想の生活関連施設・・・高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、 官公庁施設、福祉施設その他の施設(法第2条 第1項 第 21 号イ)
イ 生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活 又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。
引用元:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に 関する法律(平成18年法律第91号)|国土交通省
旅客船ターミナル、空港
・平均利用者数が2,000人/日以上の施設を原則すべてバリアフリー化。

鉄軌道駅
・3,000番線にホームドア・可動式ホーム柵を設ける。(全国の総番線数:19,951、うち整備済み:1,953(2019年度末時点))
・可能な限りバリアフリールートの複数化を進める。
・可能な限りプラットホームと乗降口の段差・隙間を縮める。
鉄道
・新幹線車両の車椅子用フリースペースの整備を進める。
航空機
・全670機のバリアフリー化。
旅客船
・全700隻中60%をバリアフリー化。
乗合バス車両
・全5万台中80%をバリアフリー化。
タクシー
・約90,000台の福祉タクシーを導入(2019年度末時点:37,064台)。
・各都道府県における総車両数の約25%をユニバーサルデザインタクシーとする
信号機
・ 重点整備地区内の信号機は原則すべて音響機能付信号とする。
都市公園
・園路および広場(約9,000箇所)の約70%をバリアフリー化(2018年度末時点:約63%)。
・駐車場(約6,000箇所)の約60%をバリアフリー化(2018年度末時点:約53%)。
・トイレ(約9,000箇所)の約70%をバリアフリー化(2018年度末時点:約61%)。

建築物
・床面積が2,000㎡未満の特別特定建築物についてもバリアフリー化を促進。
・公立小中学校では、文部科学省にて目標を定め、障害者対応型トイレやスロープ、エレベーターの設置などのバリアフリー化を進める。
マスタープラン・基本構想の作成
・マスタープラン:約350自治体(全市町村(約1,740)の2割)
・基本構想:約450自治体(平均利用者数2,000人以上/日の鉄軌道駅およびバスターミナルが存在する市町村(約730)の6割)
心のバリアフリー
・バリアフリー化に対し国民の理解と協力が得られることが当たり前の社会となるよう環境を整備する。
・「心のバリアフリー」用語の認知:約50%(2020年6月時点:約24%)
・高齢者・障害者等の立場を理解し行動できている人:原則100%(2020年6月時点:約80%)
心のバリアフリーとは何か、詳しく知りたい方はぜひこちらの記事もご覧ください。
参照:心のバリアフリーとは? 基礎的な考え方や事例をわかりやすく紹介
参照:バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について(最終とりまとめ)(概要)|国土交通省
8.最後に

私たちが生活するのに欠かせない交通機関や施設は、実はバリアフリー新法という法律によって、設置しなければならない設備などが決まっていることをおわかりいただけたでしょうか?
しかし、現状はまだまだバリアフリー化が進んでいないため、改善策として2020年に続き2025年6月にもバリアフリー新法が改正されました。
注目すべきは、やはりソフト面のバリアフリー化の推進です。
いくら設備が充実しても、それを運営する人間が使いこなせなければ意味がありません。
また、心のバリアフリーを全国民に浸透させることも、今後バリアフリー化を推し進めるためには重要となってきます。国民の、高齢者・障害者の方への理解や、理解したうえで手助けするなどの行動が当たり前の社会になってほしいですね。
法律を理解したうえで、さまざまな施設を見るとまた新たな改善策が見つかるかもしれません。それをふまえて、積極的に行政へ意見などを寄せてみてはいかがでしょうか?
当事者意識を持つことで、少しずつでも住みやすい国にしていきましょう!