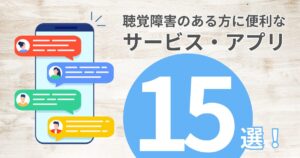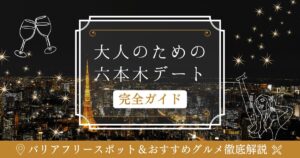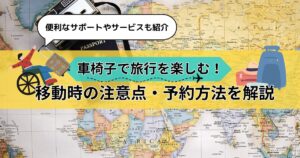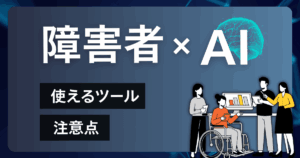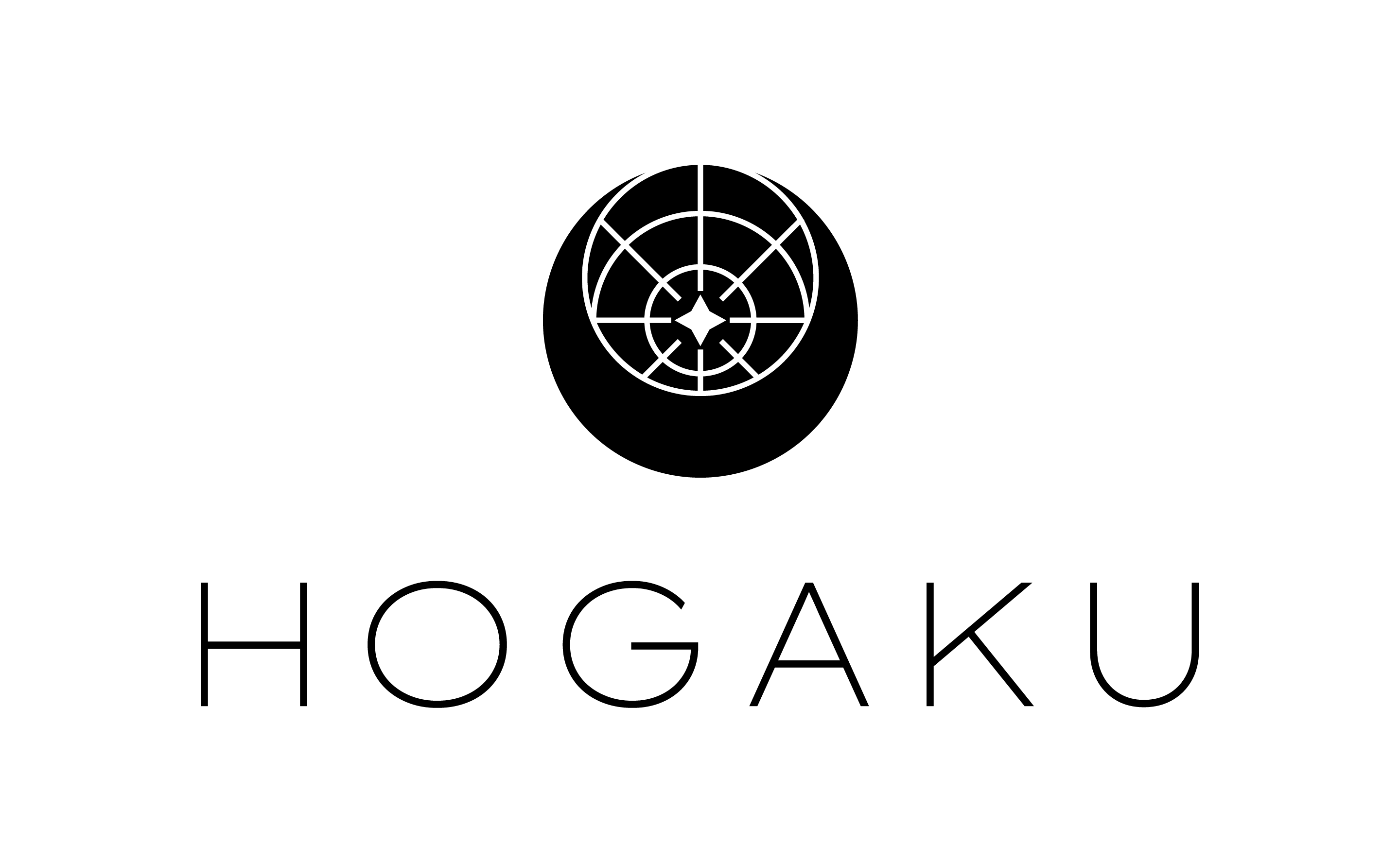2006年12月にバリアフリー新法が施行されて以降、公共施設やサービスの整備が進み、多様性を持つ人が利用しやすい環境づくりが広がってきました。
こうした法制度に基づく取り組みと並行して注目されているのが「インクルーシブデザイン」です。
インクルーシブデザインとは、障害者や高齢者、外国人を含め、誰もが快適に利用できる設計をする考え方です。
従来の「平均的な利用者」を前提にした設計とは異なり、少数派の声や体験を積極的に取り入れることで、より幅広い人にとって使いやすい仕組みを実現します。
本記事では、インクルーシブデザインの定義やユニバーサルデザインとの違いを整理し、国内外の実例10選や7つの基本原則を紹介します。違いを正しく理解したい方や自社のプロジェクトに導入を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
1.インクルーシブデザインとは?

インクルーシブデザインとは、障害者や高齢者、外国人など、これまでの一般的なデザインでは十分に配慮されてこなかった人々も含めて、誰もが利用しやすいように設計する考え方です。
従来の製品開発は「市場規模の大きい平均的なユーザー」に焦点を当てることが多く、結果としてマイノリティのニーズが置き去りにされがちでした。
一方でインクルーシブデザインは、あえて少数派の利用シーンに着目し、当事者の体験や声を出発点にデザインするのが特徴です。
1-1.インクルーシブデザイン誕生の歴史
インクルーシブデザインが提唱されたのは1994年、イギリス・ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(王立芸術大学院)において、当時名誉教授だったロジャー・コールマン氏によるものでした。
きっかけとなったのは、車椅子を利用する友人から依頼された自宅キッチンの設計です。コールマン氏は、車椅子でも使いやすいように高さや動線に配慮したデザインを提案しましたが、友人は「機能的であるだけでなく、誰もが羨むようなおしゃれなキッチンを望んでいた」のです。
この経験から彼は、機能性だけにとらわれず、当事者と同じ目線に立ち、心地よさや魅力も含めてデザインする重要性に気づきました。
コールマン氏は「健常者が気づかない、不便さを抱える人々のニーズにマッチしたデザインが重要」という考えを広めたのです。
この理念は「Inclusive Design(インクルーシブデザイン)」と呼ばれ、ヨーロッパを中心に世界各国に広がり、日本でも徐々に浸透していきました。
参照:インクルーシブデザインについて|株式会社ネクストソリューションズ
1-2.リードユーザーとは
リードユーザーとは、高齢者、障害者、外国人など、インクルーシブデザインのワークショップに参加する人たちを指します。
彼らは「少数派のユーザー」と思われがちですが、実は将来多くの人が直面するニーズをいち早く体験している存在です。
たとえば、年齢を重ねると誰もが視力や体力の低下を経験します。そのため、高齢者や障害者が感じる「不便さ」や「使いにくさ」に目を向けることで、将来的により多くの人に役立つ新しいアイデアを発見できるのです。
企業にとっても、リードユーザーは大切なパートナーです。彼らの声を取り入れることで、開発の段階から実際の利用シーンに合った商品やサービスを作れるので、結果としてヒット商品につながる可能性が高まります。
自分のニーズを正確に言葉で伝えられる人も多いため、従来のアンケートや調査では見えにくい深い洞察を得られる点も魅力です。
リードユーザーは完成した製品やサービスの熱心なファンになることも少なくありません。口コミやレビューを通じて周囲に広めてくれるため、自然なプロモーション効果も期待できます。
2.ユニバーサルデザインとの違い

インクルーシブデザインとよく比較される考え方に「ユニバーサルデザイン」があります。「誰も排除しない」という目的は共通していますが、成り立ちやアプローチに大きな違いがあります。
ユニバーサルデザインは、1970年代の「バリアフリー」思想の普及を背景に、1980年代にアメリカで広まりました。年齢、性別、国籍、能力にかかわらず、できるだけ多くの人が「使いやすい」を目指すデザイン手法です。
「ユニバーサル」には、「すべてに共通」という意味合いがあるため、あくまでも汎用的なデザインを取り入れることになります。
一方でインクルーシブデザインの場合は、高齢者や障害者、外国人など、これまでデザインから取り残されがちだった人々を企画や設計の初期段階から巻き込むのが特徴です。
インクルーシブデザインとユニバーサルデザインの違いをまとめた結果が、こちらです。
| インクルーシブデザイン | ユニバーサルデザイン | |
| ターゲット | 障害の有無や人種の違いなど特定の制約がある方 | すべての方 |
| デザインの特徴 | ターゲットの意見を最大限取り入れたデザインを採用 | 汎用性の高いデザインを採用 |
両者はアプローチの違いこそありますが、目指すゴールは同じです。
それは「誰も排除せず、すべての人が利用できる社会を実現すること」です。
参照:インクルーシブデザインが、誰ひとり取り残さないイノベーションを生み出す。|大和ハウス工業株式会社
3.インクルーシブデザインの実例10選
3-1.赤ちゃんから大人になっても使える椅子「TRIPP TRAPP」
一般的な椅子は、こども用と大人用に分かれており、サイズが合わないと快適に座れません。大人用の椅子を赤ちゃんが使うと危険ですし、こども用の椅子は成長とともにすぐに使えなくなってしまいます。
この課題に応えたのが、ノルウェーの家具メーカー・ストッケが発売する「TRIPP TRAPP」です。赤ちゃんから大人になるまで長く使える設計が特徴で、世界的に高い評価を得ています。
何歳になってもちょうど良いサイズで使用できるデザインは、快適さと優れた人間工学に基づいてデザインされています。
デザイナーのピーター・オプスヴィック氏は、2歳の息子がベビーチェアに合わず不便を感じていたことからヒントを得ました。
椅子の両側にあるL字型フレームには14段階の溝があり、座面や足を載せる板を自由に調整できます。この工夫により、成長に合わせて「ちょうど良い高さ」で座れるのです。
快適な椅子であれば、こどもがダイニングに長く座り、家族と食卓を囲む時間も増えるでしょう。
情緒や社会性を育む効果につながる点も、インクルーシブデザインの理念と一致しています。
さらに北欧らしいシンプルで洗練されたデザインは、機能性だけでなく「使いたい」と思わせる魅力も備えています。
参照:TrippTrapp Chair for lifeストッケのハイチェア「トリップ トラップ」人気の理由と購入のベストなタイミングは|ストッケジャパン
参照:TrippTrapp Chair for life|ストッケジャパン
3-2.シチズン「触って時間を知る時計」
時計メーカーのシチズンは、1918年の創業以来「すべての人に寄り添う時計づくり」を続けています。
その姿勢を象徴するのが、視覚障害者向けの腕時計の開発です。1960年代にはすでに国産初となる「触って時間を知る時計」を発売し、以来改良を重ねてきました。
最新モデル「AC2200-55E」では、インクルーシブデザインの考え方を随所に取り入れています。
開発段階では、タイのロッブリー県にある複合視覚障害者学校の教員や生徒の意見を反映し、進化を遂げました。
特にこだわったのは、いかにも「障害者向け」という印象を払拭したデザインです。シンプルでスタイリッシュな外観に仕上げることで、ファッションアイテムとしても自然に身に着けられるようになっています。
文字板に触れることで時間を確認できる機能性はもちろん、耐久性も向上し、日常生活でも長く使える時計です。
この取り組みは、「不便を補う道具」ではなく「誰もが使いたくなる製品」を目指すインクルーシブデザインの理念を表しています。
時計に関連して、視覚障害者に対して有効的な表現方法であるクロックポジションについて、こちらで詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
時計に関連して、視覚障害者に対して有効的な表現方法であるクロックポジションについて、こちらで詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
参照:【初心者向け】クロックポジションとは?事例交えて使い方を紹介!
3-3.NIKE「ゴー フライイーズ」
スポーツブランドのNIKEは、革新的な技術を取り入れた製品を数多く生み出してきました。代表例のひとつが、2021年に発表されたスニーカー「ゴー フライイーズ®︎」です。
従来のスニーカーは、靴ひもを結ぶ・屈んで履くといった動作が必要で、手や足の自由が利きにくい人にとっては大きなハードルでした。
ゴー フライイーズはこの課題に応えるため、開発の初期段階から障害のある人の意見を取り入れて設計されたのです。
最大の特徴は、「ハンズフリーで履ける仕組み」です。かかとで踏み込むとシューズのパーツが沈んでロックがかかり、手を使わずに簡単に着脱できます。
柔らかいクッション性のソールや、自然に前へ進みやすいロッカー構造など、歩行を快適にする工夫も斬新です。
カラーバリエーションも豊富に用意されており、機能性だけでなくファッション性の高さでも人気を集めています。
そのため、障害のある人だけでなく、妊娠中の方や子育て世代など「手を使わずに履ける便利さ」を求める幅広い層にも好評です。
誰でも簡単に履けるという理由で、手が不自由な障害者だけでなく妊婦や子育て世代の方にも高い人気を誇っています。
特定ユーザーの声を反映させることで、結果的に誰にとっても使いやすい製品につながるという、インクルーシブデザインの可能性を広げた商品といえるでしょう。
ゴー フライイーズ®︎については、こちらで詳しく解説しています。
参照:障害者の声が反映された靴、手を使わず履ける「ゴー フライイーズ®︎」とは?
3-4.TOTO「パブリックトイレ」
公共施設で採用されているTOTOの「パブリックトイレ」は、UD(ユニバーサルデザイン)を取り入れた例です。
従来の公共トイレは「車椅子使用者向け=バリアフリートイレ」というイメージが強く、結果、利用者が集中して混雑や使いにくさが生じる課題がありました。
さらに、オストメイトや乳幼児連れなど、利用者ごとに異なるニーズを十分にカバーできていないケースも見受けられました。
TOTOはこの課題に対し、誰もが快適に使える空間設計を実用化したのです。広めのブースを設けて車椅子利用者でもスムーズに移動できるようにしつつ、オストメイト対応の流しやおむつ交換台を配置するなど、幅広い利用シーンに応じられる設備を整えました。
単なる「バリアフリー対応」にとどまらず、利用者の状況や立場を問わず安心して使えるトイレ空間を実現している点が、TOTOのパブリックトイレの大きな特徴です。
トイレのバリアフリー化については、こちらでも詳しく紹介しています。
参照:【ホテルのトイレを攻略】自らの経験と知恵でトイレをバリアフリーにしよう
3-5.都立砧公園遊具広場「みんなのひろば」
東京都世田谷区の都立砧(きぬた)公園では、2020年3月にインクルーシブデザインを取り入れた遊具広場「みんなのひろば」がオープンしました。
「みんなのひろば」では、音や手触りといった感覚を活かした遊具を配置し、身体的な条件にかかわらず遊べる環境を整えています。
通路はゴムチップ舗装で安全性を高め、車椅子でもスムーズに移動可能です。園内には高さや広さが異なるベンチやテーブルを設置し、利用者の体格や状況に合わせて選べる工夫もなされています。
「みんなのひろば」の特徴は「配慮はしても区別はしない」という設計思想です。特定の人だけを対象とするのではなく、誰もが自然に混ざり合い、ともに遊ぶことを前提にした空間づくりが評価され、幅広い世代から注目を集めています。
3-6.服のお直しサービス「キヤスク」
おしゃれな服を見つけても、「体に合わず着られない!」。障害のある方にとって、この問題は日常的に起こりやすい課題です。
解決策として注目を集めているのが、株式会社コワードローブが展開する服のお直しサービス「キヤスク」です。
利用者一人ひとりの体型や動作の特性に合わせて衣服をリメイクし、「着たい服を自分らしく着る」を可能にしています。
キヤスクでは、オンラインでのヒアリングや写真のやり取りを通じて希望を共有し、完成後も到着した服を再度チェックして調整するなど、理想のスタイルを実現するための丁寧なサポートがされています。
取り組みは高く評価され、2022年度のグッドデザイン賞ベスト100とグッドフォーカス賞をダブル受賞しました。
「選択肢が限られていた」ファッションにおいて、誰もが自由に選び楽しめる社会づくりに貢献しているのです。
障害者向けのファッションブランドは、こちらで詳しく解説しています。
参照:障害の有無に限らずおしゃれを楽しみたい!みんなが着やすいファッションブランド7選!
3-7.マイクロソフト「Xbox Adaptive Controller」
マイクロソフトが2018年に発表した「Xbox Adaptive Controller」は、障害のあるゲーマーのために開発された特別なコントローラーです。
「ゲーミングはすべての人のもの」という理念のもと、インクルーシブデザインの手法を取り入れ、当事者からの意見を反映して作られました。
従来のゲームコントローラーは、障害のある人にとって操作が難しく、大きなバリアとなっていました。
そこで、外部のボタンやスイッチ、ジョイスティックを自由に接続できる仕様にし、利用者が自分の身体に合った操作方法をカスタマイズできるように設計されています。
また、梱包や開封の段階でもアクセシビリティに配慮され、ループ状の取っ掛かりを付けるなど、誰でも簡単に箱を開けられる工夫がされています。
「支援機器」ではなく「Xbox製品」としてのかっこよさにもこだわり、筋ジストロフィーや脊髄性筋萎縮症の当事者からも「再びゲームを楽しめるようになった」と高く評価されています。
参照:Xbox アダプティブ コントローラー|Microsoft
3-8.Google「Live Transcribe(音声文字変換アプリ)」
Googleがギャローデット大学と協力して開発した「Live Transcribe(音声文字変換アプリ)」は、話し言葉を即座に文字に変換できるAndroid向けの無料アプリです。
聴覚障害者が会話に参加しやすくなるように設計され、学生や旅行者、ジャーナリストなど幅広い利用者にも活用されています。
GoogleのAudio Setで分類された632種類の環境音データ の中から、音声文字変換では「風の音」や「犬の鳴き声」など60個の分類を採用しており、画面に「ノックの音」のようなアノテーション(注釈)が表示されるようになりました。
これにより、視覚で環境の音を示せば、耳が聞こえづらい人でも安心して会話が楽しめるようになります。
テキストはクラウドに保存されず、即座に削除されるためプライバシーにも配慮されているのがポイント。
ダークテーマでバッテリー消費を抑える機能や、多言語対応など、日常生活からビジネスまで幅広く役立つインクルーシブなツールです。
参照:“会話”をサポートする新しい 2 つのアプリ|Google Japan Blog
3-9.スターバックス「コミュニティストア・サイニングストア」
東京都国立市にある「スターバックスコーヒー nonowa国立店」は、日本初のサイニングストア(手話を共通言語とする店舗)です。
スタッフの半数以上が聴覚障害者で、手話や指差しボード、デジタルサイネージを活用して誰でもスムーズに注文できる仕組みが整えられています。
店内のデザインもインクルーシブを意識しており、「手話の動きを妨げない低いテーブル」「表情が見やすい照明」「角の丸い家具」などが採用されています。
ドリンク受け取りカウンターには番号表示と手話紹介のデジタルサイネージを設置し、来店したお客様が自然に手話に触れられる工夫も見逃せません。
「コミュニティストア・サイニングストア」は「耳の聞こえない人が自分たちで店を運営し、キャリアを築きたい」という声から誕生しました。結果として、障害の有無に関係なく「ここで働きたい」と応募する人が増え、スターバックス全体のダイバーシティ推進の象徴となっています。
参照:手話が共通言語となる国内初のスターバックス サイニングストアが東京・国立市にオープン|スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
3-10.パナソニック「歩行トレーニングロボット」
パナソニックが開発した「歩行トレーニングロボット」は、高齢者やリハビリ患者の歩行訓練を支援する機器です。
2018年の開発段階では機能重視で物足りないデザインでしたが、実証実験で「かっこ悪いから使いたくない」という声が上がり、当事者との対話を通じてデザインを一新しました。
スポーツジムの器具のようなスタイリッシュな外観に生まれ変わったのです。
結果、高齢者自身が積極的に使うようになり、2021年に商品化。IAUD国際デザイン賞金賞やグッドデザイン・ベスト100を受賞するなど高い評価を得ました。
単に「使える」だけではなく「使いたい」と思ってもらえることが、インクルーシブデザインにおいて重要であると教えてくれたのです。
もっと全国の取り組みを知りたいというあなたにおすすめの記事もあります。
4.インクルーシブデザイン7つの原則

作成者 alice_photo
4-1.同等の体験を提供する
インクルーシブデザインの基本原則のひとつは、利用する人の立場や状況にかかわらず「同じ体験を共有できること」です。情報やサービスの一部が特定の人にだけ制限されてしまうと、利用の格差が生まれてしまいます。
たとえば、視覚に障害がある人には画像の代替テキストや音声解説を提供し、聴覚に障害がある人には字幕や手話通訳を用意するなど、異なる方法であっても体験の本質は同じになるように設計します。
利用するすべての人に公平感と安心感を与えるデザインが必要です。
参照:インクルーシブデザインの原則|Inclusive Design Principles
4-2.状況を考慮する
人はいつも同じ環境や状態で商品やサービスを利用するわけではありません。明るい屋外でスマートフォンを操作する時もあれば、電車の中で片手しか使えないケースもあります。
インクルーシブデザインでは、そうした利用環境や体調・状況の違いを前提に設計することが重要です。
たとえば、コントラストの確保による屋外でも見やすいカラーリングの採用や、利用者の状況に即して内容が変化するヘルプ機能などがあります。
利用者の「状況を考慮する」工夫を重ねることで、誰もが場所やコンディションに左右されず、安心して同じサービス体験を得られるのです。
参照:インクルーシブデザインの原則|Inclusive Design Principles
4-3.一貫性を保つ
インクルーシブデザインでは、利用される方にとって馴染み深い慣例やパターンを一貫して適用することが求められます。
操作方法やレイアウトが場面ごとに変わってしまうと、混乱を招き、利用者にとっては大きな負担です。
そこでデザインガイドラインに従ったり、一貫したパターン・ページ構造を採用し、利用しやすいようにデザインする必要があります。
一貫性を持たせることは単なるデザイン上の美しさではなく、誰もが迷わず安心して使える体験を実現するための基本原則といえるでしょう。
参照:インクルーシブデザインの原則|Inclusive Design Principles
4-4.利用者に制御させる
インクルーシブデザインでは、利用する方が自ら制御できるデザインとしなければなりません。
自らがデザインした内容を押し付けるのではなく、利用者が自分好みにカスタマイズできる余地を残すことが重要です。
人によって「見やすい文字サイズ」や「心地よい色のコントラスト」は異なります。そのため、フォントサイズや表示方向、配色などを自由に変更できる機能を用意することで、誰もが自分に合った環境でサービスがを利用可能です。
また、予期せぬアニメーションや自動再生など、利用する方が望まないコンテンツの変化を避ける必要があります。
参照:インクルーシブデザインの原則|Inclusive Design Principles
4-5.選択肢を与える
インクルーシブデザインでは、複数の方法(選択肢)を用意するのが原則です。ひとつの手段しかなければ、使いにくい人にとって大きなハードルになってしまいます。
たとえば、フォームの送信では「Enterキーで送信」と「送信ボタンをクリック」の両方を用意する・。音声案内だけでなく文字情報も併記する・など、細やかな工夫によって、利用する人は自分に合った方法を選べるのです。
複数の選択肢を準備することで、視覚や聴覚に制約のある人や、一時的に手がふさがっている人など、さまざまな状況の利用者でもスムーズに操作でき、誰にとっても使いやすい環境を実現できます。
参照:インクルーシブデザインの原則|Inclusive Design Principles
4-6.コンテンツの優先順位を決める
インクルーシブデザインでは、ただ情報を並べるのではなく、利用者にとって重要な内容をわかりやすく整理して提供することが大切です。優先順位が曖昧だと、必要な情報にたどり着くまでに余計な負担がかかってしまいます。
たとえば、FAQ(よくある質問)のページでアコーディオン形式を採用すれば、利用者は見たい質問だけをすぐに開いて確認できます。また、メールアプリなら「新規作成」ボタンを画面の目立つ位置に配置することで、利用頻度が高い操作を迷わず実行できるでしょう。
コンテンツの優先度を整理することで、情報が探しやすく、操作が直感的にできる環境を実現できます。結果として、利用者全体のストレスを軽減し、すべての人にとって快適な体験につながるのです。
参照:インクルーシブデザインの原則|Inclusive Design Principles
4-7.付加価値をつける
最後の原則は、利用者にとって「便利さや安心感をプラスすること」です。基本的な機能を満たすだけではなく、「あると助かる」工夫を盛り込むことで、使いやすさが一段と高まります。
たとえば、スマートフォンのマイクやカメラ、バイブレーション、位置情報(ジオロケーション)といった機能を活用すれば、日常生活をより快適にサポート可能です。
付加価値を意識したデザインは、単に「使える」だけでなく、「使いやすくて安心できる」と感じられます。
参照:インクルーシブデザインの原則|Inclusive Design Principles
5.インクルーシブデザインを推進すればいいというものではない
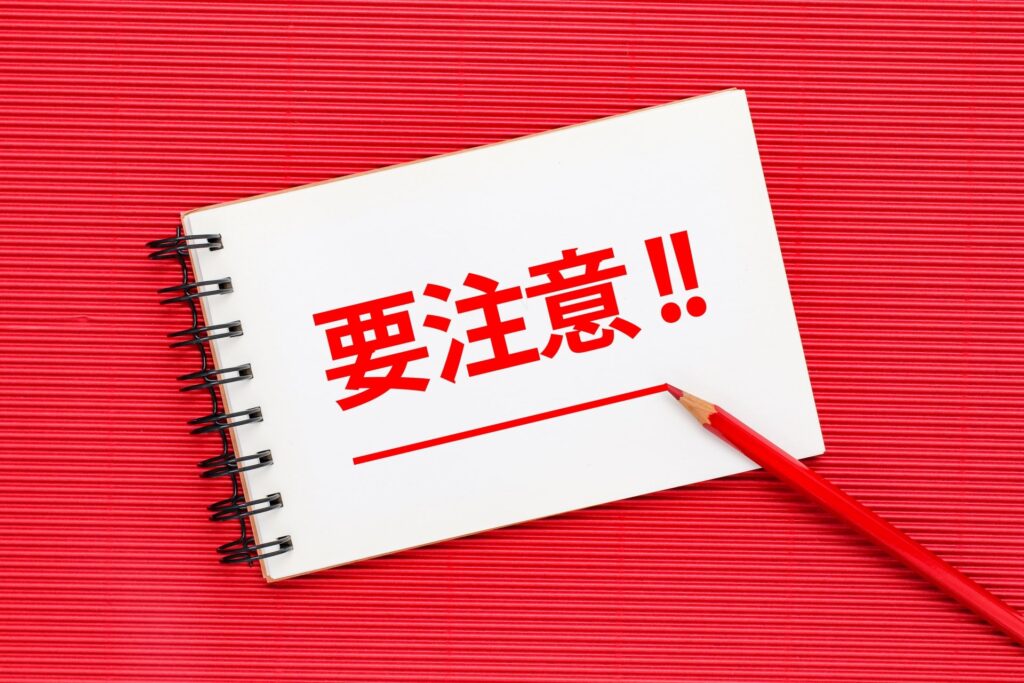
インクルーシブデザインは、さまざまな利用者の声を取り入れることで革新的なアイデアを生み出しやすく、社会に大きな価値をもたらします。しかし「やればやるほど良い」という単純な構図ではなく、いくつかの注意点や限界も存在します。
・調整コストと目的のずれ
リードユーザーの意見を取り入れることは重要ですが、必ずしも全員の声を等しく反映できるわけではありません。
障害の種類や程度、文化的背景によってニーズは大きく異なり、無理に統合しようとすると本来のプロジェクト目的が見失われる恐れがあります。
適切な調整には多くの時間と労力が必要であり、成果物の方向性を見誤らない冷静な判断が求められます。
・デザイナーの力量と役割
リードユーザーの声をそのまま形にするのではなく、製品やサービスに落とし込むためには高い力量が必要です。
デザイナーは単なる設計者ではなく、異なる背景を持つユーザー同士の「通訳」や「ファシリテーター」として機能しなければなりません。
多様な意見を尊重しつつ、全体の調和を取る役割を担うため、専門性とコミュニケーション能力が不可欠です。
・コストとリスク
新たなデザイン手法を導入するには、デザイナーの育成やユーザー参加の仕組みづくり、場合によっては専用設備の導入など、多大な費用が発生します。
小さな検証をせずにいきなり大規模投資に踏み切ると、失敗した際のダメージも大きくなります。
インクルーシブデザインは「段階的に検証しながら進めること」が成功のポイントです。
・よくある落とし穴
インクルーシブデザインの現場では、「当事者から一度意見を聞けば十分」という誤解が生まれがちです。
本来、ヒアリングはゴールではなくスタートに過ぎません。継続的に当事者と協働し、知見を深めなければよいサービスの提供は難しいでしょう。
ユーザー視点とビジネス視点の両立ができていないと、単なる理想論に終わる危険性もあります。
・対等性を前提とした取り組み
最後に強調すべきは、インクルーシブデザインは「障害」を特別扱いするのではなく、物理的・認知的・感覚的な違いを起点に課題を発見するプロセスであるという点です。
当事者を尊重しつつも、必要以上に重くとらえず、あくまで「対等な立場」でともに考える姿勢が大切です。
6.最後に
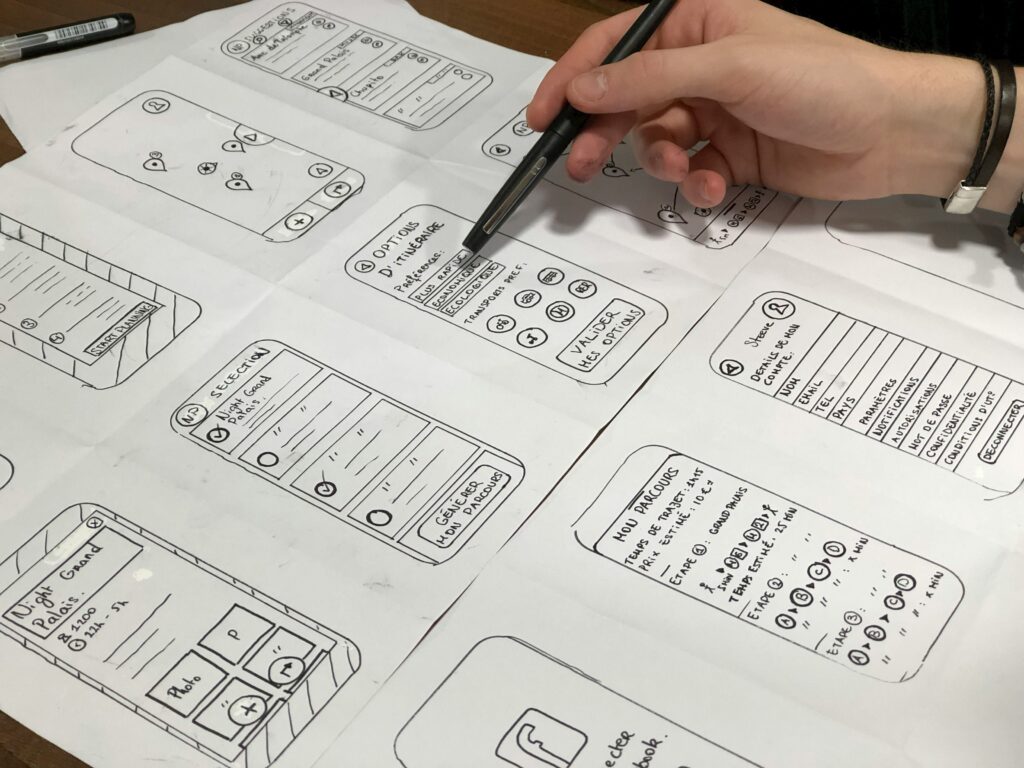
インクルーシブデザインは、従来の開発プロセスでは取りこぼされがちだった障害者や高齢者の声を積極的に取り入れる点が大きな特徴です。その結果、特定の人だけでなく、誰にとっても便利で安心して使える商品やサービスが数多く生まれています。
今回ご紹介した実例からもわかるように、インクルーシブデザインは「特別な人のためのもの」ではなく、私たちの日常を豊かにする考え方です。ビジネスやサービスに取り入れれば、新しい発想や市場の拡大にもつながります。
ぜひ本記事で紹介した原則や事例を参考に、身近な場面でインクルーシブデザインの視点を活用してみてください。