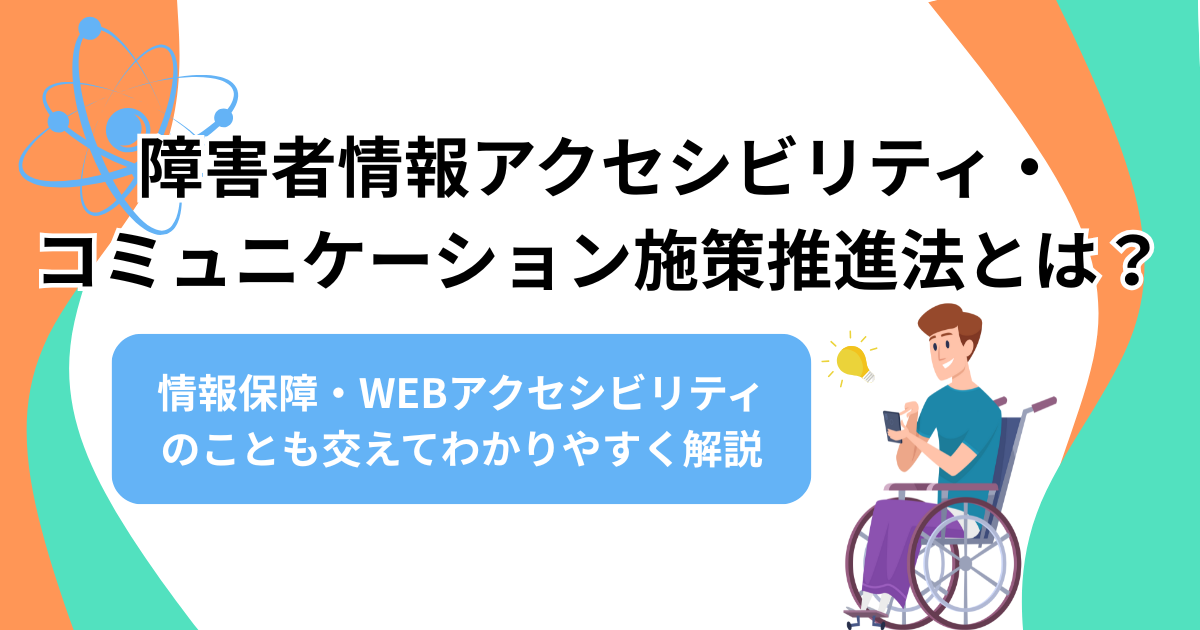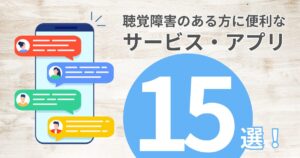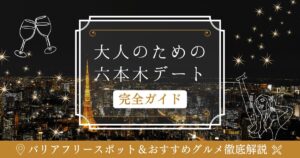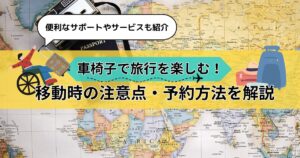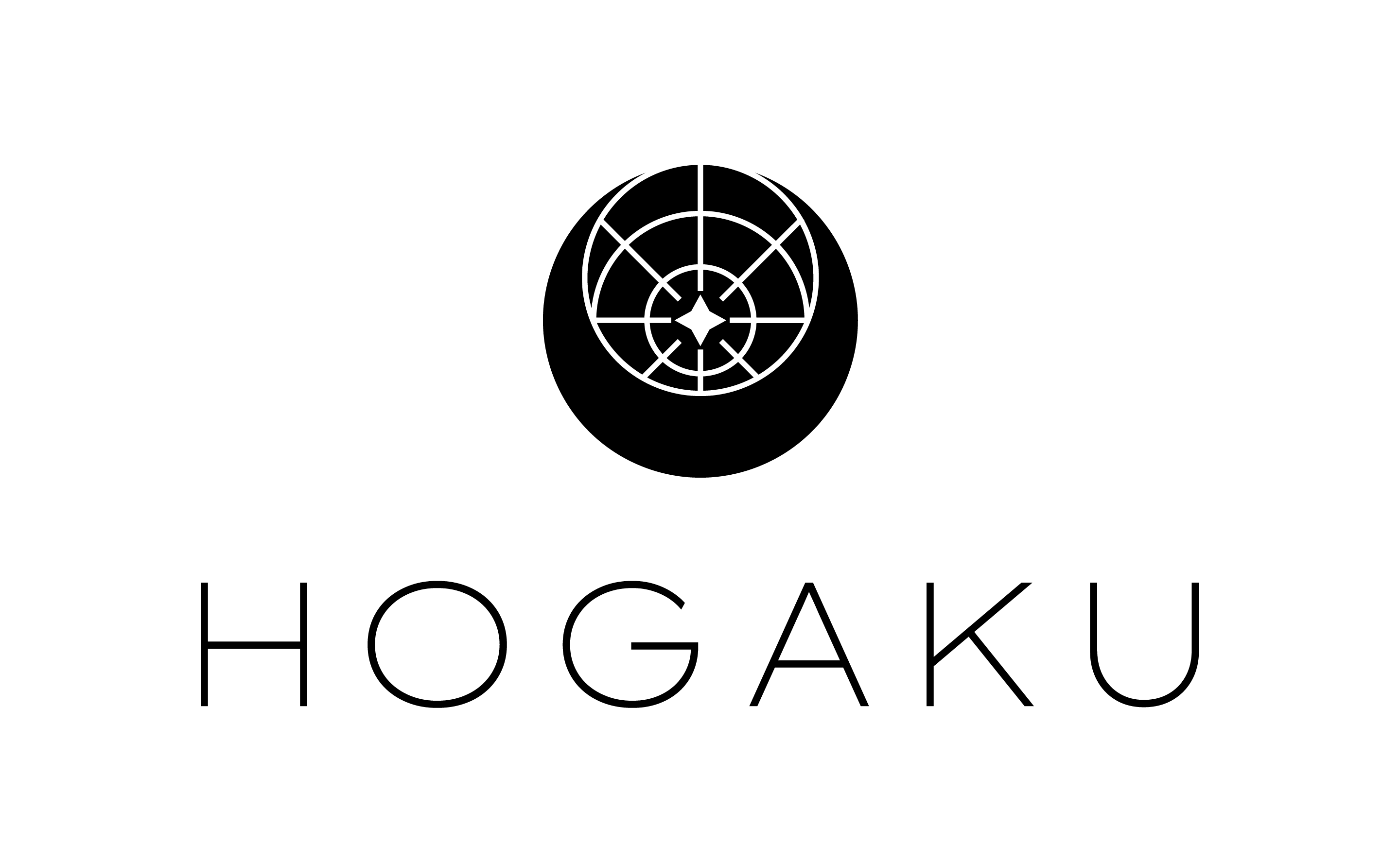「障害のある方にもきちんと情報が届く社会にしたい」
そのような思いから生まれたのが「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」です。
しかし「一体どのような法律なのか?」「どのようなことを対策として取り入れればよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、法律のポイントをやさしく解説しながら、ウェブアクセシビリティへの取り組み方を紹介します。情報保障やウェブアクセシビリティの基本を理解し、すべての人にとってより良い社会への一歩を踏み出しましょう。
目次
1.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法とは?

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法は、障害のある方が情報を取得し、円滑に意思疎通を図れるようにすることを目的として、2022年に施行された法律です。
参議院厚生労働委員会で審議された「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法案(正式名称「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」)の基本理念を、以下にまとめました。
| 基本理念 | デジタル社会においても、すべての障害者が情報通信技術を活用して必要な情報を取得・利用し、意思疎通できるようにすること |
| 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする | |
| 障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする | |
| 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会) |
これら4つの基本理念からわかる通り、国全体が、視覚や聴覚など障害の種類にかかわらず、誰もが必要な情報にアクセスできる社会の実現を目指しています。
企業がこの法律に基づいた対応を進めることは、社会的責任を果たすだけでなく、より多くの人にサービスを届ける大きな機会となるはずです。情報のバリアフリー化を進める第一歩として、まずはこの法律の趣旨をしっかり理解しましょう。
2.制定の背景と経緯
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が制定された背景には「障害者の情報格差」が大きな理由として挙げられます。
急速な情報社会の進展により、行政手続きやサービス提供、災害時の情報発信のデジタル化などが大きく発展してきました。しかし「必要な情報にアクセスしづらい」「コミュニケーションが円滑に進まない」といった「情報格差」が深刻な社会問題となっています。
視覚、聴覚、知的、発達など障害の種類や程度によって、求められる支援手段は多岐にわたります。しかし、従来の制度や取り組みでは画一的な対応にとどまり、障害の特性に応じたきめ細かな情報提供が十分に行われていないのが現実です。特に「災害時に避難情報が伝わらない」「緊急通報ができない」といった事例は、命や生活に直結する大きな課題といえるでしょう。
このような状況を踏まえ、情報取得や意思疎通に関する支援を体系的に進める法整備が行われたというのが、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法制定の経緯です。企業にとっても、この法律は重要な指針となります。単に法令遵守の観点だけでなく、多様な人々に向けてサービスを届けるために、ウェブアクセシビリティの確保や合理的配慮の強化が求められています。合理的配慮について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
3.法律の概要をわかりやすくまとめました

3-1.抱えている障害や病気によって求められる対応が変わります
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法では、障害や病気の種類・程度に応じた適切な情報提供と意思疎通の手段が求められています。企業が情報保障・ウェブアクセシビリティを考える際には「一律の対応」ではなく「個々のニーズに合った支援」が鍵となるでしょう。以下に、障害別の具体的な対応ポイントをまとめました。
| 障害の種類 | 対応ポイント |
| 視覚障害 | 音声読み上げ対応のウェブ設計(スクリーンリーダー対応)代替テキスト(altテキスト)の正確な記述点字資料の提供や拡大文字の使用 |
| 聴覚障害 | 動画・音声コンテンツへの字幕付与手話・要約筆記の導入チャットやメールなど文字ベースの問い合わせ手段の整備 |
| 肢体不自由 | キーボード操作や音声入力への対応マウスを使わずに操作できるナビゲーションの提供シンプルな画面構成と適切なタップ領域の確保(スマートフォン対応) |
| 知的・発達・精神障害 | 難解な専門用語を避けた、やさしい日本語での情報提供図やイラストを活用した視覚的な説明情報量を整理し、段階的に提示する工夫 |
| 内部障害・高次脳機能障害 | 集中力・記憶力に配慮した操作設計(簡潔な導線、入力補助)長時間の閲覧を前提としないレイアウトユーザーのペースで操作できるシステム構成 |
企業がこれらの視点をもってアクセシビリティに取り組むことは、単に法令に対応するだけではなく、すべての人が生きやすくなる社会への第一歩です。
情報が正しく届き、自分の意思が伝えられる環境は、障害のある方にとって自立や社会参加を後押しする大きな力となります。そしてその姿勢は、企業にとっても「誰にでも届くサービス」という新たな価値を生み出し、多様なユーザーとの信頼関係を築く大きなチャンスとなるでしょう。
3-2.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の事例を紹介
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の理念を実践している企業の一つが、神奈川県小田原市に本社を構える株式会社リンクラインです。
リンクラインは、障害者雇用を促進する「特例子会社」として、石けんの製造・販売を中心に事業を展開しています。特徴的なのは、事業を福祉的な枠組みにとどめず、高品質な商品を生み出す民間企業としてしっかりと機能している点です。自社ブランド「liilii(リィリィ)」Ⓡは、全国の雑貨店で取り扱われ、見た目のかわいらしさと肌へのやさしさで多くの支持を得ています。
リンクラインの取り組みは、法律の理念を具体的な形で実現した好事例といえるでしょう。情報保障や合理的配慮のあり方を模索する企業にとって、多くのヒントと学びを与えてくれる存在です。
参照:株式会社リンクライン
4.2024年から重要性が増してきたウェブアクセシビリティのポイントも解説!
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行により、情報への公平なアクセス環境の整備が企業にも求められるようになりました。これに伴い、近年ではウェブアクセシビリティの重要性がこれまで以上に高まっています。
特に注目されているのが「誰もがストレスなく情報を受け取れるウェブサイト設計」です。
例えば、視覚障害のある方には音声読み上げに対応した構造や、代替テキストの適切な記述が必要です。聴覚障害のある方に対しては、動画コンテンツへの字幕付与が欠かせません。さらに、知的障害や発達障害のある方には、やさしい日本語や図解を用いた説明が効果的です。こうした多様なニーズに応えることで、すべての人に開かれたウェブサイトを実現できます。
今後は法的な側面だけでなく、企業の信頼やブランド価値にも関わる要素として、アクセシビリティへの取り組みが問われるでしょう。ウェブアクセシビリティについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
参照:ウェブアクセシビリティとは?メリットや取り組み事例含めてわかりやすく解説!
5.まとめ
障害の有無にかかわらず、すべての人が正しい情報にアクセスできる社会をつくるためには、企業によるウェブアクセシビリティの理解と実践が欠かせません。近年では法律の整備も進み、企業にも具体的な対応が求められています。
ウェブアクセシビリティ対策は、単なる技術対応ではなく「合理的配慮」の一環としての重要な取り組みです。そのため、対応を進める企業の多くが、社内の意識向上や体制づくりに課題を抱えているのではないでしょうか。
Ayumiでは、障害者支援の現場から生まれた知見を活かし、無料相談を受け付けています。実践的に学べるワークショップの開催も行っており、企業ごとの課題に合わせた柔軟なサポートが可能です。
どんな小さな疑問でも構いません。「企業がこれからやるべきことって何だろう」と疑問に思ったときは、お気軽にAyumiまでお問い合わせください。未来の共生社会は、その小さな一歩から始まります。