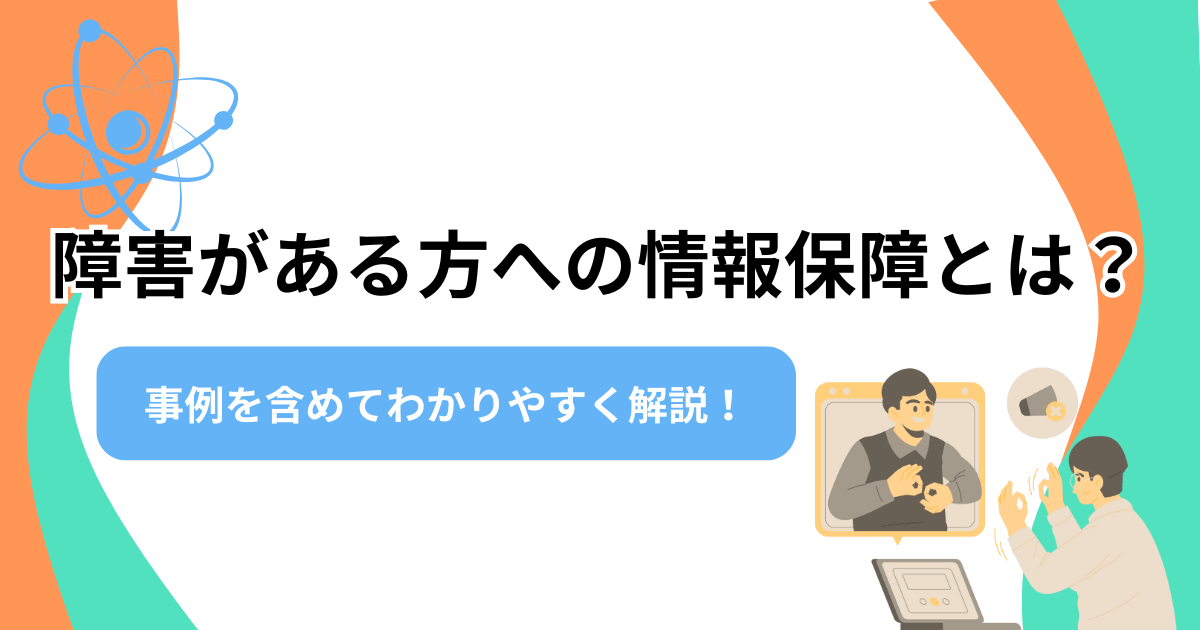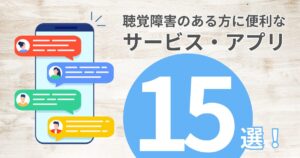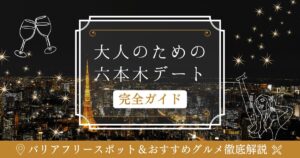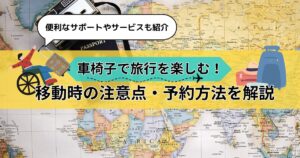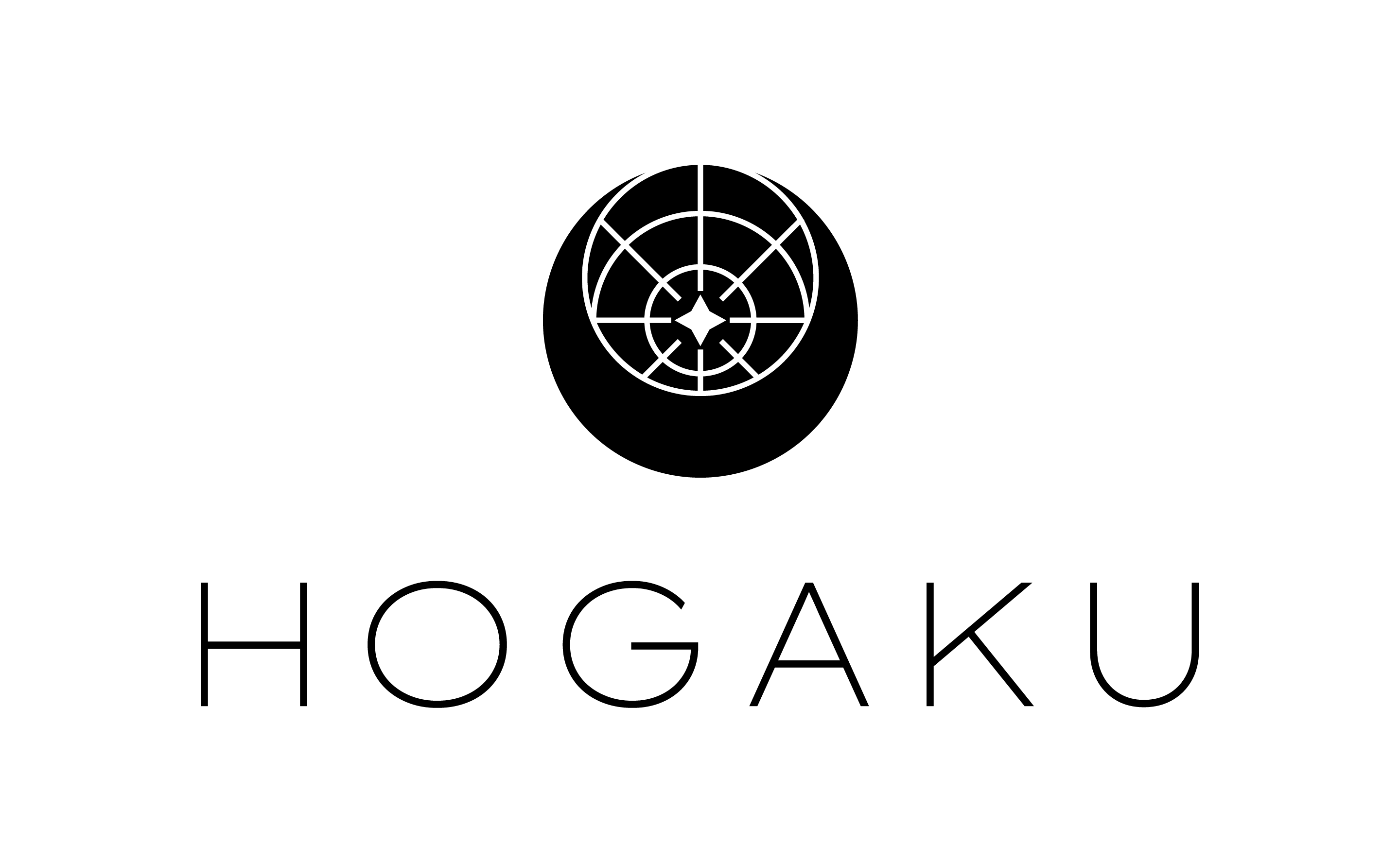「障害のある方にも、正しい情報が届くようにしたい」
そのような思いをさらに具体化するのが「情報保障」の考え方です。
これまで合理的配慮に取り組んできた企業であっても「情報保障とは何か」「どのような配慮が求められるのか」と戸惑うことがあるのではないでしょうか。実際、障害の種類や状況によって、必要な支援方法は大きく異なります。
本記事では、情報保障の基本的な考え方を整理しながら、聴覚障害・視覚障害など、それぞれの特性に応じた対応ポイントを具体的に紹介します。
より多様な人が安心して働き、活躍できるように、情報保障の視点を取り入れた職場環境づくりを目指しましょう。
目次
1.情報保障とは?

情報保障とは、障害のある方が必要な情報に平等にアクセスし、理解し、活用できるよう支援する取り組みのことです。
例えば、視覚障害のある方には音声読み上げ対応の資料を、聴覚障害のある方には字幕や手話通訳を提供するなど、障害の特性に応じて情報の伝え方を工夫することが求められます。また、知的障害や発達障害のある方には、やさしい日本語や図解を使った説明も有効です。
情報保障は単なる情報提供にとどまらず「伝わること」「理解できること」をゴールとしています。情報保障の視点を取り入れることは、誰もが安心して生活できる環境をつくるために、企業にとってますます重要になっていくでしょう。
2.聴覚障害者向けの情報保障とは?
聴覚障害のある方に対する情報保障とは「音声情報が届かない」という障壁を取り除き、正確に情報を受け取れるよう支援する取り組みのことです。具体的な例として、以下のような対策が挙げられます。
- 会議や研修において手話通訳や要約筆記を用意する
- 動画コンテンツに字幕を付与する
- メールやチャットなど文字による情報伝達手段を整備する
ポイントは、単に情報を「提供する」だけでなく、タイムリーかつ正確に伝えることです。たとえば緊急連絡の際は、音声だけに頼らず、即時にテキスト情報を配信できる仕組みを備えておくことが大切でしょう。
3.視覚障害者への情報保障とは?
視覚障害のある方への情報保障とは、見えない・見えにくいことによる情報格差をなくし、必要な情報にアクセスできる環境を整える取り組みのことです。具体的な例として、以下のような対策が挙げられます。
- 音声読み上げに対応したデジタル資料を活用する
- 書類や資料を提供する際、点字版や拡大文字版を用意する
視覚障害者への情報保障において大切なことは、視覚に頼らない形で正確に伝える手段を選ぶことです。例えば社内会議では、資料を事前にデータで共有し、読み上げソフトでも問題なく理解できるよう配慮するといった対策が有効でしょう。
4.緊急時・有事の時に備えて対策したい配慮
緊急時や災害時に命を守るためには、迅速かつ確実に情報を伝えることが欠かせません。障害者を雇用する企業においては、事前にしっかり対策しておく必要があります。
例えば、問い合わせ先には電話だけでなく、メールやFAXでも連絡できる窓口を明記することが重要です。また、緊急時には言葉だけでなく、イラストやピクトグラムを指で指し示すことで、直感的に情報を伝える工夫も効果的です。
聴覚障害者への配慮としては、手話通訳やリアルタイム字幕を用意したり、必要に応じて通訳者を手配したりといった体制づくりが求められます。さらに、口元の動きを読む必要がある方に配慮して、マスクを外し、表情が見える状態でコミュニケーションを取ることも大切です。
万が一の場面でも誰一人取り残さないために、日頃から多様な配慮を備えておきましょう。
5.全国で対応されている情報保障の事例を紹介します!
ここでは、具体的な例として情報保障の取り組み事例を紹介します。
東京都では、障害のある方も安心してイベントや会議に参加できるよう、情報保障の取り組みを強化しています。視覚障害や聴覚障害のある方への具体的な取り組み例は、以下の通りです。
- 点字資料や拡大文字、音声データを提供する
- 手話通訳や要約筆記を提供する
他にも、知的・発達・精神障害のある方には、振り仮名やイラスト付きの案内板を使い、理解しやすい情報提供を工夫しています。受付や席配置にも配慮し、車椅子使用者への対応や、手話通訳者が見やすい座席確保など、細やかな調整が行われているようです。
さらに緊急時には、障害の特性に応じた伝達手段を用いた、迅速な避難誘導を実施しています。こうした東京都の取り組みは、情報保障を考えるうえで大いに参考になるでしょう。自社の対策をブラッシュアップするヒントにしてみてください。
参照:障がいのある人に対する 情報保障のためのガイドライン|東京都大田区役所障害福祉課
6.情報保障(情報バリアフリー)とWEBアクセシビリティの違い

情報保障(情報バリアフリー)とWEBアクセシビリティは、どちらも「誰もが平等に情報へアクセスできる環境づくり」を目指す取り組みですが、対象範囲に違いがあります。
情報保障は、あらゆる場面で障害のある方が情報を受け取り、理解し、意思疎通できるよう支援する考え方です。例えば、会議での手話通訳やイベント案内への点字添付、緊急時にFAXでの連絡体制を整えるなど、デジタル・アナログを問わず幅広い手段が含まれます。
一方でWEBアクセシビリティは、WEBサイトやアプリケーションといったデジタル領域に特化し、視覚・聴覚・身体的制約の有無にかかわらず誰もが操作しやすい設計を指します。音声読み上げ対応や代替テキスト、字幕対応などが主な対策です。
企業にとっては、両方を意識しながら、リアルとデジタルの両面で障害を取り除く視点が求められます。
WEBアクセシビリティについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
参照:参照:ウェブアクセシビリティとは?メリットや取り組み事例含めてわかりやすく解説!
7.まとめ
障害の有無にかかわらず、すべての人が正しく情報を受け取り、意思疎通できる社会をつくるためには、企業による情報保障への理解と実践が欠かせません。合理的配慮を理解したその先に、情報保障をどう実現していくかが重要なテーマとなります。
情報保障は単なる対応策ではなく、一人ひとりが尊重される職場づくりの基盤です。しかし実践には、社内の意識醸成や仕組みづくりといった新たな課題も見えてくるでしょう。
Ayumiでは、障害者支援の現場で積み重ねてきた経験をもとに、無料でのご相談を受け付けています。また、実際に手を動かしながら学べる実践型ワークショップもご用意しています。貴社のペースや課題に寄り添ったサポートを大切にしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
情報保障に取り組みたいと感じた今が、その第一歩です。貴社に合ったかたちで情報保障への一歩を踏み出しましょう。
Ayumiへのお問い合わせはこちら
参照:お問合せ
Ayumiが開催する合理的配慮のワークショップの概要はこちら