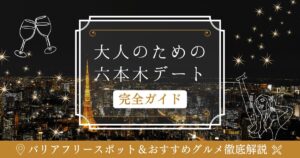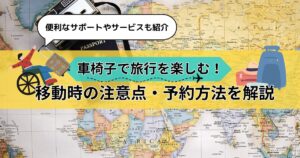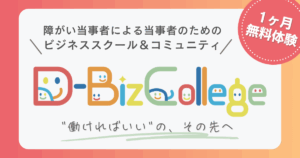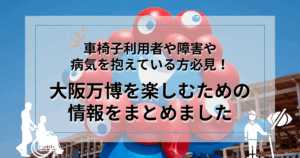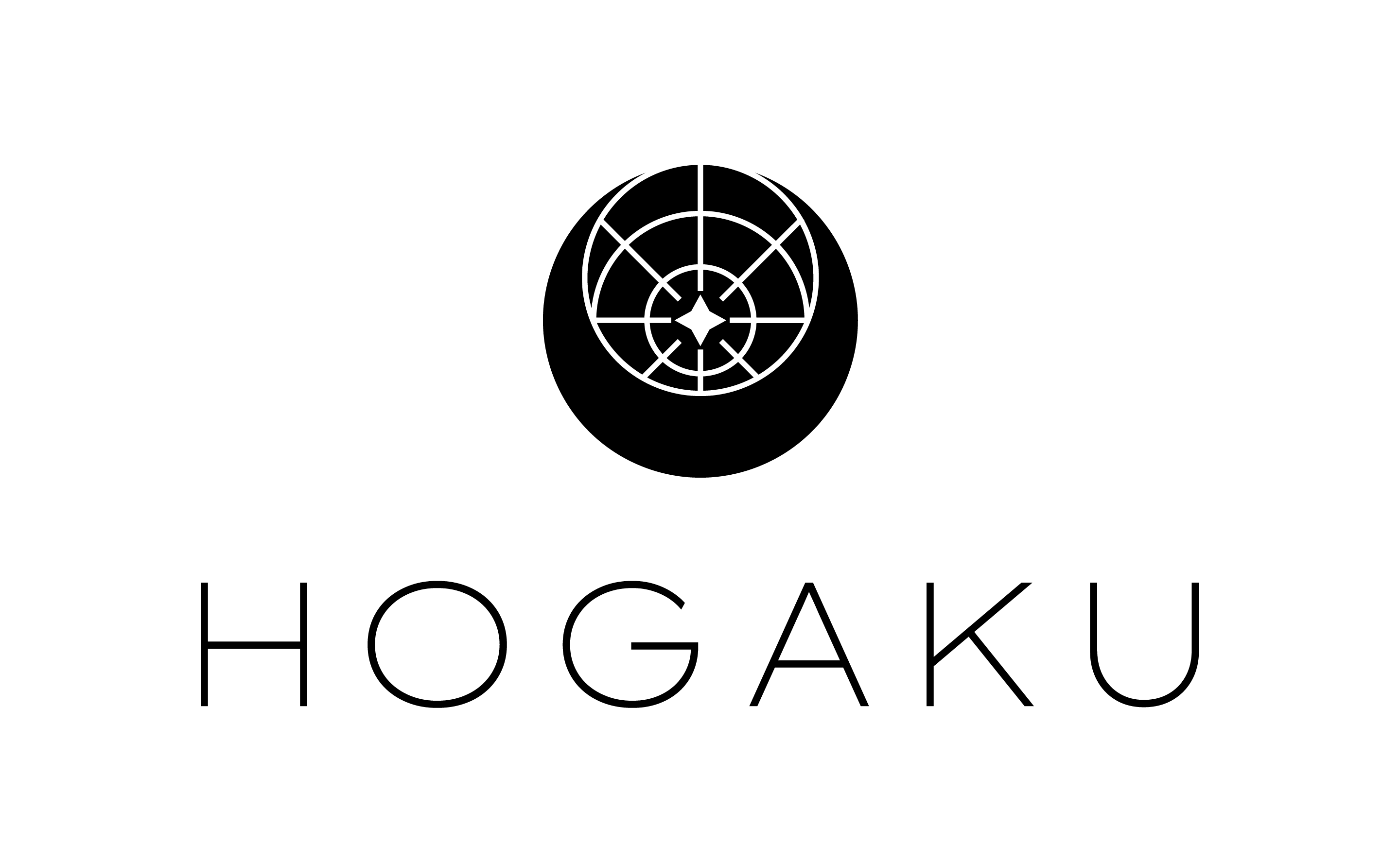子どもが入院したら、親も泊まり込みで付き添いをしなければならないということを知っていますか?
入院することが多い病児や障害児のいるご家族の間では、「付き添い入院」と呼ばれており大きな問題になっています。
今「問題」と書きましたが、なぜ付き添うことが問題なのでしょうか。
その理由は、付き添い入院をする際の親の環境が非常に過酷であるためです。
今回の記事では問題になっているその環境について、そして付き添い入院をしているご家族がどう乗り越えているのかということを、付き添い入院を何度も経験した筆者が紹介していきます。
目次
1. 子どもの付き添い入院問題とは?
子どもの入院の際に親は付き添いをほぼ強制的に求められますが、親の自由や快適性は考慮されていないことが、付き添い入院問題の根幹を成しています。
参照:ただ、耐えるしかなかった…病気の息子に付き添う日々の中で|NHK
親の自由は、全くと言っていいほどありません。SNS等では「人権がない」といった表現も見られるほどです。
1-1. 付き添い入院が作り出す親の「軟禁状態」
子どもが入院したら、まず親は基本的に、その病室から離れることができません。
これは、子どもを病室で1人にすると、何が起きるかわからないからです。
ベッドの柵を乗り越えて転落したり、点滴を抜いてしまったりすることも考えられます。
さらに、いつ体調が急変するかも分かりません。
障害児の場合、体調が悪くなってもナースコールが押せないケースも考えられます。
そんな中で、子どものそばを離れることができるでしょうか。
親は文字通り、付きっきりで看護しなければならず、親の「軟禁状態」が生まれます。
トイレに行く時でさえ、子どもの調子やタイミングを見て行くのです。
食事の買い出しやシャワーなど、生活に必要な行動すら、自由にすることができません。
子どもがお昼寝をしている時や、体調や機嫌が安定している時を見計らって、急いで行きます。
病室を離れても子どもの状態が常に気になって、気が休まることはありません。
1-2. 満足に摂れない食事
親は、食事も満足に摂れないことも多いです。
子どもには病院食が出ますが、親の分はありません。付き添い入院を経験した多くの方が、院内のコンビニで済ませているようです。
参照:独自調査【子どもの入院への付き添いに関するアンケート】結果のご報告|特定非営利活動法人 キープ・ママ・スマイリング
ほぼ毎日コンビニのおにぎりやパン、お弁当ばかり食べていると、当然栄養のバランスは崩れます。
それが原因で、体調を崩す方もいるでしょう。
体力もどんどん消耗していきますし、食べるものが満足に選べないことで、気力まで失われていくこともあります
先述のように、買い出しに行くことも難しいため、食事を抜くことも少なくないです。
買い物に行く機会を失うと、持ち込んでいた日持ちのするお菓子やレトルト、インスタント食品などでしのぐ方もいらっしゃいます。
1-3. 劣悪な睡眠環境
寝る時は、子どもと一緒に小児用ベッドで寝ます。
簡易ベッドが用意されている病院もありますが、共通しているのは、寝返りさえ打てない狭い寝床であることです。
体型によっては、足も伸ばせない方もいるでしょう。
ベッドがきしむ音で子どもが起きないか気を配ったり、モニターの光が眠りを妨げたり、夜間巡回に来る看護師さんのライトで起きてしまったりして、ゆっくり眠ることも難しいです。
1-4. まだある付き添い入院の問題点
他にも、シャワーを使う時間が限られていたり、予約制のため予約が取れないと使えない日もあったり、衛生面でも大変なことがたくさんあります。
親の食事やコインランドリー、冷蔵庫、テレビなどの費用がかさむうえ、付き添い入院をしながら働くのは難しいため経済的な不安も出てきます。
長期になればなるほど、親に負担がかかっていくのです。
さらに、コロナ禍によって状況は悪化しました。
たとえば、付き添い者の交代や付き添い者以外の面会が禁止されるといった制限が生じ、それまで以上に大変な生活になりました。
これが、付き添い入院問題の実態です。それでも付き添いを拒否することは現状難しいので、なんとか乗り切るしかありません。
2. 付き添い入院の問題をどう乗り越えるか?
2-1. 付き添い入院に向けて事前に確認したいこと

今ある問題のすべてを解決することは残念ながらできませんが、準備次第で多少快適さを上げることはできます。
まずは、病院の設備やルール、どんなサポートがあるかを把握しておくといいと思います。
病院によって、用意されている設備やルールが違いますので、あらかじめ聞けるようであれば以下について確認しておくと、荷物の準備をする際の過不足を防止できます。
・貸し出しや備品として用意してあるものはあるか(ドライヤー、電気ケトルなど)
・シャワーはいつ使えるのか、使用時間や頻度、ルールはどうか
・付き添い者の交代は可能か
・面会はどこまで可能か(親族のみ、友人も可など)
・差し入れが受けられるか
また、付き添い入院についてのブログや記事を見て、実際の生活をイメージすることも準備に役立ちます。
2-2.付き添い入院に必要な持ち物
実際に付き添い入院を経験された先輩たちが、どのように乗り越えているかについてもご紹介しましょう。
『つきそい応援団』というサイトでは、付き添い入院経験者たちが投稿した口コミを見ることができます。
参照:つきそい応援団|特定非営利活動法人 キープ・ママ・スマイリング
その中に、付き添い入院中「あると便利なもの」を投稿するスレッドがありましたので、その中から一部抜粋します。
・延長コード
・マットレス
・スキンケア用品
・折りたたみハンガー、洗濯ネットなどの洗濯グッズ
・インスタント、缶詰など日持ちする食料品
・ポケットWi-Fi、タブレットなど楽しく過ごすためのもの
キャンプ用品や百均グッズを活用するアイデアは数多く投稿されており、私も読みながら「なるほど」と思うものもありました。
詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
参照:入院付き添いするにあたって「あると便利なもの」を教えてください!|つきそい応援団
3. 付き添い入院に保険は適用される?
付き添い入院をおこなう場合、想像以上に多くの費用を負担しなければなりません。
そこで、保険を適用することができれば自己負担額を減らすことが可能です。
付き添い入院で発生する費用については、入院する子ども名義で医療保険に加入している場合は、保険が適用されます。
ただし、親名義で医療保険に入っている場合は、付き添い入院の際に医療保険が適用されないため注意が必要です。
子どもの入院期間が長くなると、自己負担額が増えてしまいがちです。
また、付き添いのために仕事を休む場合、収入が減ってしまうことになります。
そのため、共済や民間の医療保険に、子ども名義で加入することを検討しておくのもおすすめです。
4. 付き添い入院が必要な子どもの家族を支援する団体を紹介!

この『つきそい応援団』を運営している特定非営利活動法人キープ・ママ・スマイリングでは、子どもの付き添い入院を支援する取り組みも行っています。
その一つが、「付き添い生活応援パック」です。
参照:【22年4月より対象拡大】お子さんの長期入院に泊まり込みで付き添うご家族に「付き添い生活応援パック」を無料でお届けします!|特定非営利活動法人 キープ・ママ・スマイリング
2週間以上の入院が見込まれている方を対象に、食品、生活・衛生用品の詰め合わせを無料で配布しています。
さらに、プロの料理人と管理栄養士が作る料理をふるまう「ミールdeスマイリング」という活動をされていたり、付き添い入院の実態を定期的に調査し公表、提言を行ったりもしています。
最近では、厚生労働省が行なった付き添い入院実態調査が回答率1.4%に終わったことを受け、付き添い入院経験者からの不満をいち早くキャッチし、独自に調査を実施していました。
付き添い入院経験者から集まったアンケート総数は、なんと3,600件以上もあり、この問題への関心の高さを感じますね。
5. まとめ
我が子が病気や怪我で入院し、治療する姿を見るのはそれだけで辛いものです。
痛い、苦しい治療も中にはありますから、それをそばで支える親にも少なからず負担がかかるでしょう。
それに加えて、過ごす環境が過酷で、疲れも取れないという状況で、心身ともに追い込まれてしまうのが付き添い入院問題の深刻なところです。
付き添い入院は書面上「親の希望」ということになっていますが、実態はほぼ強制のような形になっており、すぐに解消するのは現状難しいようです。
参照:「心を病む」過酷な子どもの付き添い入院、親の声はなぜ国に届かないのか 厚労省の実態調査は回答率わずか1%で終了?支援いまだ進まず|47NEWS
今は自助努力で少しでも快適に過ごす方法を模索するしかありませんが、サポート団体やご家族、病院スタッフなどの力も借りて、何とか、退院に向けて乗り越えましょう。
孤独感を覚えた時には、SNSで「#付き添い入院」と検索してみてください。今も付き添い入院をされている方が他にもいると分かるだけでも、心が軽くなるかもしれません。
Ayumiでは、障害児・医療的ケア児を抱える親御さんのコミニュティについて以下の記事で紹介しているのでぜひご覧ください。