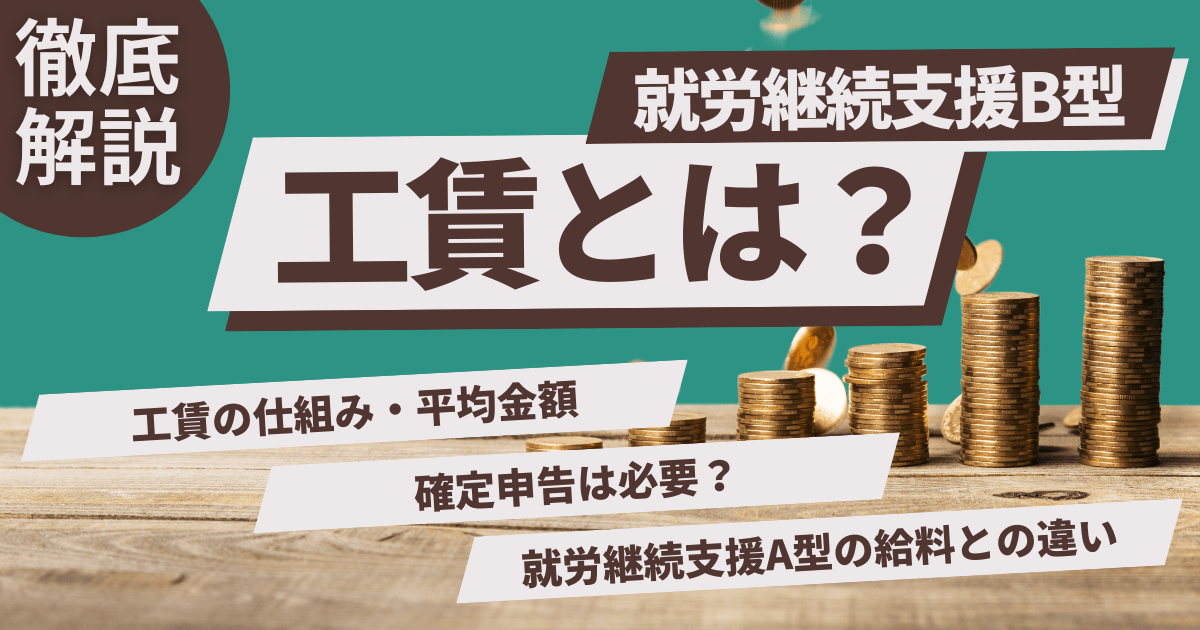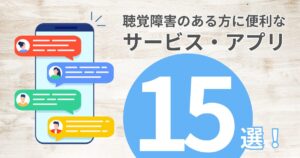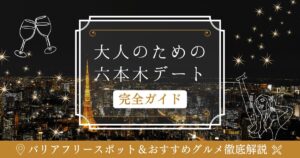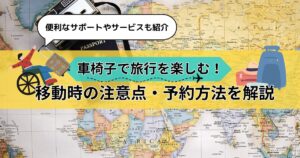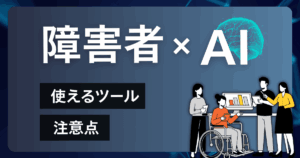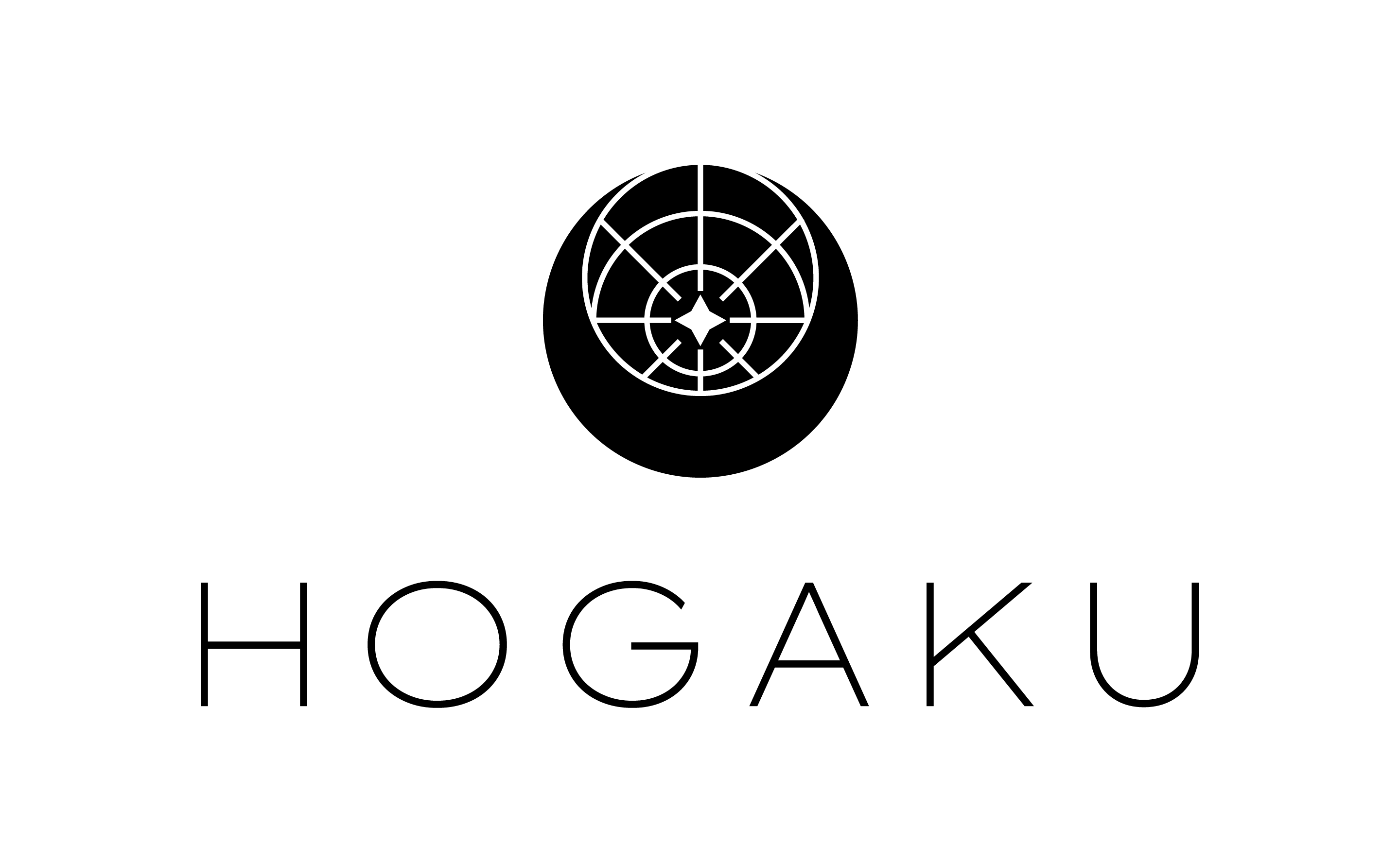障害者の就労の選択肢の一つである就労継続支援B型事業所は、一般企業などで働くことが難しい方が、福祉サービスを利用しながら働くことができる場所です。
利用を検討している方や、進路に悩まれている障害当事者の方へお届けしたい内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.工賃とは?
体調などから一般的な労働契約を結んで働くことが難しい人が、就労継続支援B型(福祉サービスの位置付け)などの就労支援を通じて生産活動(作業や仕事)を行った人に対して支払われるお金を「工賃」と呼びます。
工賃とは、工賃・賃金・給与・手当・賞与その他名称を問わず,事業者が利用者に支払うすべてのものを言います。
一般的な労働契約に基づかないため、生産物や成果に対しての対価・成果に対する報酬は賃金ではなく、工賃として考えられています。
1-1.工賃の仕組みは?
生産活動で得られた収入ー生産活動に係る事業に必要な経費(生産のための材料費・交通費・消耗品費・受注活動費・修繕費・光熱水費等)を、生産に関わった人数で配分した額が支払われます。(詳細な工賃に関しては事業所によって変動することもあります)
必要経費には事業所の職員の人件費や運営費用は含まない事としています。
したがって受託作業の売上や、物品販売による収益の合計である就労支援事業収入(売上高)が工賃の基になっています。
なお、利用者それぞれに対し支払われる1ヶ月当たりの工賃の平均額は3,000円以上という決まりがあります。しかし、最低賃金として3,000円が保証されているという意味ではないので、その点に注意することが必要になります。
このことから工賃の性格は「配分金」であると言えます。
つまり、受託作業で売上を上げつつ、生産やサービス提供に関わる経費をどれだけ抑えるかどうかが工賃配分向上のポイントになってくるのではないでしょうか。
人数を減らせばそれだけ配分される工賃が高くなるのでは?という意見もあるかと思いますが、それをしてしまうと次は障害者達の就労の機会が失われます。
障害者の雇用を守ること・工賃配分向上・事業所の運営のバランスを取ることが事業所に委ねられているということです。
1-2.工賃の平均金額
厚生労働省の資料によると、国内における工賃の平均金額は令和4年度で月額17,031円、時給換算で243円となっています。
| 施設種別 | 月額平均 | 時間額平均 | 施設数 |
| 就労継続支援B型事業所(工賃) | 17,031円 | 243円 | 15.354 |
| 就労継続支援A型事業所(賃金) | 83,551円 | 947円 | 4.196 |
令和3年度と比較すると、月額で3.2%、時間額で4.3%の上昇がみられます。
ただし、一般就労や雇用契約を結んで最低賃金が保障される就労継続支援A型と比べると金額が低い状況が続いています。
1-3.工賃は何をしたらもらえるの?
雇用契約による就労が難しい方でも、必要なサポートを受けながら生産活動を行うことで、工賃が発生します。
工賃が発生する作業は、就労継続支援事業所によって異なります。商品の袋詰めやパンの製造、ビルの清掃など、利用者の適性に応じて作業が可能です。
中にはインターネットを使った仕事に特化した事業所もあり、YouTubeのデータ分析やWEBデザイン、サイト構築などPCだけで完結する作業もあります。
このように就労継続支援事業所それぞれに特色がありました。
1-4.工賃収入と障害年金だけで障害者は生活できるの?
上記で説明した通り厚生労働省の調査結果によると、平均工賃は平成21年度から右肩上がりとなっており、令和4年は17,031円でした。
加えて、障害によっては障害基礎年金を受給できる場合があります。
ただし受給額は障害の程度によって異なり、例えば1級の場合は月に83,551円もらうことができ、工賃と合わせると約10万円の収入になるということです。
家賃を含めて食費や水道光熱費などの生活費を考えると、工賃と障害基礎年金だけでの生活は難しいという現状があります。
そのため家族の経済的支援を受けたり、グループホームに入居するケースもあります。
こうした課題を解決するため、国は「工賃向上計画支援事業」を推進し、就労継続支援事業所に経営の専門家を派遣したり、人財育成を図る研修会を実施するなどして、対策を行っているそうです。
工賃収入と障害年金を合わせて扶養に入りたいと考えている人は以下の記事をご覧ください。
参照:障害年金をもらいながら扶養に入れる?扶養の条件や制度を徹底解説!
また、すぐには厳しい現状でも、後学のために一人暮らしに必要な生活費や支援制度を知りたいという方は、以下の記事を参考にしてみてください。
参照:障害者が一人暮らしをする方法を解説!必要な生活費や支援制度も紹介
2.工賃としてお金を貰っているから確定申告の手続きは必要?

結論、状況に応じて確定申告が必要です。
通常、事業所(企業や法人)との契約に基づいて働いて得た収入は給与所得とよばれます。一方、工賃は「雇用契約を結ばない」で得る収入(お金)になるため、給与所得にはなりません。
しかし、区分としては「雑所得」という所得に含まれます。雑所得の場合、源泉徴収は行われないため、確定申告の対象になります。
源泉徴収と確定申告の考え方については、以下の別のサイトをご参照ください。
参照:源泉徴収の仕組みについて徹底解説!対象となる収入や、不要になるケースなどをご紹介|株式会社クレディセゾン
法律上では、年間で受け取った工賃が55万円(月額換算約4.58万円)以下の場合は必要ないとされています。
工賃の平均時給や働く時間などを総合的に考えると55万円以上になることは少ないと考えられ、ほとんどの場合で申告が不要のことが多い状況です。
確定申告の対象になるかわからないから困っている。そんな方は国税庁の相談窓口や、近くの税務署に問い合わせることができますので一度お電話などで問い合わせをしてみてください。
ここからは補足として、源泉徴収の考え方と確定申告の考え方について記載しています。
2-1.そもそも源泉徴収って何?
源泉徴収とは年間の所得にかかる税金(所得税)を事業者(企業や法人)が給与からあらかじめ差し引くことをいいます。従業員の給与を支払う事業者であれば、必ず行わなければなりません。
事業者が源泉徴収を行うことで、従業員は確定申告をする必要がなく、毎月の給与から少額ずつ所得税を納めることができます。また、国にとっても「安定的な税収を得る」「確実に所得税を徴収する」という意味で、源泉徴収は大きなメリットがあります。
2-2.確定申告は必要なの?
確定申告とは、「所得税を納める手続き」のことです。
雇用契約にある従業員は、会社や法人が源泉徴収と年末調整を行い、従業員全員分の所得税の申告・納税をするために、確定申告は原則として免除されます。
就労継続支援B型の工賃は、雑所得(給与によらない収入)に該当するため、収入の金額によって確定申告は必要となります。
3.就労継続支援B型と就労継続支援A型の給料の違い

A型とB型の大きな違いは、雇用契約の有無です。
A型は雇用契約を結んでいるため、最低賃金が保障された給料が報酬となります。一方でB型は雇用契約を結んで働くことが困難な方が利用するため、成果物に応じた工賃という形でもらえます。
A型と比べると金額は少ないものの、ご自身の体調に合わせて焦ることなく働くことができるのも特徴のひとつです。また作業に慣れてきたらA型へキャリアアップする選択肢もあります。
就労継続支援A型とB型の違いや利用するまでの流れを詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
参照:就労継続支援B型とは?仕事内容や就労継続支援A型、就労移行支援との違いを解説!
就労継続支援A型について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
参照:【就労継続支援A型とは?】特徴・利用対象者・メリットデメリットを紹介!
4.工賃に対する障害者の捉え方は?
生産活動や成果の対価として工賃をもらうことで、働く自信がついたり、働き続けることのモチベーションになるという声もあります。
しかし、大半の方々からは「障害者年金と工賃だけでは到底1人暮らしややりたいことや買いたいものが買えない」「結局周りの人に頼って申し訳ない気持ちになる」等、形式上では社会参加を出来ていると考えつつも、本質的な部分にフォーカスすると大きな壁があるのが現状です。
また、以下のようなネガティブな意見も目立ちました。
- 税金を納めていないので社会参加をしている気になれない
- 時給200円や時給200円以下のもっと低い賃金で働いているためモチベーションを保つのがやっと
- 上司や事業所と賃金や作業についての交渉をしても何も変わらず、反対に人間関係が悪くなり退職を検討している
就労継続支援についての在り方などについては、改善の余地があると言えます。
また、工賃向上にフォーカスされがちですが、「働き方」「本人達にしか無い価値の見出し方」など、社会参加・経済的自立・就労支援・復職支援という側面の本質を捉えるとなると課題は山積みだと言えます。
5.何故、工賃という考えが定着したのか?
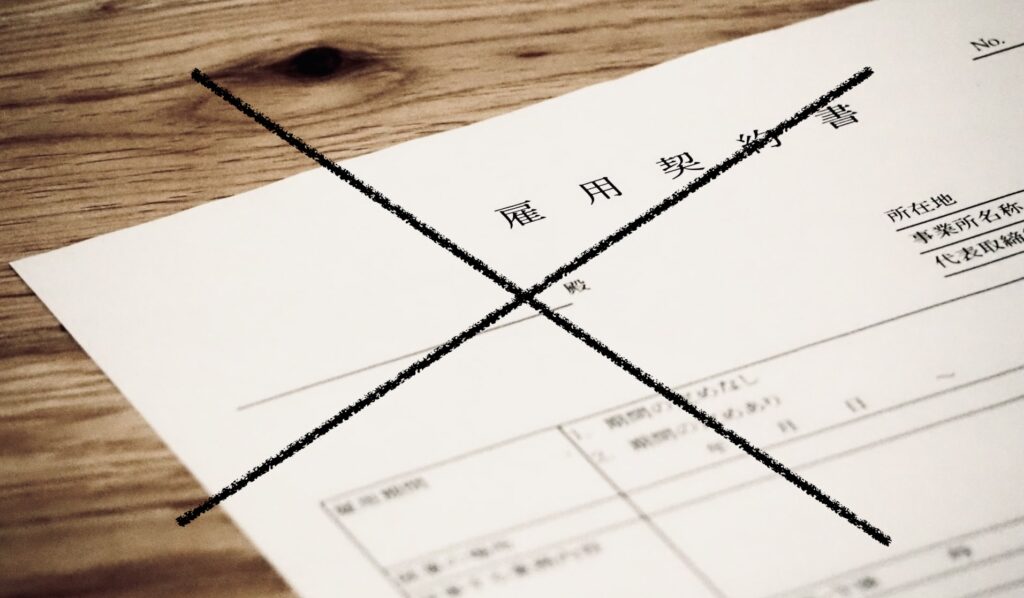
工賃という考えが定着した要因としては、以下が考えられます。
- 雇用契約を結ばない
- 仕事自体が低報酬になっている(営業活動が弱い)
- 事業所が工賃にこだわらない(企業・法人の調査不足)
- 柔軟な通所計画の代償
- 弱気な価格設定
雇用契約を結んでいないので、案件受注をした収入から必要経費を抜いた金額を利用者に配分をすれば事が足りる状況です。
それで雇用を守っているという感覚を持っている事業所も少なくないのではないでしょうか。雇用を守る事もそうですが、社会参加・利用者の価値創出などにもより着眼することで、変わってくるのではないかと思います。
また、工賃が発生する仕事の大枠は単純作業です。
単純作業が苦手な方にとってはやりがいを感じるどころか、続けていると精神的な負担が増えキャリアアップの足しにもならないと考えている人がいることも事実です。
「ここは仕事場である以前に居場所だ」「我々は居場所や雇用を提供している」として工賃より大事なものを信じている節があるようです。
極端な所では「工賃ばかりが大事ではない」と唱えている事業所もあるそうです。就労支援の上位概念にある「社会参加」「経済的自立」「就労機会を与える」等の言葉はどこに消えてしまったのでしょうか。
6.まとめ
これまでの話を踏まえ、就労継続支援において、仕事を受注すればいいという訳でもないと考えています。
仕事を得るための営業活動が上手くいかない事業所も多いと聞きます。非常に低い報酬の仕事や案件を中心に請け負ったせいで仕事量だけが膨大になっているにも関わらず、工賃は増えていないというケースが見受けられます。
安く案件を受注してしまうと事業所・利用者の利益が少なくなり、働く人のモチベーションが低くなります。
「モチベーションを高く保って仕事をしよう」などと当事者達に言っても、根本的な部分が改善されない限り難しいと考えます。
企業にとっては、障害のある方に仕事を生み出している、良いことをしているという思いがあります。
事業所の方でも、利用者さんの作業を確保しながら、安価な労働力を提供することで企業や社会に貢献できていると捉えているケースが多いです。
Ayumiからすると善意でもなんでもなく、仕事の価値・対価を正当に評価する努力を怠っていると捉えています。案件の委託等を中心に付加価値を生む努力をしていません。利用者(障害者)が置き去りになっていて、悪しき慣習ではないでしょうか。
人として当たり前の権利を、障害があるからと言って保障されないのはおかしいと考えます。
「工賃」という言葉のシステムの裏には、正義・大義名分をもとにした多くの深い闇が存在しているのです。
就労継続支援の経済循環システムで、障害福祉・社会参加・障害者雇用・自立という美辞麗句をもとに搾取を行い、誰が・どのように、利益(搾取による恩恵)を享受しているのかについて、引き続きリサーチしていきたいと思います。
また、真っ当に、真面目に就労継続支援を行っている事業者が生き残れる制度を国が変えることが出来るように、今後もAyumiなりのアプローチで推進・提言していければと思っています。