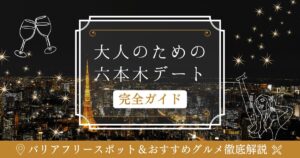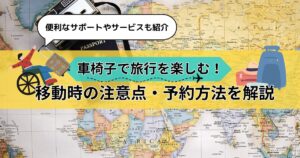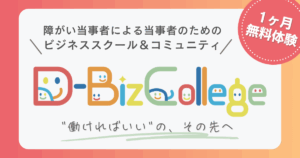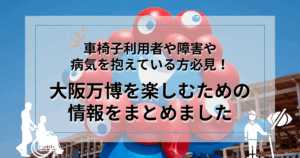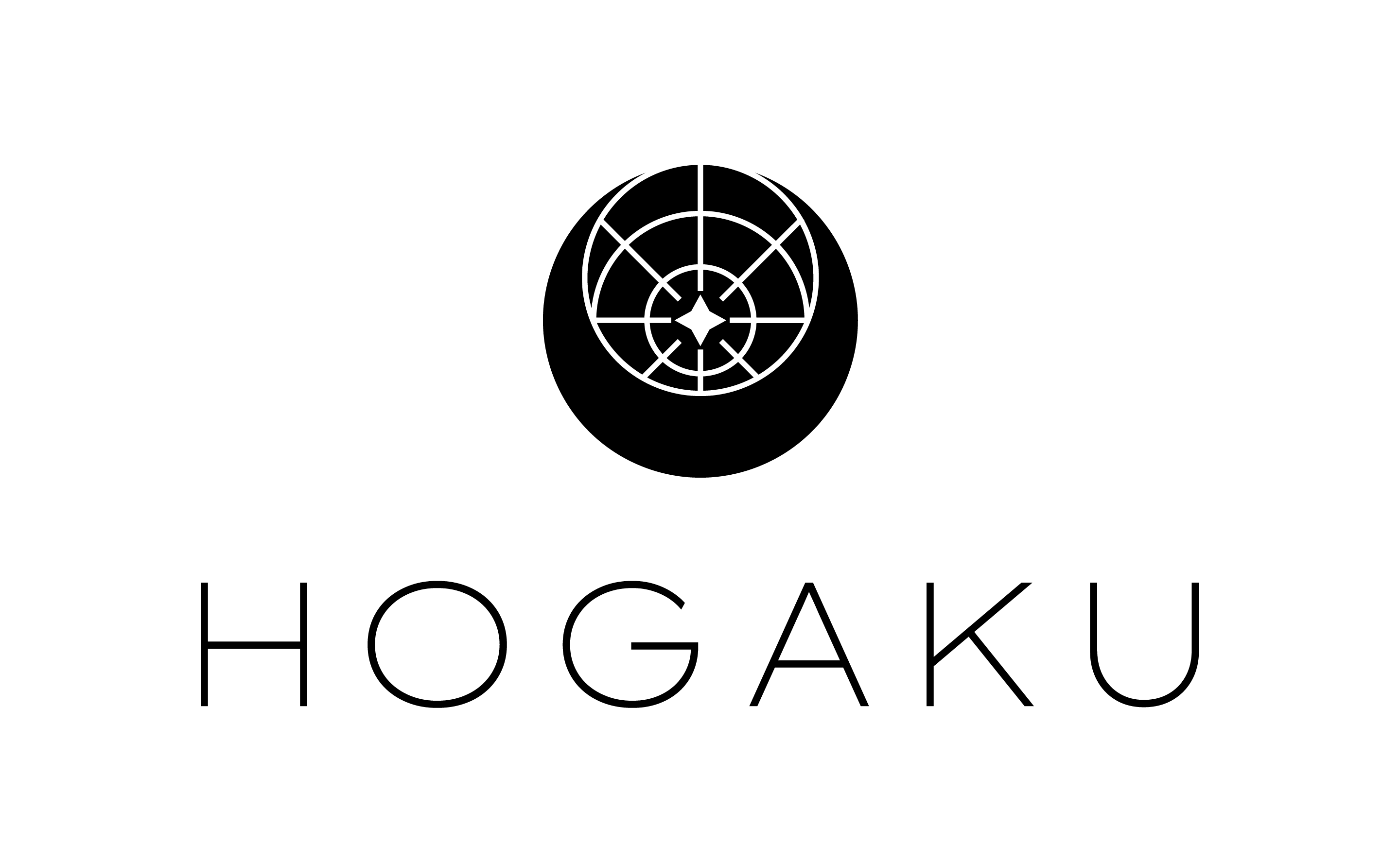障害のある方の中には、一人暮らしを考えている人や、一人暮らしをしなければならない状況下にいる人も多いのではないでしょうか?
しかし、障害者が一人暮らしをするには健常者よりも課題が多く、スムーズにいかないこともあります。
そこでこの記事では、障害者が一人暮らしをする際の注意点や、役立つサポート制度などを解説していきます。
【読者の皆様のご意見をお聞かせいただきたく、アンケートへのご協力をお願いします】
目次
1.一人暮らしをする障害者の割合
平成15年・17年・18年の内閣府調査において、身体障害者の10.9%、知的障害者の4.3%、精神障害者の17.9%が一人暮らしをしているという結果が出ています。
多くの障害者は家族との同居を選択しているようです。
精神障害者の約77%は家族と生活していて、身体障害者の多くは、配偶者との共同生活を送っています。知的障害者は、一人暮らしや配偶者との生活が少なく、親や兄弟姉妹との同居が一般的です。
その一方で、令和3年度に厚生労働省が実施した全国調査によると、グループホーム利用者約2,400人のうち「将来一人暮らしまたはパートナーと暮らしてみたい」と回答した方は約45%という結果も出ています。
参照:第1章 障害者の状況(基本的統計より)|内閣府
参照:共同生活援助に係る報酬・基準について≪論点等≫|厚生労働省
2.障害者の一人暮らしに生活費はいくら必要?
2-1.一人暮らしにかかる費用の目安
一人暮らしにかかる費用は、総務省統計局の2024年家計調査によると、1ヶ月あたり169,547円です。
過去15年の消費支出を見てみると、15〜17万円で推移しています。
一人暮らしの場合、主に賃貸物件で1部屋(1K、1DK、1LDK)に住んでいるケースが多いです。
1部屋に住む一人暮らしの人の場合の生活費の主な支出の項目と目安金額は、以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
| 家賃※ | 5〜6万円 |
| 食費 | 3.7〜4.4万円 |
| 光熱費(電気・ガス・水道) | 1〜1.4万円 |
| 通信費(携帯・ネット) | 5〜8千円 |
| 交際費その他の備品費用 | 3〜5万円 |
※家賃については「全国賃貸管理ビジネス協会」のデータを参考
参照:全国家賃動向 2025年1月調査|全国賃貸管理ビジネス協会
一人暮らしにかかる生活費は、その人の収入やライフスタイルによって大きく異なりますが、上記は一人暮らしをする際の参考になります。
家賃は、立地のいい都市部であれば高くなりますが、地方や郊外に住むことで安く抑えられます。
一人暮らしにかかるお金を把握して、準備をしておくことは大切です。
2-2.障害基礎年金や特別障害者手当は受給できる?
障害の程度によっては、障害基礎年金や特別障害者手当が受給できる可能性があります。
障害基礎年金の受給要件は次の通りです。
引用元:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間- 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
申請には、戸籍謄本や医師の診断書、病歴を記した書類などが必要になります。
障害の程度によって、1級と2級に分類され、令和6年4月時点では1級だと1,020,000円、2級だと816,000円が年間で支給されます。
障害基礎年金の申請を検討される方は、お近くの年金事務所に問い合わせてください。
また障害基礎年金と合わせて、特別障害者手当も申請すると良いでしょう。
在宅で重度な障害があり、日常生活で常に介護が必要な方が受け取れる手当金で、令和6年4月時点で月額28,840円を受け取ることが可能です。
こちらも申請には、いくつかの書類が必要です。自治体によって書類が異なるため、詳しくはお住まいの区役所に問い合わせください。
一人暮らしに必要な費用を理解し、収入の少ない人でも障害基礎年金や特別障害者手当を生活費として活用することで、障害者でも一人暮らしは可能なのです。
3.障害者が一人暮らしを始めるための準備

3-1.バリアフリーな賃貸物件探し
障害者が一人暮らしをするには、アパートや借家などの賃貸物件を借りることがほとんどです。
しかし、賃貸物件を契約するには入居審査があり、家賃が滞りなく支払える状況であるかどうかの収入面や、入居者がどのような人物であるかも審査対象になります。
審査基準は大家さんや物件状況によって異なりますが、障害者に部屋を貸すことに抵抗を感じてしまう方も少なくありません。
現在では、障害だけを理由に物件契約を断るのは、障害者差別解消法で「障害による不当な差別」という扱いになるため禁止されていますが、現状としては理解がされないことも多いのが事実です。
また、車椅子ユーザーの場合は、段差がなく移動しやすいバリアフリーな賃貸物件を探さなければなりません。
障害者の物件探しは、健常者よりも入居審査が通りづらいことに加えて、物件に対する条件も多いため、探す際には苦労することも多いでしょう。
ただ、最近では障害者の物件探しをサポートしてくれる不動産会社を探せる「FRIENDLY DOOR」のようなサービスもあるので、探しやすくなっています。
参照:FRIENDLY DOOR|不動産・住宅情報サイトLIFULL HOME’S
また、Ayumiではバリアフリーな物件を探すときの注意点や、バリアフリーな家づくりに関しての記事も掲載しているので、以下の記事も参考にしてください。
参照:バリアフリーな物件を探す時の注意点、家を探す前にこれを見て不安を解消しよう!
参照:【プロに聞きました!】障害のあるこどもとバリアフリー住宅に住む上で大事なこととは?
3-2.服薬管理や金銭管理をできるようにする
障害者が一人暮らしをする上での大きな課題は、毎日の服薬管理を含めてスケジュールを全て自分で管理して行動しなければなりません。
病院や施設であれば、看護師が服薬管理をしてくれる場合もありますが、一人暮らしになると自分で飲む時間を決める必要があります。さらに障害の程度によっては、時間通りに行動できない場合もあるでしょう。
iPhone にあるヘルスケアアプリの服薬管理機能を使うと、服薬のリマインドと服薬した時間を記録できます。 詳しくは下記の記事をご覧ください。
参照:iPhoneにバリアフリーな新機能誕生!「服薬管理」ができるように
服薬管理をしっかり行えるかどうかが、一人暮らしできるかどうかの一つの課題であり判断基準になります。
また、金銭管理については、できるだけキャッシュレス決済やICカードを使って現金を持たないようにしたり、日常生活自立支援事業を利用したり、家計簿管理アプリを使って家計簿をつけたりしながら、お金の管理ができるように工夫していく必要があります。
3-3.水道光熱費や携帯料金などの固定費の見直し
水道光熱費や携帯料金など、固定費の見直しを図ることも重要なポイントです。
水道料金については、自治体によっては障害者手帳があると割引される制度を採用している場合があります。
すべての障害者が対象となるわけではなく、以下の基準に該当する方が対象となる場合が多いです。
- 身体障害者手帳1~2級
- 療育手帳 重度以上
- 精神障害者保健福祉手帳1級
参照:水道料金の減免制度|神奈川県
参照:水道料金の一部免除制度【千葉県営水道】|千葉県
お住まいの自治体で割引制度があるかを確認し、割引の対象となる場合は積極的に利用しましょう。
一方、費用が発生しがちな電気やガス料金については、補助制度は用意されていません。
電気料金については、2016年から自由に電気会社を選択できるようになったため、電力会社と電気料金のプランを見直すことで節約に繋がります。
ガス料金も、2017年からスタートした都市ガス全面自由化により、自由に都市ガス会社を選べるようになったので、自分のライフスタイルに合致した会社やプランを選びましょう。
日々の生活に欠かせない携帯電話については、障害者向きのプランに見直すことで固定費を下げることができます。
大手キャリアでは、それぞれ以下の障害者向けプランが用意されています。
| キャリア名 | プラン名 | 内容 |
| NTTドコモ | ハーティ割引 | ・毎月の携帯電話の基本使用料を割引 ・spモードや留守番電話などの月額使用料が60%割引テレビ電話通信料が割引 ・新規契約、名義変更、機種変更、契約変更の各種手続きの手数料が無料 ・初期設定サポートが無料 ・電話番号案内「104」への通話料と番号案内料が無料 |
| au | スマイルハート割引 | ・基本料割引を187~440円割引 ・au電話への通話料/一般電話への通話料が50%割引、他社携帯電話/PHSへの通話料が20%割引 ・SMS送信料がau電話への送信料を50%割引、他社携帯電話/PHSへの送信料を20%割引 |
| SoftBank | ハートフレンド割引 | ・通話定額基本料、通話定額ライト基本料を月額料金より月1,870月割引 ・契約事務手数料や機種変更手数料などの手続き手数料無料 ・各種オプションの月額使用料を60%割引 |
上記のプランの対象者は、いずれも以下の交付を受けている方となります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特定疾患医療受給者証
- 特定疾患登録者証
- 特定医療費(指定難病)受給者証
他の割引制度と併用できるため、積極的に適用して高額となりがちな通信料金を抑えましょう。
参照:スマイルハート割引|au
参照:ハーティ割引|docomo
参照:ハートフレンド割引(スマ放題/スマ放題ライト)|SoftBank
3-4.家事・食事など自立した日常生活を送れるようにする
一人暮らしは、洗濯や部屋の掃除などの家事や毎日の食事を一人でこなしていかなければなりません。
病院や施設であれば、看護士を始め、専門スタッフの方が洗濯や家事を代わりにやってくれるでしょう。また、実家であればご家族の方が代わりにやってくれるかもしれません。
しかし、一人暮らしをする場合は、自分自身で部屋を衛生的に保ち、栄養バランスのとれた食事をとることになります。これらのことは、心身の健康を保つことにも繋がるので疎かにできません。
しかし、障害があると自力で全ての家事をするのは困難であると言えます。
そこで利用したいのが、後ほど詳しく解説する障害者が利用できる自立生活援助や居宅介護などのサポート制度です。
これらのサービスを利用することで、障害者であっても一人暮らしをすることは十分に可能です。
3-5.住所変更などの引越しや移住に必要な書類を役所に提出
引越しや移住する場合、住所の変更に関連する手続きを行う必要があります。
主なものだけでも、以下の手続きが必要です。
| 引越し前(旧居) | 引越し後(新居) |
| 転出届の提出国民健康保険の住所変更または資格喪失手続き介護保険の住所変更または資格喪失手続き印鑑登録の廃止手続き | 転居届または転入届の提出マイナンバーカードの住所変更手続き国民健康保険の加入手続き介護保険の加入手続き国民年金の住所変更手続き印鑑登録の手続き |
上記の手続きは、引越し前や引越し後の役所に出向いて手続きしなければなりません。
ただし、大半の手続きは代理人による申請を認められており、代理人に依頼すれば障害者の方が役所まで出向く必要はありません。
また、マイナポータルを経由したオンライン申請や、郵送での提出による申請なども利用できる場合があります。
4.障害者が一人暮らしをする際に注意するポイント
4-1.障害の程度を考慮する
障害者が一人暮らしする場合、障害の程度によって住む場所や施設などを決めることが重要です。
身体障害者の場合、なるべく低層階で段差が少ない場所にあるのかを重視したいものです。
また、床の段差を減らしたり、手すりを設置したりしているなど、障害の特性に合った住居を選んでください。
精神障害者の場合、症状に波があるケースが多いため、どの程度の波があるのかを考えて必要なサポート体制を整える必要があります。
また、食事の準備や掃除洗濯など、家事が無理なく行うことができるかも考えておきましょう。
4-2.家事ができるように訓練しておく
先述の通り、一人暮らしをすると、洗濯や掃除、食事の準備を基本すべて一人1人で行わなければなりません。
そこで、一人暮らしをする前に一通りの家事ができるように訓練しておきましょう。
事前に訓練しておくことで、自身の障害の程度や得意・不得意によって困難な家事も分かってきます。
もしどうしても対応できないものがあれば、後ほど紹介する自立生活援助などのサービスを利用することを検討してください。
5.障害者が一人暮らしで困ったときに相談できる窓口

障害者が一人暮らしをするにはさまざまな課題がありますが、それらを一人で解決するのには限界があります。
ここでは、障害者の一人暮らしに関する相談ができる窓口をご紹介します。
5-1.各自治体の「社会福祉課」
障害者の困りごと全般を相談できるのが、住んでいる各自治体の「社会福祉課」です。
社会福祉課は、障害を抱えた人の一般的な相談窓口として機能しています。
また、障害者の困りごとを解決するために適切な機関に繋いでくれる役割を担っているので、まずはお住まいの地域の社会福祉課に相談してみましょう。
5-2.障害者の相談窓口「基幹相談支援センター」
基幹相談支援センターとは、障害者やその家族の支援業務を行っている施設です。
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的役割を担っており、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する相談等の業務を総合的に行っています。
また、病院や施設と連携した地域移行・地域定着支援、障害者に対する虐待や権利の保護に関する相談支援を行っています。
基幹相談支援センターは、単独ではなく役所や公共施設に併設されていることがほとんどです。
そのため、相談したい場合は市町村役場に問い合わせてみましょう。
5-3.障害者の支援計画をサポートしてくれる「特定相談支援事業所」
特定相談支援事業所とは、相談支援センターとも呼ばれており、障害福祉サービスを利用する際の相談窓口です。
障害者が一人暮らしをする際には、さまざまな障害福祉サービスが受けられます。
障害福祉サービスを受けるには「サービス等利用計画」を作成し、市町村に提出する必要があります。
利用計画は自分でも作成可能ですが、どのような支援を受ければいいのかわからないという方も多いでしょう。
そこで、特定相談支援事業所に相談することで、自分に合った障害福祉サービスを教えてくれたり、計画書類作成のサポートをしたりしてくれます。
5-4.地域で暮らし続けるためのサポート支援をしてくれる「一般相談支援事業所」
一般相談支援事業所とは、障害者が地域で暮らしていけるようにサポートする機関です。
一般相談支援事業所は、色々な相談ができる「基本相談支援」に加えて、「地域移行支援」と「地域定着支援」の役割をになっています。
地域移行支援は、障害者が病院や施設を出てから地域生活に移行するための居住支援を行います。
地域定着支援は、一人暮らしの障害者や家族と同居していても障害や疾病などの関係で支援対象者が対応できない場合の緊急訪問や、緊急対応などをサポートしてくれるのが特徴です。
6.障害者が一人暮らしをする際に受けられるサポート制度

6-1.自立生活援助
自立生活援助とは、一人暮らしをしている又はしようとしている障害者に対して一定期間の間、職員の巡回訪問や支援を行う制度です。
定期的に一人暮らしの障害者の自宅を訪問し、生活をしている上での困りごとへの助言や問題解決のための情報提供などを行います。
自立生活援助の対象者となる方は、以下の通りです。
- 障害者支援施設やグループホームから一人暮らしに移行する人
- 既に一人暮らしをしているが地域生活に不安がある人
- 同居している家族の支援が得られずに実質一人暮らしの状況の人
上記のように自立生活援助は、一人暮らしをしているかどうかに関わらず、家族と同居していても十分な支援が受けられない障害者も対象となります。
そのため、一人暮らしに限らず幅広い生活での問題を抱えた人の制度として、自立生活援助は位置付けられています。
6-2.日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは、高齢や障害によって一人で日常生活を送ることに不安を感じている人が、社会福祉協議会との契約に基づき金銭管理や重要書類の保管・管理を行うサービスです。
対象者は、軽度の認知症や知的障害および預金管理や重要書類の取り扱いに不安がある方です。
また、認知症や知的障害の診断を受けていなくても、必要であれば利用できます。
日常生活自立支援事業の具体的なサービス内容は、以下の通りです。
- 福祉利用サービスに関する情報提供
- 郵便物の確認
- 住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供
- クーリングオフ制度の手続き
- 住民票提出などの行政書類の手続き
- 医療費や公共料金などの支払い
- 年金・福祉手当に関する手続き
- 預貯金通帳や実印などの重要書類の保管・管理
これらのサービスは、いずれも本人が利用内容を理解していることと、利用意思が明確であることが前提です。
利用内容の理解ができない、判断能力がないと判断される場合は「成年後見制度」の利用を検討します。
6-3.居宅介護支援
居宅介護とは、障害者が地域生活を安心して送るための障害福祉サービスの一つです。
利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された人および、同等の障害を持つ18歳未満の障害児となります。
また、指定難病やその他特殊な疾病、事故などにより四肢や視覚障害となり、障害支援区分認定された人も居宅介護の対象者です。
居宅介護の具体的なサービス内容には、以下が含まれています。
- 身体介護:入浴、排せつ、食事等の介助
- 家事援助:調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などの援助
- 通院等介助:通院などへの付き添い
その他、生活に関わる全般の行動介助や相談、助言なども居宅介護支援のサポート範囲です。
6-4.移動支援
移動支援とは、単独で外出が困難な障害者に対してヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介助を支援するサービスです。
利用の対象となる人は、各自治体によって異なります。
たとえば、静岡県富士市の場合、身体障害における移動支援の対象となる障害者の要件は以下の3つに該当する人です。
引用元:移動支援事業について|富士市
- 身体障害者手帳の両下肢障害で1級又は2級に該当する重度の身体障害。
- 「社会生活上必要不可欠な外出」及び「社会参加のための外出」の支援が必要と認められる人。
- 適切な介護者を得ることができない場合。
移動支援サービスは、社会参加や余暇活動を楽しむためには必要不可欠であり、障害者の地域生活を支える制度です。
6-5.地域生活支援事業
地域生活支援事業とは、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、市区町村や都道府県が独自に行うサービスです。
たとえば、地域生活に伴う相談や日常生活用具給付等など、障害者の日常生活をサポートするような事業を行っています。
また、地域活動支援センターの運営を行い、障害者の創作・生産活動を促進する事業もあります。
6-6.重度訪問介護
常に介護を必要とする重度障害者の方は、親亡き後に施設やグループホームに入るしか選択肢がないと思っている方も多いでしょう。
しかし、重度な障害を抱えていても適切な支援制度を受けることで、一人暮らしは可能です。
重度な障害を持っていて、地域社会で一人暮らしをしたい方は「重度訪問介護」という制度を利用します。
Ayumiのライターの赤石さんも重度訪問介護を使って生活している一人です。
ヘルパーさんとどのように日常生活を送っているのかが気になる方は、下記動画で1日ルーティンを見れるのでご覧ください。
重度訪問介護の対象者は、障害支援区分4以上で以下のいずれかに該当する人です。
引用元:重度訪問介護|厚生労働省
- 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
重度訪問介護は、24時間365日の介護サービスが受けられる制度なので、重度障害者の方でも安心して一人暮らしができます。
また、利用料については低所得者の場合、原則無料です。
ただし、世帯収入が一定以上ある場合は、月9,300円〜最大3万7,200円の負担が発生します。
参照:(6) サービス利用料|居宅介護・重度訪問介護事業の手引き|豊島区
6-7.生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、障害者世帯や低所得世帯、高齢者世帯に対して資金の貸付けと必要な相談支援を行い、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図ることで安定した生活を送れるようにサポートする制度です。
生活福祉資金貸付制度では、総合支援資金として以下3つの資金を援助しています。
- 生活支援費
- 住宅入居費
- 一時生活再建費
また、福祉資金として生業を営むために必要な経費や障害者サービスを受けるために必要な経費をまかなえる福祉費、緊急小口資金についても援助されます。
「障害者世帯」とは、具体的に以下の交付を受けた者が属する世帯となります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
実際に生活福祉資金貸付制度を活用して借り入れしたい場合、世帯の居住地を担当する民生委員を通じて実施されます。
そして、市町村社会福祉協議会を経由し、都道府県社会福祉協議会で貸付けが最終決定されます。
6-8.生活保護制度
生活保護制度とは、資産や能力などをすべて活用しても生活に困窮している人を救済する制度のことです。
困窮の程度に応じて必要な保護を実施し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護の要件として、以下を満たしている必要があります。
| 種類 | 生活保護の要件 |
| 資産の活用 | 最低限度の生活をするために所有する資産は、一定の場合を除き原則として処分した上で、生活の維持のため活用する必要がある |
| 能力の活用 | 働く能力がある人は能力に応じ働いて収入を得ていること、及び仕事が見つからない人は求職活動をすること。働く能力を活用しない人は生活保護を受けられない |
| 扶養義務者による扶養 | 親や子、兄弟姉妹などの援助を受けられるケースでは、優先してその援助を受けること |
| 他の法律による給付等の優先 | 生活保護法を除いた法律や制度で給付等を受けられる場合、優先してその手続きを行うこと |
上記要件を満たした上で、世帯の収入と厚生労働大臣が定めている基準により計算される最低生活費を比較し、収入が最低生活費に満たないケースで生活保護が適用されます。
生活保護には以下8つの種類があり、障害者の場合は主に介護扶助や医療扶助などで活用可能です。
| 扶助の名称 | 内容 |
| 生活扶助 | 食事、被服費、光熱水費等 |
| 住宅扶助 | 家賃、敷金、住宅の改修費等 |
| 教育扶助 | 学用品費、給食費などの義務教育就学費 |
| 介護扶助 | 介護サービス利用にかかる費用 |
| 医療扶助 | 医療機関における診療、治療等の費用 |
| 出産扶助 | 出産時の入院、衛生品費等 |
| 生業扶助 | 技能習得費、高等学校等就学費等 |
| 葬祭扶助 | 死亡時の火葬、死体運搬費等 |
生活保護を申請する際、事前に民生委員または区役所の福祉事務所に相談しましょう。
次に、福祉事務所の窓口で正式に生活保護を受けたい旨を伝えた後、ケースワーカーからの家庭訪問を受けるとともに、扶養調査と金融機関への調査が行われます。
そして、審査の結果が通知されて、審査に通過したら受給開始されます。
参照:生活保護制度|厚生労働省
7.まとめ
今回は、障害者の一人暮らしをテーマに、頼れる支援制度や生活での注意点をお伝えしました。
障害者であっても、自分に合った支援制度を利用することで一人暮らしは実現できます。
制度を利用しながら自立した生活を送ることは、人間的にも成長できるいい機会です。
この記事が「病院や施設でしか生活できる場所がない」と思っている障害者の方の新しい選択肢のひとつになれば幸いです。
また、Ayumiでは障害者手帳で受けられるサービスについてもご紹介しています。こちらも併せてお読みいただき、一人暮らしを行う上で少しでもお役に立てると嬉しいです。